「個人主義・集団主義・全体主義の意味や違いって何だろ~? 。゚(゚^o^゚)゚。 」
「それぞれの意味や違いぐらい知っているつもりだったんだけど、実は理解できていなかったのかも!?って感じちゃう時があるんだよねー ヽ(;▽;)ノ 」
「日本は集団主義の国、欧米は個人主義の国って聞くけど、それって本当なのかな~?どーも違和感があるんだけど・・・? (;゜д゜) 」
「集団主義・全体主義 = 協調性もあるし仲間意識もあるから組織力も高くて強い組織がつくれる、個人主義 = 協調性がなくてワガママで自分勝手だから組織力も低くて弱い組織になりやすいって聞くこともあるんだけど、それって本当にそうなんだろーか???なーんか違うような気がするんだけど??? (;゜∇゜) 」
「日本人は集団主義で全体主義で、海外の人は個人主義だよなーって、海外に行く前は思っていたんだけど、今はどっちかってゆーと、日本人は全体主義だけど集団主義とか個人主義とかって感じじゃなくて、海外の人は全体主義を毛嫌いしていて個人主義だけど集団主義って感じがしなくもないんだけど・・・? (;・∀・) 」
「海外の人の方が個人主義って聞くけど、実は日本人の方がずっとずっと個人主義なのかも!?って感じることもあるんだけど・・・? o( ̄_ ̄|||)o— 」
などなど・・・
「経営理念・ビジョン・経営計画等の作成」、「組織人事戦略(戦略的な組織づくり)」、「組織力の強化や向上」、「組織人事戦略(戦略的な組織づくり)」、「経営に役立つ情報活用(IT活用・ICT活用)」などのお手伝いを行なっているからなのか・・・
日本国内・海外問わず、世界各国の方々へ「自律型人材育成」のお手伝いをした経験があるからなのか・・・
海外赴任の経験があるからなのか・・・
このような声をお聞きすることもあるんですけど・・・
んでもって、いろんな意味で考えさせられることもあるんですけど・・・
フムフムフーム (`・ω・´) フムフムフーム
こーゆー疑問って意外と大事
なのかも~???
(〃⌒∇⌒)ゞ
日本にずっと住んでいたり、日本人としか接することがなかったりしたら、気づかないことだってあるのかも~???
それが常識だし、普通だし当たり前だしって、思い込みしちゃっていることだってあるのかも~???
なーんて、感じることもあるのと・・・
ヾ( ̄ω ̄〃)ノ
それに、実はコレってもしかしたら・・・










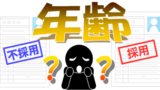







などなどにも、ある意味関係するっちゃーする面もあるのかも~???
なーんて、感じることもあるので・・・
個人主義って、いったい何なんだろーか?
集団主義って、いったい何なんだろーか?
全体主義って、いったい何なんだろーか?
何がどう違うんだろーか?
個人主義やら集団主義やら全体主義やらって、組織力や現場力などとは何がどう関係するんだろーか?
個人主義やら集団主義やら全体主義やらって、教育(共育)とは何がどう関係するんだろーか?
強い組織とか弱い組織とかって何なんだろーか?
強い組織なのか弱い組織なのかって、どんな基準でどう判断するんだろーか?
そもそもの話、組織って何のためにつくるんだろーか?
誰のために、組織をつくるんだろーか?
組織だからできることって、いったい何なんだろーか?
組織でなくてもできることって、いったい何なんだろーか?
などなども含めて、一緒に考えてみません? (^^)
あ、モチロン、「自律的に」という意味で。
ちょっと興味あるかも~?
って言ってくださる方は、お付き合いいただけると嬉しいです。
(^^)/
個人主義、集団主義、全体主義の違いと組織力などとの関係って何だろう?(パート1)
んーと・・・
自分自身の中に意外なヒントがある
かもしれないし・・・
それに、もしかしたら・・・
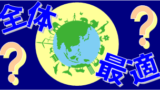



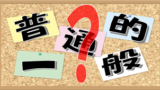


なんかにも、ある意味、関係するっちゃーする面もあるのかもしれないし・・・
( ・ _ ・ )
視点が変われば何か気づくこともあるかもしれないので、まずは身近なところから考えてみるのはどーでしょう?
(⌒▽⌒)ノ
以下の中で、個人主義・集団主義・全体主義のそれぞれのイメージに近いかも~?って感じるのはどれでしょーか?
組織力なんかとも関係しているのかも~?って感じるのはどれでしょーか?
o(*⌒O⌒)b
みなさまだったら、どんな時に、
「コレって、個人主義と関係あるように感じるよなー」
「コレって、集団主義と関係あるように感じるよなー」
「コレって、全体主義と関係あるように感じるよなー」
「コレって、個人主義・集団主義・全体主義のどれにも関係していないように感じるかも~?」
「コレって、組織力なんかとも関係しているのかも~?」
「コレは、組織力なんかとは関係していないのかも~?」
って、感じるでしょーか?
また、その理由は何でしょーか?
「個人主義・集団主義・全体主義の意味も違いも全然わからないんだけど!? (;゜д゜) 」って場合は、ココのパート1は一旦すっ飛ばして、パート2をご覧いただいてから、パート1に戻って来てやってくらぱいませませ~っっ。 (⌒人⌒)
- 履歴書を手書きでカキカキしている時
- 履歴書をパソコンでカキカキしている時
- 職務経歴書を作成している時
- エントリーシートを作成している時
- 就活塾に参加している時
- リクルートスーツを着て、就職活動や転職活動をしている時
- 面接で、自己PRをしている時
- 入社式に参加している時
- 災害等により通勤電車がストップしている、または、めちゃくちゃ遅れているのに、それでも出勤しなければならない時
- 通勤電車が遅れたため、遅延証明書をもらおうと列に並んでいる時
- 病気で熱もあるけど出勤するのが当たり前と思う時
- 病気で熱があるから欠勤するのが当たり前と思う時
- みんなが残業していても、残業しないで帰る人を見かけた時
- みんなが残業しているから、一緒に残業しているという人を見かけた時
- 必要であれば残業はするけど、残業代はきっちり請求する人を見かけた時
- 何があっても、どんな状況であっても、絶対に残業しない人を見かけた時
- 特に急ぐ仕事ではないけど、あえて残業する人を見かけた時
- サービス残業を要求する人を見かけた時
- サービス残業を断る人を見かけた時
- サービス残業を自主的に喜んで行う人を見かけた時
- 長時間労働や徹夜を自慢する人を見かけた時
- 仕事よりもプライベートを優先する人を見かけた時
- プライベートよりも仕事を優先する人を見かけた時
- 有給休暇を毎年のように100%取得する人を見かけた時
- 有給休暇を取得したいのに、全く取得させてもらえない時
- 有給休暇を取得する理由を、アレコレと詮索される時
- 育児・介護休業を申請する時
- 育児・介護休業を申請する人を見かけた時
- 配偶者に頼まれているにもかかわらず、育児・介護休業を絶対に取らない人を見かけた時
- 育児・介護休業を取らせない人を見かけた時
- 公私混同に腹が立つ時
- 公私混同に共感する時
- 協調性のない人を見かけた時
- 協調性のある人を見かけた時
- 忖度する人を見かけた時
- 一切忖度しない人を見かけた時
- 主体性のない人を見かけた時
- 主体性のある人を見かけた時
- 会議で積極的に発言する人を見かけた時
- 会議で一切発言しない人を見かけた時
- 会議がイヤだと文句を言っている人を見かけた時
- 会議で内職している人や居眠りしている人を見かけた時
- 仲間意識や愛社精神を持つのが当たり前だと思っている人を見かけた時
- 仲間意識や愛社精神など必要ないと思っている人を見かけた時
- イエスマンを見かけた時
- 面従腹背の人を見かけた時
- 不平・不満があるのに、誰にも愚痴らず我慢している人を見かけた時
- 不平・不満がたくさんあり、毎日のように愚痴りまくっている人を見かけた時
- 無気力でやる気がなさそうな人を見かけた時
- 失敗した人をつるし上げる人を見かけた時
- 失敗した人のつるし上げを、自分自身も一緒になって行う時
- 失敗して落ち込んでいる人をスルーする時
- 失敗して落ち込んでいる人を気遣う時
- 下請けいじめを行う会社を見かけた時
- 下請けいじめをされているが、必死に耐えている下請企業を見かけた時
- 自分自身がいじめられている時
- 誰かをいじめている人を見かけた時
- いじめられている人を見かけて、自身がいじめを止める時
- いじめられている人を見かけて、自身が誰かに相談する時
- いじめられている人を見かけたが、とばっちりを受けたくないからなどの理由で見て見ぬ振りをする時
- いじめられている人を見かけて、自身も一緒になっていじめる時
- 誰にも相談しない人は自己責任だと思う時
- 誰にも相談しない人を気遣う時
- 他者に迷惑をかけるのは良くないと思う時
- 他者に迷惑をかけられても構わないが、自分が誰かに迷惑をかけるのはイヤだと思う時
- 他者に迷惑をかけられるのも、自分が誰かに迷惑をかけるのもイヤだと思う時
- 他者に迷惑をかけてもかけられても、持ちつ持たれつと思う時
- バイトテロを行っている人を見かけた時
- バイトテロを行っている人を黙認する時
- バイトテロを行っている人に注意する時
- コンプライアンス違反に該当する行為を見かけた時
- コンプライアンス違反に該当する行為を、自分自身も行っている時
- コンプライアンス違反に該当する行為を、見て見ぬ振りをする時
- コンプライアンス違反に該当する行為を、内部告発する人を見て腹が立つ時
- コンプライアンス違反に該当する行為を、内部告発する人を見て賛同する時
- コンプライアンス違反に該当する行為を、自身が内部告発する時
- 管理職になりたくない人を見て、腹が立つ時
- 管理職になりたくない人を見て、共感する時
- パワハラ(パワーハラスメント)を行っている人を見て、腹が立つ時
- パワハラ(パワーハラスメント)を行っている人を見て、共感する時
- うつ病で休職する人を見て、腹が立つ時
- うつ病で休職する人を見て、共感する時
- 会社を辞める人を見て、腹が立つ時
- 会社を辞める人を見て、共感する時
- カスハラ(カスタマーハラスメント)を見て、腹が立つ時
- カスハラ(カスタマーハラスメント)を見て、共感する時
- お客様は神様だと思う時
- お客様は神様ではないと思う時
- 商品を選ぶ際に、コスパを最優先に考える時
- 商品を選ぶ際に、コスパ以外を最優先に考える時
- ブランド名や知名度などを優先される人を見かけた時
- ブランド名や知名度などよりも、中身を優先される人を見かけた時
- 何を言ったかよりも、誰が言ったかを大切にする人を見かけた時
- 誰が言ったかよりも、何を言ったかを大切にする人を見かけた時
- 社会的に不利な立場にある人を、気遣う行為を行う人を見かけた時
- 社会的に不利な立場にある人を見かけても、スルーする人を見かけた時
- 社会的に不利な立場にある人をわざと狙って攻撃する人を見かけた時
- 社会的に不利な立場にある人のために、ボランティアや寄付などを行う時
- 社会的に不利な立場にある人のために、ボランティアや寄付などは行う必要などないと思う時
- みんなと同じであることに、安心する時
- みんなと違うことに、安心する時
- 日本スゴイ!って言っている人を見かけた時
- 日本サイテー!って言っている人を見かけた時
- 自国ファーストの国について、腹が立つ時
- 自国ファーストの国について、共感できる時
- 日本にしか興味がなく、日本が世界で一番いい国だし、海外に行く必要もなければ海外のことを知る必要もないと思う時
- 日本はいい国だとは思うし、日本にずっといたいとはものの、世界を知らなければいけないと言っている人を見かけた時
- 日本は全然いい国ではないから、海外に行きたいと言っている人を見かけた時
- たとえ業務命令であっても海外には絶対に行きたくないし、もしも海外赴任を命じられたら会社を絶対に辞めてやる!と言っている人を見かけた時
- 本当は海外赴任をしたくないけど、業務命令だから渋々従うと言っている人を見かけた時
- 海外で不幸な出来事に見舞われても、それは自己責任だと言っている人を見かけた時
- 海外で不幸な出来事に見舞われた人を悼む人を見かけた時
- 移民を一切受け入れるべきではないと言っている人を見かけた時
- 移民を受け入れるべきと言っている人を見かけた時
- 難民を一切受け入れるべきではないと言っている人を見かけた時
- 難民を受け入れるべきと言っている人を見かけた時
個人主義、集団主義、全体主義の違いと組織力などとの関係って何だろう?(パート2)
うーむ・・・
どっ・・・、どーでしょう???
「ううーむ・・・、 個人主義・集団主義・全体主義のそれぞれ意味や違いがわかっていると思っていたけど、実はわかっていなかったのかも・・・!? (;・∀・) 」
「もしかしたら、思い込みしちゃっていたのかも!? ( ̄○ ̄;) 」
という方も、いらっしゃれば・・・
「コレってやっぱ、個人主義と関係していると思うんだけどなー (; ̄ェ ̄)」
「いやいや、コレってやっぱ集団主義と関係していると思うよなー ( ̄‥ ̄;) 」
という方も、いらっしゃれば・・・
「個人主義はわかるんだけどさー、ワガママってことだと思うしぃ~ 。゚(゚^o^゚)゚。 」
「だけど、集団主義と全体主義の違いがわかりそうでわからないんだよなー (^∀^|||) 」
という方も、いらっしゃれば・・・
「コレって、組織力なんかとも関係しているんじゃないのかな~? (´ε`;) 」
「コレは、組織力なんかとは関係ないような気がするんだけど? (´-ω-`) 」
という方も、いらっしゃれば・・・
「ナルホド・・・、ちょっぴりわかった気がするかも・・・ ヽ(´ー`)ノ 」
「あ、なーんだー、そーだったんだ~ (〃▽〃) 」
という方も、いらっしゃれば・・・
「わかったよーなわからんよーな・・・ ( ̄д ̄;) 」
「やっぱ、頭がウニ状態じゃー!よくわからーん! \(  ̄曲 ̄)/ 」
という方も、いらっしゃるんじゃーないでしょうか?
(^^)
で・・・、もしかしたら・・・

なんかにも、ある意味関係するかもしれないので、例えばこんなのからも考えてみるのはどーでしょう?
(。・ω・)b
個人主義とは?
○ Weblio辞書
- 個々の人格を至上のものとして個人の良心と自由による思想・行為を重視し、そこに義務と責任の発現を考える立場
- その人の属している組織全体・社会全体のことを顧慮せずに、個人の考えや利益を貫く自分勝手な態度
○ ウィキペディア
個人主義とは、国家や社会の権威に対して個人の権利と自由を尊重することを主張する立場。
あるいは共同体や国家、民族、家の重要性の根拠を個人の尊厳に求め、その権利と義務の発生原理を説く思想。
個人主義と「利己主義」は同一ではない。
個人の利益・欲としての幸福だけが道徳の規準になるとすれば、それはエゴイズム・利己主義であり、幸福がもっぱら自己の快楽であるとされれば、それは快楽主義・享楽主義である。
個人主義は個人の自立独行、私生活の保全、相互尊重、自分の意見を表明する、周囲の圧力をかわす、チームワーク、男女の平等、自由意志、自由貿易に大きな価値を置いている。
個人主義者はまた、各人または各家庭は所有物を獲得したり、それを彼らの思うままに管理し処分する便宜を最大限に享受する所有システムを含意している。
個人主義という語は多義的であって、個人が至高の価値を有するという道徳原理、自己発展、自律性、プライバシー等の観念が結びついている。
利己主義とは?
○ goo辞書
社会や他人のことを考えず、自分の利益や快楽だけを追求する考え方。
また、他人の迷惑を考えずわがまま勝手に振る舞うやり方。
エゴイズム。
○ Weblio辞書
自分の利益を最優先にし、他人や社会全般の利害など考えようとしない態度。
身勝手な考え方。
エゴイズム。
自己主義。
○ ウィキペディア
利己主義は、自己の利益を重視し、他者の利益を軽視、無視する考え方。
「利己主義」は英語のegoism(エゴイズム)におおよそ相当するが、英語の “ego-ism” は ” 己-主義 ” ということであり、日本語よりもさらに広い範囲を指すので若干注意を要する。
他者の不利益を求める悪、万人の利益を求める功利主義とは区別される。
利己主義は、心理的利己主義 と 倫理的利己主義 の二種類に分類されている。
心理的利己主義とは?
心理的利己主義は、「人間の行為は自分自身の利害に現に常に動機付けられている」とする見解。
倫理的利己主義とは?
倫理的利己主義は、「人の行為は自分自身の利害に動機付けられるべきである」とする倫理学上の立場である。
ただし実際には、社会に利益をもたらせば、めぐりめぐって自分の利益として戻ってくることが多く、また自身の利己的な行動が周囲の行動へと伝染し、他者の利己的な行動を誘発し、めぐりめぐって自己の不利益ともなるので、利己主義(者)であっても、左記を理解し長期的な合理性を考慮し行動をする者に限定すれば、結果は(ある程度)利他的になるとも考えられている。
集団主義とは?
○ コトバンク
日本的経営の特質の一つとして欧米の個人主義に対比して用いられる言葉。
個人と集団の関係において、個人は集団と心理的な一体感をもつとともに集団の目標や利害を自分のものよりも優先させていくという集団中心の考え方。
○ はてなキーワード
個人よりも集団に価値を置く考え方、あるいは自分の利害よりも自分の属する集団の利益を優先する価値観。
○ Weblio辞書
集団主義とは個人よりも集団に価値を置く思想や、その傾向を指す用語。
全体主義とは?
○ Weblio辞書
個人は全体を構成する部分であるとし、個人の一切の活動は、全体の成長・発展のために行われなければならないという思想または体制。
国家・民族を優先し、個人の自由・権利は無視される。
個人主義、集団主義、全体主義の違いと組織力などとの関係って何だろう?(パート3)
うーむ・・・
どっ・・・、どーでしょう???
「そっ・・・、そーだったのかー! ガ━━(= ̄□ ̄=)━━ン!! 」
「うぉぉぉー!!思いっきり勘違いしていたのかも!? ヾ(.;.;゜Д゜)ノ 」
という方も、いらっしゃれば・・・
「もしかしたら、ガラパゴス化とか井の中の蛙とかとも関係するんだろーか??? (´._.`) 」
「もしかして、出る杭は打たれるとも関係しているんだろーか??? ( ー`ω´ー ) 」
という方も、いらっしゃれば・・・
「ん?ってコトはだよ・・・??? ( ̄∧ ̄ ) 」
「ありりぃ~!?んじゃー、コレってどーなんだろ~??? ?(゚_。)?(。_゚)? 」
という方も、いらっしゃれば・・・
「ナルホド・・・、ちょっぴりわかった気がするかも・・・ ヽ(´ー`)ノ 」
「あ、なーんだー、そーだったんだ~ (〃▽〃) 」
という方も、いらっしゃれば・・・
「わかったよーなわからんよーな・・・ ( ̄д ̄;) 」
「やっぱ、頭がウニ状態じゃー!よくわからーん! \(  ̄曲 ̄)/ 」
という方も、いらっしゃるんじゃーないでしょうか?
んでもって・・・
例えばこんなのからも考えてみるのはどーでしょう?
( っ・ω・)っ
集団主義を温存したままの成果主義 = 個人主義が生み出す矛盾
■ 「職場いじめ ― あなたの上司はなぜキレる」
日本的労務管理の弊害が声高に言われるようになった。
その理由は色々とあるが、ひとことで言えば経営環境の変化にともない、これまでのやり方が通用しなくなったり、むしろ弊害をもたらすようなことが起こるようになってきたからである。
これまでは長所としてもてはやされてきたことが、逆に短所となりはじめてきているということである。
ニーズが多様化して、それに応じた多種類の少量生産という小回りのきく生産体制には、集団主義的な行動様式はマイナスに働くことになる。
今日求められていることは、集団でどのように行動するかではなく、個人個人がそれぞれの能力や特性を発揮し、その総合力をどのように発揮していくのか、ということである。
日本の企業社会は、一種のセレモニー化した規範を確立して協調性を大切にしてきた。
そして、こうした企業内の協調性を土台にした人間関係が集団主義を支えてきた。
しかし、この一見まさに集団主義的で協調的に見える行動も、その基準は実は自分の打算によっている。
一見企業へのロイヤリティを軸にした統一した行動に見えても、その原理となっているのは、その行動が己の打算にかなうかどうかである。
つまり、個人としては嫌であっても、出世や仕事にいい効果をもたらすということで参加してきた。
自分だけが仲間と違う行動を取るのはまずいという判断で、自分を殺して参加していることが多かった。
逆に言えば、拒否が自らの利益につながらない場合や、そうした利益を無視しても参加したくない譲れない哲学がある場合には、拒否することもあるだろうということである。
日本人の多くは、実は自分自身は集団主義的な人間だなどとは思っていないという不思議な現実がある。
むしろ、個人個人に聞けば、「日本的集団主義には辟易していて、何とかそういう呪縛から自由になりたかった」などと語ることが多い。
それどころか、「日本人全体が集団主義である」ことは認めても、「自分は、そうした生き方に仕方なく従っているが、本当は違う」と感じている人のほうが多いのが現実であろう。
今、職場に起きていることは、集団主義の揺らぎに対しては「以前から望んでいなかったことだから」と肯定しつつも、今度は「そうは言っても個人主義的に飛び出した行動をすることが本当に利益なのかどうか」を見定めている状態なのだと言ってもいい。
まさに、職場は今、集団主義から個人主義、そして年功序列から成果主義を典型とする変化を前に、自らがどのように協調性を発揮すればいいのか分からず、立ちすくんでる状態なのだ。
古い価値観の集団主義や協調性というしがらみを捨てようとしながらも、なお、その一方でしがみつくという混乱と矛盾の中にいるのだと言ってもいい。
成果主義の重視する個人主義がこれまでの集団主義と軋轢を起こしはじめ、実力発揮が集団主義の厚い壁に頭をぶつけることになってしまった。
日本企業の背骨ともいうべき集団主義を温存したままでの成果主義 = 個人主義は職場に矛盾を生み出したのである。
したがってそこでは、まさに実力を発揮するには、集団から疎まれない形での実力発揮が求められ、そこでの評価は集団への迎合を含むことを了解することになった。
こうした現状はまさに制度としての矛盾になる。
つまり、成果主義とは、本来は何物にもとらわれず、己の実力をそのまま発揮して、それが客観的に評価されるシステムであるはずが、そこに歪みが生じてしまったのだと言ってもいい。
それでもその制度を信じて個人主義を貫こうとする人たちにとっては、過酷な時代になろうとしている。
本来の実力を発揮するには、集団主義の壁を突き抜けるために通常以上の力が求められることになるからである。
個人主義を貫くには周囲からの同調圧力に屈しない精神力が求められる。
その一方で、これまでは年功序列と集団主義意識のもとで、企業への帰属意識だけで生きてきた中高年にとっても過酷な環境となってきた。
まさに、職場が居心地の悪い落ち着かない場所となってきたからである。
新しい制度への不安や、失われたものへの喪失感によるイライラは、ストレスとなって職場環境を悪化させている。
そして、帰属への不安によって彼らの不満は増幅され、年功序列制度や集団主義への強烈な回帰への願望を募らせている。
その葛藤が陰湿ないじめや、その結果としてのメンタルストレスを呼び込むことになっているのだ。
集団主義のもと逸脱行為を許さないかつての日本的経営
■ 「職場は感情で変わる」
長期的関係がベースにあり、集団主義のもと逸脱行為を許さないかつての日本的経営の中では、人は周囲の意図に反した行動をするとはじかれてしまうのではないかと思い、自分の行動を抑制していました。
協力という行為も、ある意味、そうしなければ自分が損をするのだから、自分から協力することが当たり前だと思えたわけです。
それが、短期的関係を前提にした途端、それぞれが自分のために行動を起こし始めた。
だから、相手の行動が予測できない。
今まで常識だと思ってきたことが通じない。
こんな構造に陥っているのが、今の日本企業であり、日本社会です。
この定義から考えれば、周囲が思い通りの行動をするような明確なルールが必要であり、そうした行動をとらなければ損をするという状況をつくり出さなければならないということになります。
自分から周囲に協力しない人は評価を下げ、給与を下げる。
あるいは、周囲に影響を及ぼすような行為をしたら、組織から出て行ってもらう。
確かにこうしたルールは、誤った行為をさせない、組織の中での不確実性を排除する仕掛けとして、機能します。
しかし、ルールに縛られ、その通り行動しなければならないような集団主義的組織に変えて、そこで働く人たちは幸せになれるのでしょうか。
日本人は、ほんとうに集団主義的なのだろうか?
■ 「「集団主義」という錯覚」
「日本人 = 集団主義」説は、日本人論の通説であり、国内では長いあいだ、紛れもない事実だと受けとめられてきた。
外国でも、「集団主義」は「フジヤマ、ゲイシャガール」にかわって、日本を理解するための第一のキーワードになっている。
では、日本人は、ほんとうに集団主義的なのだろうか?
「集団主義」というのは、ひとことで言えば、個人より集団を優先する傾向のことである。
「個人主義」というのは、逆に、集団より個人を優先する傾向のことである。
日本人論では、多くの場合、「集団主義的な日本人」は、「個人というものが確立していない」、「和を尊び、つねに集団として行動する」などと評されてきた。
こうした見方は、日本人だけではなく、欧米人のあいだでも、そして、欧米式の教育を受けた他の地域のひとびとのあいだでも、「日本人」についてのもっとも強固なイメージとして定着している。
金太郎飴は、どこを切っても同じ顔が出て来る。
おなじように、「日本人は、だれを見ても、みな同じような顔をしている」というのである。
「個我が確立していない」ので、「自己主張ができない」し、日本人の人間関係は、たがいに甘えあい、もたれあう関係になる。
また、つねに他人の目を意識して行動するので、「恥ずかしくないかどうか」が行動を律する原理になる。
つねに集団として行動する日本人は、集団の「和」を大切にし、集団のためには個人が犠牲になることもいとわない。
その「和」を乱す異分子は集団から排除しようとする。
自分が属する集団の「ウチ」と「ソト」を峻別し、「ウチ」のひとたちには温かい気遣いを示すが、「ヨソ」のひとたちには邪険にあたる。
集団を統制する原理は、上が下を支配し、下が上を支えるという、「タテ」の関係が主軸となる。
こうしたところが日本人論における「集団主義的な日本人」の典型的なイメージである。
「日本人の集団主義」は、日本の社会で起こったさまざまな出来事を説明するために、頻繁に利用されてきた。
集団主義のせいで個人が独自の考えをもつことができない日本人は、当然、「創造性には縁がない」と見なされることになる。
不祥事隠しなど、なにか事件がおこるたびに、「日本人の集団主義」が引き合いにだされる。
たいがいは、悪いできごとの説明に使われるのだが、たまに、良いできごとの説明に使われる場合もある。
「日本的経営」というのは、集団主義的な経営である。
企業の従業員が結束を固め、一丸となって努力した結果、驚異的な経済成長が可能になったというのである。
もうひとつ、良い事例は、低い犯罪発生率である。
おなじ「先進国」である欧米諸国と比べて、日本で犯罪が少ないのは、「集団主義的な日本の社会では、たがいに監視しあい、干渉しあうので、犯罪が抑制されるからだ」というのである。
日本では、集団は個人に優先するとされてきた
■ 「人を伸ばす力 ― 内発と自律のすすめ」
日本では、伝統的に集団は個人に優先するとされてきた。
それはきわめて強力な社会的価値であり、日本文化の中ではほとんど普遍的といっていいいほど、人々に共有されている。
日本においての統制という手段は、外からの強制にもとづいているというよりは、内在化を促進する、信じられないほどの効果的なプロセスである。
その中で、人々は価値を身につけ、その価値を自分自身に対して厳格に適用しようとするのである。
文化の担い手によって統制されるのではなく、文化における社会的慣習と調和しながら、自分自身を統制していこうとするのである。
それはたしかに、これまでは効果的であったかもしれない。
だが日本という社会がほころびはじめていることを示す証拠も、しだいに増えつつある。
横領や癒着などが告発されていることは、個人主義の感覚が大きくなってきていることを証明しているし、ホームレスなどの社会問題も、増加傾向にある。
独立性と同じように、個人主義も自律性と混同されてきた。
しかし、2つの概念は決定的に異なる。
個人主義とは、われわれ自身の目的を自由に追求することができるということである。
われわれが自分の欲するものを得ようとする試みは、それが合法的であるかぎり、いかなり外的な力によっても妨げられることがないということである。
(個人主義という価値は、最低限、法を遵守することを伴う)
同様に、自律性とは、われわれが自由意志によって、選択した目標を追及すると(すなわち、自由に目標を追求できること)と定義することができる。
しかし2つの概念が焦点を合わせているもの、意味しているものはまったく異なっている。
個人主義とは自己の利益追求のことであり、自分自身のために何かを達成し、あるいは獲得しようとして行動することである。
それには、個人的・情緒的に独立していることが含まれているが、それをはるかに越えて、わがままの感覚、つまり自分自身のことしか気にとめないところまで行き着く。
個人主義は、みんなのために行動することと正反対にある。
個人主義の反対は集産主義である。
ここでは、全体の権利や目標のために、個人の権利や目標は従属させられる。
集産主義社会では、人々は他者に依存しているが、彼らの依存は単なる個人的で情緒的な信頼感によるものではなく、一人ひとりの結果がすべて他者の結果と複雑にからみ合っている。
構造的な相互のつながりである。
個人の前に家庭があり、個人の前に集団があり、個人の前に社会がある。
個人は自分自身のためというよりは、共通の利益のために役立つよう行動することが期待される。
つまり、個人の幸福が共同体の強さをもたらすというよりは、共同体の強さの結果として個人の幸福がもたらされると見なされている。
それにくらべて自律性とは、自己選択の感覚や柔軟さ、自由さを感じながら、意志をもって何らかの行為を行うということである。
それは、自分の興味や価値観と調和して、責任ある行動をしようとする真の意志を感じることである。
自律的であることの逆は、統制されていることである。
何か特定のやり方で行動したり、考えたり、感じたりするように圧力をかけられていることである。
統制という手段は、他者によって(つまり、上の立場に立つ人たちや社会によって)行使されることが多いが、自分が取り入れた規範を満足させるために、自分で自分を統制する場合もある。
自分自身に圧力をかけたり、何らかの行動を自分自身に強制したり、あるいは何かをしなければならないと感じることによって、自律性は低下するのである。
より大きな富と権力とを求めて戦い続けている、野心的で競争的なビジネスマンは、粗野な個人主義ではあるかもしれないが、自律性の見本ではない。
彼らの目標追及が、たとえ個人の内部から発したものであったとしても、それが圧力をかけられ、強要されたものであるかぎり、個人主義的ではあるが自律的ではないのである。
「個人主義」と「利己主義」は、まったくの別物
■ 個人主義って利己主義とちゃうで…
恥ずかしい話なんですけど、ぼく、「個人主義」って「自分のことばっかり考える」っていう意味やと、長~~~いこと思い込んでましてん。
で、ようやくちょっと前に「自分のことばっかり考える」というのは「利己主義」のことで、「個人主義」と「利己主義」はまったくの別物…ということがわかったんです。
そんでも、人間は基本的に「自分のことを考える」のは当然のことなので、「利己主義」とは「自分のことばっかり考える」ことに加えて、「自分さえよかったら他人のことなんかどうでもいい」…という内容を含むものと理解してます。
他方、「個人主義」は「人は個人として尊重される」というもので、
「人というものは組織や団体の一員として尊重されるんじゃない、一人の人間として尊重されるべきもんだ」
…という意味です。
ちなみに、「個人主義」は日本の憲法の大切な原則の一つになってまして、憲法13条には「全て国民は、個人として尊重される」としっかり書かれてあります。
( → これは、国民は日本という国の構成員としてではなく、一人の人間として尊重されるんだ…というコトです)
また「個人主義」は個人の「幸福追求権」の土台になってる考え方でもありまして、同じく憲法13条には、
「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」
と規定されてて、これは、国民は一人の人間として尊重されるべきものであるから、国は市民一人一人の幸福追求権を最大限尊重しなければならない…という当然の帰結を述べたものです。
そもそも、個人が一人の人間として…ではなく、組織や団体の構成員として尊重される…とするのは、戦前の「全体主義」の考え方そのものでありまして、この考え方だと、組織や団体( → それは究極的には国)に価値があるからその構成員にも価値を認める(≒尊重する)
…となるので、組織や団体の利益にならないと判断された構成員は尊重しなくてもよい…ということになってしまいます。
戦前の「非国民」という言葉は、それをわかりやすく表現した言葉です。
立憲主義とおなじく世界の(法)常識となって久しい「個人主義」にイチャモンをつける…ということも、やはり、21世紀の国としてはすっごく恥ずかしい話(…というか、あり得ない話)であるので、今後は、「行き過ぎた個人主義」…なんていうコトを話す人を見かけたら、「コイツ、個人主義と利己主義の区別もついてへんやんけ」…と呆れて下さいませ。
日本人は欧米人より集団主義的だとは言えない
■ 日本人は欧米人より集団主義的だとは言えない
日本人は集団主義という通説は誤り、とする研究結果が話題になっている。
「個性が乏しい」
「同調圧力に影響されやすい」
といった日本人論が客観的な根拠に基づかないことにかねてから疑問を抱いており、心理学、言語学、教育学、経済学それぞれの分野から「日本人は欧米人より集団主義」との言説が否定され得るとの研究結果を明らかにした。
日本人の通説を考える上で言われがちな、かつて集団主義だった日本人が占領でアメリカナイズされて個人主義的になった、との見方も妥当ではないと主張する。
文献調査から、戦前も開国前も、日本人が個人主義的に行動した事例が多く見つかったという。
それでも「日本人は集団主義」が通説になったのは、第二次世界大戦後に米国で出版され、日本を含む海外でも広く読まれた『菊と刀』の影響が大きいとされている。
しかし、日本人の集団行動も脅威にさらされた人間集団がとる普遍的な行動に過ぎないと指摘。人間の行動理由がその人内部にあると解釈してしまう認知の歪み「対応バイアス」の影響で誤解したのではないかと推測する。
当時『菊と刀』を読んだ日本人は自らの大戦での様子を思い起こし、書籍の指摘をもっともだと受け入れてしまった可能性があるという。
「(日本人は)むしろわざわざ『和をもって貴しとなす』といちいち言わん限り得手勝手なことばかりする連中、と解したほうがよい」など、研究結果に納得する人もいる一方で、「日本の有給休暇取得率が低いのは集団主義の現れなのでは?」と、疑問の声も出ていた。
誤った解釈で輸入してしまった「個人主義」
■ 日本式の個人主義とは 困っている人を放置
日本人は「集団主義」の国民性である、という自己認識はどうも誤解のようです。
まず、欧米の職場には日本人が言うところの「個人主義」なんていうものは存在しません。
成功している組織では、先に仕事を終えた人間は自然と同僚を手伝います。
仕事の遅れには必ず原因があります。
仕事の分配量に誤りがあるか想定外のトラブルが発生しているかです。
当事者が解決できない問題であれば、周囲の人間が助けなければと考えるのが、チームワークを重視する欧米人の感覚なのでしょう。
どうも日本人が使う「個人主義」は、困っている人を放置してそれで良しとする「selfish(利己的)」に意味合いが近いように感じられます。
本来、英語で言う「個人主義(individualism)」の意味とは、集団に所属する一員としての役割や権利を相互に尊重しあう立場のことで、「私利」が「他利」に優先されるというワガママを容認してしまっては成り立たない概念です。
特に米国は、多民族の国です。
人種も違う。
宗教も習慣も、思考回路も違う人が職場に集まれば、最初に待っているのは混乱です。
しかし、だからこそ仲間に関心を持ち相互理解を深め、「他利」を「私利」に優先させなければ仕事にはならないのです。
対照的に日本人は互いの常識を「暗黙の了解」で共有できる極めて同質性の高い社会で生きてきた結果、コミュニケーション・コストを軽視してきた経緯があります。
誤った解釈で輸入してしまった「個人主義」という言葉は隣の席で困っている同僚を助けることができないほどに個人を組織の中から孤立させてしまったのではないでしょうか。
グローバル社会を生き残るには「暗黙の了解」ではうかがい知れない様々の常識に耳を傾け、自らを改め続けなければなりません。
日本式の個人主義はそんなとき、いかにも足かせになる概念です。
日本人って案外「個人主義」な気がする
■ 日本人って案外「個人主義」な気がする
よく言われるイメージとして、欧米の人は「個人主義」で、日本人は「集団主義」というものがあります。
例えば、欧米は言いたいことを言いあう「黙ってないで自分の利益を主張し切ったもん勝ち」の世界、日本は「和をもって尊しとなす」ということで周りの空気を読んで「自分の利益を忍んで行動するのが美徳」の世界、などと対照されます。
確かに「空気を読め」という圧力はとても強いこの日本。
私も長らく「欧米の個人主義」vs「日本の集団主義」というイメージを抱いて生きていました。
でも、最近ボーっと考えていて思ったんです。
案外日本人って「個人主義」かもって。
ブラック企業やら何やらと、慢性的に残業する風習で有名な日本人ですが、これってよくよく考えてみると、個人主義的行動だと思うんです。
日本人は「延長」が好きです。
「自分がやらないと誰も解決できない」
「自分がやらないと周りが困る」
見方によっては確かに仲間思いの考え方にも見えなくはありません。
でも、これって ―― 単にチームワークがなってないだけなのでは?
日本人は「和」とか「絆」とか言っておきながら、結局支えあったり助けあう気がないんじゃないのかなーって、ちょっと思ってしまった。
「延長の理由」は要するに「自分でやる」「自分でやる」って繰り返し。
それって、一人一人がただ「自分の仕事だけ」をしている ―― 自分のことだけ考えてる ―― という事実の裏返しじゃないでしょうか?
スムーズに「交代」できるように、なぜ普段から情報を共有しないのでしょう。
気兼ねなく「交代」できるように、なぜ普段から引き継ぎの風土を作らないのでしょう。
誰かが急に休むことになっても業務に支障が無いように、なぜなってないのでしょう。
それぞれがそれぞれの仕事を抱え込むのが「和」なんでしょうか?
互いに互いの仕事を助けあうのが「和」ではないでしょうか?
「チーム」ってのは、「和」ってのは、やっぱり「手を繋ぐこと」なんじゃないでしょうか。
他の人に迷惑がかかるからとか、自分にしかできない仕事だからとか・・・要は協力する気が無い、交代したくないだけなんじゃないでしょうか。
下手すると、情報を共有しないことで自分が「代わりの居ない、会社にとってかけがえの無い人材」として重要な位置を占めることを狙ってそうなきらいもあります。
それってとっても「個人主義的」に私には思えます。
「人に迷惑をかけないよう自分でやる」
一見すると「集団」を尊重している「集団主義」のように聞こえます。
でもそれは裏を返せば「助け合わない社会」「それぞれがそれぞれのことを解決しないといけない社会」であって、その意味ではとても「個人主義」になりえます。
個人主義は孤立主義ではない
■ 実は全く違う“幸せな個人主義”と“不幸せな孤立主義”
個人主義の文化では、「個人個人は異なっている」という考え方を前提としている。
その上で協力し合える関係をつくることが重要だという価値観を持っている。
かつての日本企業は、その組織力の強さが世界の注目を集めていた。
欧米の研究者には、組織力は1人1人の自発的な協力と組織への忠誠からつくられているように見えた。
だが実際には、もっと「しがらみ」だらけの窮屈な社会であったことは、日本人である私たち自身が知っている。
私たちは、そのようなしがらみでがんじがらめになった会社組織に嫌気がさしていた。
現在の「集団嫌い、組織嫌い」の日本人は「孤立主義」だ。
他者と関わること自体が面倒だと思い、協力するつもりにもならない。
集団のしがらみから自由になることだけが目標で、孤独になることのリスクをあまり考えないやり方である。
個人主義は孤立主義ではない。
欧米は、日本人だったら参ってしまうほどの集団主義でもある
■ 日本人の「個人主義」
日本人はかなりの個人主義の民族だと思う。
例えば駅前の放置自転車がひどい国って日本以外は知らない。
よく欧米は個人主義の国だと言われるけど、実際には日本人だったら参ってしまうほどの集団主義でもある。
やれボランティアをしろだとか、ノブレス・オブリージュだとか、社会が個人に対してあれこれ干渉してくる。
日本の個人主義は欧米の個人主義とは性質が違うものではあるものの、日本人は世界でも稀に見る個人主義の強い国だと思う。
悪い言い方をすると他人に冷たく、自己中心的である。
人助けランキング、日本は世界最下位
■ 「人助けランキング、日本は世界最下位」 日本は冷たい国なのか
日本の結果は惨憺たるものだ。総合順位は126カ国中107位と先進国の中では最下位だ。
注目すべきは、調査した3つの観点の中でも、「見知らぬ人、あるいは、助けを必要としている見知らぬ人を助けたか」という観点で、日本は125位と世界最下位であることだ。
とても悲しい。
それが、ホームレスが避難所に入ることを拒否されたという日本のニュースを目にした時に感じた思いだ。
そして、そんなニュースに寄せられたコメントを見て、もっと悲しくなった。
ホームレスは“受け入れ拒否されて当然”と考えているようなコメントが散見されたからだ。
“助けを必要としているホームレスを受け入れなかった行政“、そして、“行政が受け入れなかったことに賛同している人々が少なからずいること”は、調査の結果を裏づけているかのようだ。
日本が人助けをする国として評価される日が来ることを願う。
「集団主義」が行き過ぎると、戦前・戦中のようになる
■ もし「半沢直樹」がアメリカで放映されたら
アメリカはもともと「個人主義(Individualism)」の国である。
新大陸を開拓していくには個人が自分でリスクを取り、自分の人生を切り開いていく以外に道はなかった。
会社と従業員の関係は対等な契約であると見る。
その企業が気に入らなければ、とっとと辞めていく。
自分を生かしてくれる企業に転職し、そこで新たな人生を切り開こうとする。
米国では個人の幸福の追求が、集団での成功より上位の価値観に置かれる。
日本には「集団主義」の長い伝統があった。
組織に忠誠を誓い、波風を立てずに秩序だって行動することを求められた。
それが行き過ぎると戦前・戦中のように「組織のために命を捨てる」ところまで行く。
戦後、民主主義国家になって大きく変わったが、我々の意識の中には古い価値観の片鱗が残っている。
また、家族の犠牲も大きい。
日本の今の「閉塞感」はこうした諸要因が重なって起きているように思う。
会社というクローズドなシステムでは社員に逃げ場がない。
柔軟性を取り入れ、個人に選択の幅を認めるシステムに転換する必要があるように思う。
個人主義に基づくコミュニティと、日本のコミュニティの違い
■ “コミュニティ”は日本に根付く?
「コミュニティ」は、西洋的個人主義に基づくものだ。
確固たる自分の意見を持った独立した個人が、自ら望んで集まり、集団にコミットし、コミュニケーションを持ち、アイデアと創造性を発展させていく。
これが西洋的自己観に基づいたコミュニティだ。
しかし、日本をはじめとした東アジアの「コミュニティ」はそれとは様相が異なる。
人々は個々の意志で集まるというより、あまり選択肢のない中で、極端に言えば「仕方なく」集まった人々が、「ま、ここでやっていくしかないよな」という諦めのもと、集団規範に組み込まれて成り立っているのが東洋型コミュニティだ。
そこでは、個人のユニークな考えではなく、集団の持つ空気を読むことがより重要で、どのように集団に順応していくかがカギとなる。
個人が自発的に集まるコミュニティと、集団がその規範の中に個人を巻き込んでしまうコミュニティでは、そのメンバーのメンタリティや行動規範は自ずと違ってくる。
前者では、個人は自分が集団にいかに貢献できるかを考えるのに対し、後者では、個人は自分がいかに集団から利益を得られるかが重要になる。
だから、ますます強い集団規範が必要となる。
それが立ち行かなくなったのが、バブル崩壊後の日本組織だ。
そしてその直接的な理由は、年功序列、終身雇用といった「長期的関係」の組織をつくり上げる制度がなくなったことである。
先の集団規範も、メンバーが「他にいくところがないし、我慢していれば将来的には報われるので、今は集団に順応するしかない」という状態に置かれて、初めて機能するものだ。
しかし、これらの制度の崩壊によりその状態はなくなった。
後に残ったのは、日本型コミュニティの崩壊と「不機嫌な職場」だった。
見過ごしているのは、かつての日本の会社組織がコミュニティとして発展してきた理由は、そのような制度に支えられた集団規範(しがらみ)であったことだ。
日本的集団主義という旧来の経営システム
■ 今なお日本社会に巣くう「同期」という病魔
「同期」あるいは「同期意識」の思想は、日本社会固有の共同体的集団主義を基盤とした「派閥意識」といってもよいだろう。
同期意識は日本企業の経済復興期、高度経済成長期には、日本的集団主義の中核的な要素として大きな役割を果たしてきた。
しかしそれは、自分が出世コースからはずれても、同期のトップグループが出世すれば救済してくれるという意識を醸成することになり、企業内に派閥を形成する元凶になるばかりか、会社全体の社員のモラール(勤労意欲)をもそぐことになる。
欧米の企業の人材採用は新卒一括採用方式ではなく、ポストに空きができた場合に、必要な人材を採用するという能力主義だ。
新卒の大学生といえども、その職務に適合した実力がないと採用されることはない。
この背景には、欧米の企業は日本のように、企業を経営者と社員の運命共同体として捉えていないことがある。
トーナメント方式で実力のある者が勝ち上がっていくシステムなのである。
さらに、欧米の企業で成功した事例をみると、ハイブリッドな価値観(異文化的な価値観)を持った多様な人材を、能力主義という形での「競争原理」で抜擢している。
「同期」という組織上の横並び意識や日本的集団主義という旧来の経営システムを捨て去らなければ、日本の企業はグローバルな企業間競争からますます淘汰されていくことになるだろう。
アメリカ人は個性的だが利己主義?日本人は集団主義で自己表現が苦手?
■ 「(日本人)」
アメリカ人は個性的だが利己主義で、日本人は集団主義で自己表現が苦手だとされる。
日本人は、曖昧な状況に置かれると、無意識のうちにリスク回避的な選択を行う。
だが状況が明確であれば(自由に何でもやっていいのだとわかれば)、アメリカ人と同様に自己主張をする。
アメリカ人は逆に、曖昧な状況では自己主張をすることがもっとも有利な選択だと考える。
だが過度な自己主張がひんしゅくを買うような場面では、ちゃんとその場の空気を読んで自分を抑えることもできる。
アメリカ社会では、自己主張しない人間は存在しないのと同じだと見なされる。
このような環境では、迷ったら自己主張をする、というのが生存のための最適な戦略になる。
それに対して日本では、下手に目立つとロクなことがない、と考えられている。
このような社会では、迷ったら他人と同じことをしておく、というのが最適な戦略になるだろう。
全体主義的な教育
■ 「生きる力をつける ドイツ流子育てのすすめ」
自立のための勉強をさせるドイツでは、「勉強を教えるのは学校」「子どもの人間形成や礼儀などを教えるのは親」と、役割がかなりはっきりと分かれている。
親は勉強のことはすべて学校に任せ、学校は子どもがプライベートな行動面で問題を起こしても、いっさい責任をとらない。
ドイツ人は学校が子どもの人間形成を助ける役割をもつことはできないと考えている。
人間形成はあくまでも親と子どもを囲む社会の責任になるのだ。
ドイツにはいろいろな国の人がいて、文化や宗教もさまざまだ。
イスラム教徒で豚肉の食べられない子どもがいれば、ベジタリアンの子もいる。
アレルギーの子、宗教上の理由で頭にスカーフを巻かなければならない子など・・・
世の中にはいろいろな考え方があり、生き方がある。
それをまとめる役として学校は適していないのだ。
これを無理やりまとめようとすると、第二次世界大戦前のように、スパルタ式や全体主義的な教育をしなければいけなくなるかもしれない。
それをドイツ人はよしとしないのだ。
ドイツ人の親は、3、4歳の子どもに対してでも、しかるときは、
「なぜ、どういうふうに、なにが、いけないのか」
と説明する。
だから、日本人から見ると、「何も4歳の子に理由を説明しなくても」と不思議に思えるかもしれない。
ドイツの親は厳しいが、自分の子どもをしかるとき、こんな言い方はしない。
「隣の○○ちゃんはできるのに、あなたはなんでできないの?」
だからドイツの子どもは親の言いつけは守らなければならないが、ほかの子と比べられてプレッシャーを感じることはなく、のびのびと育つ。
ドイツ人は個人主義であるが、根本的に人と人を比べたりしないのは、小さいときからそういう環境にあるせいかもしれない。
厳しさの中でも、やはり、問題を親子で話し合い、子どもの意見も聞くという親子の信頼関係を大事にしている家庭がほとんどだ。
私は日本に来て、睡眠に関する考えの違いに驚いたものだ。
それは、「3日間続けて徹夜した」と当たり前のように言っている日本人に会ったからだ。
日本人は「睡眠なんてとらなくても、気合いで乗り越えれば大丈夫」と考えている人が多い気がする。
とくに睡眠をとれない理由が仕事だとすると、その考えはさらに強まる。
ドイツでは「徹夜した」と言うと、必ず、「どこのクラブで踊っていたんだ?」ということになる。
仕事で徹夜するという考え方がないから、そう言おうものなら、だらしない生活をしている人だと思われ、まちがっても偉いとか大変だとかは言われないのだ。
どんなに忙しい人でも、自分の部下に睡眠時間を削ってまで仕事をしろとは言わない。
人間は睡眠時間が減って疲れてくると仕事上のミスを犯しやすくなると思っているのだ。
日本のタクシーに乗って運転手さんの話を聞いたときは、いきなり車を降りたくなった。
時間シフト制で仕事をしていて、21時間続けて運転しているという。
21時間の勤務のあとは何日か休めるということだが、なぜ、毎日8時間労働にしないのだろうか。
徹夜明けで20何時間目の運転手さんの運転するタクシーで、高速を走ることを想像すると、怖くて体が震えてくる。
タクシーだけでなく、徹夜明けの医者、看護師、パイロットも怖い。
人の命を預かっている仕事は、絶対に徹夜禁止にすべきだ。
居眠りといえば、日本に来て驚いたのは、電車で眠っている人が多いことだ。
ドイツでは電車に乗りながら寝る人はまずいない。
みんな家で十分に寝ているからだ。
それと、治安の面でも、万が一スリなどがいたら危険だということで、人前では寝ないのだ。
そこも日本人とは大きく違うところだろう。
ドイツはヨーロッパの中でも個人主義が特に強い
■ 「びっくり先進国ドイツ」
ドイツの個人主義は、この社会が日本ともっとも大きく異なる点である。
しかも、この国はヨーロッパの中でも、個人主義が特に強いと考えられている。
日本はチームワークとか他人への思いやり、気配り、調和が重視される社会だが、ドイツはその正反対である。
個人の意思がもっとも尊重され、他の人がどう思っても、自分の意見や気持ちを正直に言うことが、正しいと見なされる。
理屈さえ通っていれば、他人と違う行動を取ったり、大勢に逆らうような発言をしたりすることは、日本ほど問題視されない。
会社でも、自分の任務さえきちんとこなしていれば、「上司や他の人がまだ働いているから、自分も残業しよう」などという配慮は全く必要ない。
ドイツの商店ではサービス精神は少ないし、いやいや仕事をやっているせいか、笑顔も見せないぶっきらぼうな店員も多い。
日本社会にはない良い面もある。
たとえばドイツでは、お年寄りや女性が大きなトランクを抱えて駅の階段を登っていると、通りすがりの人が運んであげたり、女性が乳母車を市電に載せるのを手伝ってあげたりするのを、よく見かける。
道で物乞いをしているホームレスに、お金をあげる人も目立つ。
たとえ知らない人でも、困っている人を助ける精神は、日本よりも強いような気がする。
ドイツ人の個人主義を観察するには、会社の様子を見るのがもっとも手っ取り早い。
日本の企業では、チーム精神やグループ全体の利益が何よりも重視されるが、ドイツでは会社でも、個人の利益を守ろうとする傾向が強い。
たとえば日本企業では、上司や他の同僚が忙しそうに働いている時に、さっさと退社することは、よく思われないが、ドイツでは職場を出た後の個人の時間を誰もが尊重しているので、あまり白い目で見られない。
特に管理職とヒラ社員の給料の差が、日本よりもはるかに大きいので、上司は平社員よりも長時間働いて当然と思われているのだ。
また、ドイツでは労働基準法が日本よりも厳密に守られている。
たとえば、基本的に管理職以外の社員は、1日10時間以上働いてはならない。
また原則として夜8時以降の労働、日曜日や祝日の労働も禁止されている。
ドイツでは、労働基準監督署が抜き打ちで労働時間の検査を行うことがある。
この検査によって、企業が組織的に社員を毎日10時間以上働かせていたり、週末労働をさせたりしていることがわかると、多額の罰金を科されたり、人事部長が逮捕されたりする恐れがある。
このため、どの企業でも社員の労働時間には神経を使っている。
もともと、企業に対する忠誠心は日本ほど重視されないので、夜遅くまで残業をするだけでは、あまり評価されない。
みな労働時間を短くしようとするので、ドイツ人の仕事への集中度は高い。
会社ではあまり無駄話をせず、わき目もふらずに仕事をする。
いわゆるフレックス・タイム制度を採用している企業も多く、午前9時から午後3時までは会社にいなくてはならないが、所定の労働時間(週37.4時間)をこなしていれば、いつ退社しても良いことになっている。
ドイツ人は朝早くから働き始める人が多く、朝7時からオフィスで働き始めて、午後3時には家に帰るという人もいる。
ドイツでは公私混同を嫌い、会社と個人の時間をきっちりと区別する人が多い。
仕事が終わってから上司や同僚と飲みに行くことは、1年に1回あるかないか。
年間30日の有給休暇にしても、ドイツの制度の根底にあるのは、
「個人の生活を楽しむ権利を与えた方が、社員もリフレッシュされて、会社のために働く意欲が増す」
という発想である。
企業や役所に勤める人には、法律や労働協約で30日間の有給休暇が保証されている。
会社員や公務員は、ふつう週末には働かないので、丸々6週間の休みである。
残業時間を消化するための代休や、前の年に消化し切れなかった休暇まで考慮に入れると、1年の有給休暇が50日、つまり10週間近くになることも珍しくない。
2週間の休暇を年に2回くらい取るのは当たり前である。
ドイツでは上司も含めて全員が交代で休むので、気兼ねもなく、長期休暇は当たり前になっている。
6週間は、働かなくても自動的に給料が出るのだから、休まないのは損なのである。
しかも、上司の顔色をうかがいながら休暇を申請する人は誰もいない。
30日間の休暇は、すべて取るのが当然の権利と見られており、みな堂々と休みを取る。
休暇申請書に休む日を記入して、上司のサインをもらうだけである。
いや、むしろ従業員が30日間の休暇を全て消化しないと、管理職は事務所委員会(組合に似た労働組織)から「なぜ社員を休ませないのか」とにらまれる恐れがあるので、むしろ上司は社員がきちんと休暇を取るように奨励する。
休みを取らないで働いても、「やる気がある」とか「忠誠心がある」と思ってくれる上司はいないので、意味がないのだ。
管理職にとっては、社員がノイローゼになったり、転職したりすることを防ぐためにも、長い休暇によって気分転換をさせ、新しい気持ちで仕事にのぞんでもらうのは、重要なことなのである。
ヨーロッパの様々な国民の中でも、ドイツ人の個人主義は、特に強い。
他人と折り合いをつけるとか、他人の感情に配慮して妥協するのが、苦手な人が多い。
そういう人にとっては、職場で好きでもない人々と顔を突き合わせなくてはならないことは、ほとんど耐え難いことだが、金を稼ぐためには我慢せざるを得ない。
したがって6週間の休暇は、多くのドイツ人にとって、自己を取り戻すための貴重な時間なのである。
あるドイツ人がこんなことを言った。
「あなたたち日本人は働くために生きているように見えますが、我々ドイツ人は休暇を楽しむために働いているのです」
「アメリカは個人主義、日本は組織力」というのは、むしろ反対
■ 「採用基準」
日本人はよく「アメリカは個人主義、日本は組織力」などと言いますが、むしろこれは反対です。
日本では、高校、大学、大学院の進学は、ほぼ100%個人の成果によって決まりますが、アメリカの学校の大半は、入学時に提出させる資料において、過去のチームの体験、チームで出した成果、そのチームの中で自分が果たした役割や発揮したリーダーシップについて、詳細に問うてきます。
働き始めてからの人事評価も同じです。
日本では、管理職以外は個人の成果に基づいてしか評価を受けていないのではないでしょうか。
グループの成果を問われるのは管理職だけです。
現実の社会を考えた時、集団や組織を動かさずに成果を上げられることはほとんどありません。
ところが日本では教育現場においてさえ、そういった経験を求められません。
これでは社会に出た後も、組織を動かすなんて不可能です。
そもそも「みんなでやるより、自分一人で集中して取り組んだほうが高い成果が出る」と考えているような人に、ついていきたい人はいないでしょう。
「自分一人ではなく、みんなの力を結集したからこそ、この成果を出せた」と考えるリーダーがまとめ上げた解を、人は他人事ではなく「自分がつくった仕組みだ」と感じます。
そうやって初めて、実際の世の中で動く仕組みができあがるのです。
自分たちだけで問題を解決することは、日本では「他人に迷惑をかけない、責任感をもった立派な対応」と見なされます。
しかしこういった態度は、関係者の力を結集してチームで解決するのが当然と考える欧米からは、「何かを隠しているのではないか」と見えてしまいます。
個人主義のもと「雇用契約に則って動くべきである」という心構え
■ 「「すみません」の国 」
欧米に限らず、海外勤務をした人たちがよく言うのは、日本と違って個人主義が徹底している国では、自分のノルマとして決められた仕事はするけれど、それ以上のことはしてくれないから戸惑うということだ。
日本であれば、自分の仕事が終わって手が空いているときに、「ちょっとこの仕事を手伝ってくれないか」と上司から言われれば手伝うだろう。
そうした日本での常識は、どうも多くの国では通用しないらしい。
組織よりも個人を拠り所とする場合は、自分のノルマ以外の仕事を手伝うには相当の理由が必要になる。
多くの場合、手伝うことで本人にとってどんなメリットがあるかが説明され、納得すれば動くようだ。
個人主義の文化的伝統のもと、「雇用契約に則って動くべきである」という心の構えをもっていれば、何の抵抗もないのだろう。
考えてみれば、日本では仕事の境界も曖昧で、どこまでが自分の仕事で、どこからが他の人の仕事かということが明確に区別しがたく、曖昧領域というようなものがあるように思われる。
それでもトラブルが生じない文化だということなのだろう。
そのいい加減さが、利他的行動をとりやすくする要因ともなっているのだ。
集団主義すら作用しなくなりつつある日本企業が抱える余裕のなさ
■ 「どうやって社員が会社を変えたのか」
そもそもチームというのは、人間集団が特定の目的を共有したときにはじめて成立するものである。
したがって、油断していると簡単に、チームは単なるただの集団に戻ってしまう。
そうなりかねない諸要因に常に取り囲まれているものなのだ。
メンバーそれぞれが、チームの一員として目指すものに向かって組織的に行動するとか、お互いの間に「判断基準または行動の原則」を共有していることで全体の働きにまとまりが出てくる、というチームメンバーが共有するある種のルールなのだ。
日本のチームワーク力が欧米に比べて落ちてきている、と言われるようになって久しい。
「チームを教育するアメリカ、個人主義化が進む日本」とも言っているのだが、おそらく多くの日本人は逆の印象をもっているのではないか、と思う。
つまり、アメリカは個人主義で、チームワークは日本の専売特許、というものである。
確かに、高度成長真っ盛りの時代は集団主義的な日本の特性が強く現れた時代であった。
集団主義とチームワークは同じではないが、「お互いに協力し合いながら事を進める」という点では、結果として似たような作用をする部分があるのも事実だ。
ただ、高度成長時代には当たり前であった「社員の会社に対するロイヤリティ(忠誠心)」は、今やあらかた消えてしまっている。
集団主義すら次第に作用しなくなりつつあるのだ。
このことはつまり、「社員相互の判断基準や行動の原則がバラバラだし、目指すものも共有していないから、集団として存在はしていてもチームとして機能しなくなってきている」ことを意味している。
世の中には単なる仲良しグループを見て、そういうのをチームだと思ったり、チームワークが良いなどと考えたりしている向きが多いものだが、チームワークというのは、そもそも「仲が良いから成立する」ものではまったくないのだ。
日本社会によく見られる「お互いに気を遣い合い、合わせ合っているご近所さんとの関係」でもない。
つまり、チームとグループはまったく異なる概念だということなのだ。
他の先進国やアジア諸国に比べても、相変わらずお互いに気を遣い合い、はっきりと言うべきことを言わない、という日本の傾向には根強いものがある。
気を遣い合うことで、確かに職場の雰囲気はぎすぎすしなくなるかもしれないが、他方、意味のない残業が増えたり、合わせ合ってしまうことで問題が見えなくなり、かえってコミュニケーションが阻害されたりすることも多い。
確かなことは、気を遣い合うこととチームワークの良さとは似て非なるものである、ということだ。
経営と社員の信頼関係が弱まり、意思疎通も不十分になってきていることが、まさにチームワークの悪さそのものの表れなのだが、裏腹の関係で生じてくるのが、官僚主義や、セクショナリズム、事なかれ主義、縦割り組織などである。
社員は目の前にある仕事をこなし、細分化された仕事をたださばくことに集中するのが普通になってしまう。
こんな状況だと、当たり前だが、企業全体が高コスト体質になり、組織の活力は著しく減退する。
日本企業の抱える生産性、利益率とも、他の先進諸国と比べて著しく低いという重大な事実は、その結果として生じているのだ。
といっても、日本人が勤勉さをなくしたというわけではない。
社員の多くは今もなお長時間労働、過労死が問題になるほど懸命に働いているからだ。
それに、生産性が低いといっても、技術力が他の先進諸国と比べて特に低いわけではないのだ。
にもかかわらず、日本企業全体として見ると、低い利益率しか上げられていないという事実のもつ意味は非常に大きい。
そして、この先進国としては最も低い利益率が、社会全体として見れば、人が人として豊かに暮らしていくだけの余裕を奪ってしまっているのである。
この日本企業の抱える余裕のなさが、結果として見れば、長時間労働など社会的弱者にしわ寄せをもたらし、自殺率を高め、日本社会の将来に大きな不安要素を持ち込んでいるのだ。
なぜ、これだけ分社化やアウトソーシングをはじめとする合理化に励み、コスト低減をやり続け、さらには長時間働き続けているにもかかわらず、利益が出にくいのだろうか。
それは、チームワークが働かず、総合力が発揮されにくい環境がいつの間にかできてしまっているからだ。
日本企業のチームワークを悪くしている最大の要因は、社員間の信頼関係もさることながら、経営と社員との間の信頼関係がきわめて希薄になってきていることである。
社員のロイヤリティは、いつの間にか先進国では最も低くなってしまっているのだ。
右肩上がりの時代、頑張ればとりあえず利益がついてきた時代には、会社に対して忠誠を誓ってさえいれば、終身雇用も、そして老後もそれなりに保障された。
年々増大する売上と利益の分け前にあずかることができたからである。
こういう時代であれば、経営と社員の間に横たわる少々の不満も右肩上がりの空気の中でかき消されていく。
経営と社員との間にはまがりなりにも一定の信頼関係が成立しえたのだ。
右肩上がりの時代は、一方的な指示や命令で事を進めても、何とかつじつまを合わせられた時代であった。
ひとつには、指示の中身自体も今ほど複雑ではなかったということと、社員のロイヤリティさえ高ければ少々の押し付けでもそれなりに受け入れられたからである。
つまり、上司が鬼になってやらせることが、それなりの成果に結びつく時代だったのだ。
一方的な指示や命令も、経営と社員の間に一定のロイヤリティが存在し、指示に対しても、それなりに耳を傾ける姿勢を社員がもっているところでは伝わったということだ。
ところが今日では、情報の発信側と受け取る側に基本的な信頼関係が成立していなければ、どんなに大事な方針も発信側の意図どおりに伝わらない、というケースが当たり前になってきている。
経営と社員の信頼関係も、そしてまたチームのありようも決定的な変わり、経営の舵取りが一筋縄ではいかない、厳しい時代になっているのだ。
日本の一番大きな問題はチームワークのなさ、とりわけ、経営と社員のチームワークがいまやかなり多くの企業で危機的状況を呈しているところにある。
しかし、この病理現象も、経営が社員と社員のもつ可能性をどこまで信頼できるか次第で解決可能である。
個人主義、集団主義、全体主義の違いと組織力などとの関係って何だろう?(パート4)
うーむ・・・
どっ・・・、どーでしょう???
「そっ・・・、そーだったのかー! ガ━━(= ̄□ ̄=)━━ン!! 」
「だからかー!!だからだったのかー!! ヾ(.;.;゜Д゜)ノ 」
という方も、いらっしゃれば・・・
「ナルホド・・・、ちょっぴりわかった気がするかも・・・ ヽ(´ー`)ノ 」
「あ、なーんだー、そーだったんだ~ (〃▽〃) 」
という方も、いらっしゃれば・・・
「わかったよーなわからんよーな・・・ ( ̄д ̄;) 」
「やっぱ、頭がウニ状態じゃー!よくわからーん! \(  ̄曲 ̄)/ 」
という方も、いらっしゃるんじゃーないでしょうか?
他にも、例えば・・・


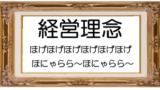












などなども含めると、いろんな意味で考えさせられちゃいません? (^^)
ふーむ・・・、こーやって考えてみると・・・
まだ見えていないだけで・・・
意外なところにヒントがいっぱい溢れている
おお~っ ━━━━ヽ(゜Д゜)ノ━━━━ 見っけ~♪
のかも~???
なーんて、感じません?
(〃▽〃)
どっ・・・、どうでしょう???
皆さまは、どう思われますか?





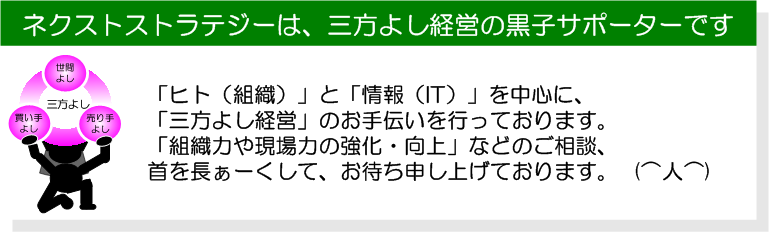
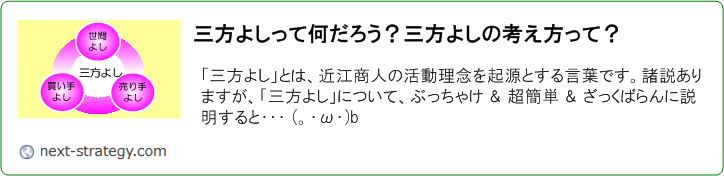


コメント