「リスクって何だろ~? (;゜д゜) 」
「リスクマネジメントって何だろ~?どんな時に必要なんだろ~? ( ̄ー ̄?) 」
「ウチの会社には、どんなリスクがあるんだろ~?やっぱ自然災害とかかな~?他には、下請けいじめとか、資金繰り難とか倒産とかもかな~?リスクに対処するには何からどーやって考えたらいいんだろ~? (;・∀・)」
「リスクマネジメントって何からどーやってやったらいいんだろ~?いくらぐらいかかるものなのなんだろ~?リスクに備えておく必要があるのはわかっているけど、経営環境の変化も激しいし、いつ何時何が起こるかわからないから、リスクヘッジはやっぱ必要だとも思うんだけど、中小零細企業だからそんなコストをかけられないし・・・ (|||▽ ) 」
「リスクマネジメントって、やらなきゃいけないもんなの?地震とか津波とか火事とかの災害なんて滅多におきないのに? ヽ(´∞`)ノ 」
「リスクを恐れていたら、なーんにもできなくなっちゃうよねぇ~、どーせ経営にリスクは付きものだもんねぇ~、リスクをとらなきゃ会社経営なんてできないもんねぇ~、まっ、なるようになるさぁ~ ( ̄▽+ ̄*) 」
などなど・・・
「下請けからの脱却(脱下請け)」、「組織人事戦略(戦略的な組織づくり)」、「組織力の強化や向上」、「経営に役立つ情報活用(IT活用・ICT活用)」などのお手伝いを行なっているからなのか・・・
「爆発・炎上・崩壊組織」で消防のお手伝いを行なうこともあるからなのか・・・
リスク等に関するこのような声をお聞きする機会もあるんですが・・・
( ´・ω・`)
コレって、もしかしたら・・・








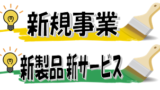

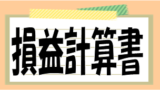








などなどにも、ある意味関係するっちゃーする面もあるのかも~???
なーんて感じるコトもあるので・・・
そもそもの話、リスクって、何だろーか?
組織には、どんなリスクがあるんだろーか?
経営を行う上で、どんなリスクがあるんだろーか?
リスクマネジメントって、何だろーか?
リスクヘッジって、何だろーか?
どんなリスクに、対応すればいいんだろーか?
どんなリスクには、対応しなくていいんだろーか?
それは、誰がどんな基準でどう判断するんだろーか?
リスクを取るって、どーゆーことなんだろーか?
リスクを取らないって、どーゆーことなんだろーか?
リスクを取るか取らないかの判断基準って何なんだろーか?
リスクやらリスクヘッジやらリスクマネジメントやらに関係するのって、誰なんだろーか?
経営者や管理職だけに関係することなんだろーか?
一般従業員には関係ないことなんだろーか?関係するんだろーか?
取引先には関係ないことなんだろーか?関係するんだろーか?
何のためにリスクを取ったり、リスクに対応したりするんだろーか?
誰のためにリスクを取ったり、リスクに対応したりするんだろーか?
などなども含めて、一緒に考えてみません? (^^)
あ、モチロン、「自律的に」という意味で。
ちょっと興味あるかも~?
って言ってくださる方は、お付き合いいただけると嬉しいです。
(^^)/
リスクとは?リスクマネジメントとは?何のため?(パート1)
んーと・・・
リスクに関する誤解や勘違い、思い込みなど意外とある
のかも~???
( ・ _ ・ )
なーんて感じるコトもあるので、例えばこんなのからまずは考えてみるのはどーでしょう?
(。・ω・)b
リスクとは?
○ はてなキーワード
資産やインフラ、プライバシーなど、価値を有するモノの一部または全部を失い、結果として損失を出す可能性。
ただし、資産運用の用語として使用される場合には、単に「確定していないこと」やその度合いを意味する。
特に損失を被る可能性に限定する場合には、「ダウンサイドリスク」等と言う。
数学においても、不確実性(uncertainty)とリスク(risk)は同義であるが、不確実性(もしくは不確定性)という用語が一般的である。
○ ウィキペディア
リスクは、「将来のいずれかの時において何か悪い事象が起こる可能性」とされている。
この概念をベースとして、金融学や工学、あるいはリスクマネジメントの理論の中で派生的にバリエーションのある定義づけがなされている場合がある。
日本語では「危険」などと訳されることもあるが、「危険」では「可能性」という概念が十分に表されていない。
辞典の定義のとおり、リスクは「悪い事象」ではなく「悪い事象が起こる可能性」であるから、悪い事象の「重大性」と「可能性」のマトリックスによって「リスク」の大小が決定づけられることとなる。
語源であるラテン語の「risicare」は「(悪い事象が起こる可能性を覚悟の上で)勇気をもって試みる」ことを意味する。
経済学上のリスク
経済学においては一般的に、リスクは「ある事象の変動に関する不確実性」を指し、リスク判断に結果は組み込まれない。
例えば、ビルの屋上の端に立つのは危険であるが、まだ転落するか無事であるかは分からない。この状態はかなり不確実でリスクが高い。
しかし、一旦転落すれば十中八九命がないとすれば、転落直後にリスクが低下することになる。
企業経営上のリスク
企業経営上のリスク対応は、主に経営資源とブランドを確保することが求められる。
すなわち資金・人・物・時間というリソースと、会社としての信用である。
システム上のリスク
システムにおけるリスクは、損失の可能性があるものだけがリスクとみなされる。
その意味では不確実性ではなく、確実な危険性といえる。
この対策として、平常時からバックアップとして配置し運用する場合が多く、これを冗長化と呼ぶ。
経営リスクとは?
○ コトバンク
経営全般にかかる事業体制の不備や外的要因による間接的影響から生じる、「経営損失の危険性」。
企業の事業活動だけではなく、個人事業主、SOHO、さらには第三セクター、官庁などの事業活動も含まれる。
商品の生産、販売、流通、アフターサービスなど、事業活動を行なっている全過程において発生する。
また企業内部で発生しうる経営リスクとしては、法務リスク、財務リスク、人事リスクなどもこれに含まれる。
リスクヘッジとは?
○ 金融・経済用語辞典
リスクヘッジ(Risk Hedge)とは、様々な起こりうるリスクを回避したり、その大きさを軽減するように工夫することを指す。
ちなみに「ヘッジ」というだけでも同じ意味を指す。
具体的にはヘッジ取引により将来のリスク低減、分散投資によるリスクの低減などが代表的。
リスクマネジメントとも呼ばれる。
なお、金融取引だけでなく、ビジネスの一般用語として用いられる。
例えば将来の勤め先の業績悪化による解雇というリスクに対して、そのリスクをヘッジするために資格を取得して自身の価値を向上させることもリスクヘッジの一つである。
リスクとは「不確実性」という意味であり、将来どうなるか分からないということに対して、特にマイナスの意味をもつ事態・事由に対してそのリスク低減のための行動がリスクヘッジとなる。
リスクマネジメントとは?
○ ウィキペディア
リスクマネジメントとは、リスクを組織的にマネジメントし、ハザード(危害(harm)の発生源・発生原因)、損失などを回避もしくは、それらの低減をはかるプロセスをいう。
各種の危険による不測の損害を最小の費用で効果的に処理するための経営管理手法である。
リスクマネジメントとは、リスクを把握・特定することから始まり、把握・特定したリスクを発生頻度(発生確率、possibility)と影響度(酷さ、severity)の観点から評価した後、発生頻度と影響度の積を評価の尺度とした、リスクの種類に応じて対策を講じる、また、仮にリスクが実際に発生した際には、リスクによる被害を最小限に抑えるという一連のプロセスをいう。
どの会社においても、意思決定を行う際は、当然、暗黙の了解で、そういったことをこれまで行ってきたものと思われるが、近年、リスクマネジメントに対する意識の高まりを受け、特に、明示的に行われるケースが増えている。
○ Weblio辞書
リスクを管理するプロセス、体制、組織文化などを含む経営管理の要素。
「リスクマネジメント」とはプロジェクトにおける様々なリスク管理のことを指す。
プロジェクトで起こりうるリスクを出来る限り排除、低減することにより、損失をできるだけ回避し、プロジェクトを遂行することを目的とする。
「リスクマネジメント」のプロセスとして、リスク要因を特定しその影響度を分析、評価し、それに対応する戦略を打ち立て、リスクをコントロールする、という一連の流れが考案されている。
企業経営には様々なリスクがあり、代表的なものとして
- 製造物責任、機密漏洩などの「経営リスク」
- 地震、火災などの「災害リスク」
- 戦争、内乱、為替変動などの「カントリーリスク」
です。
最近では、情報漏洩・顧客情報漏洩などの「情報セキュリティリスク」があげられますが、それ以外にも数多くのリスクが企業経営には潜んでいます。
それらのリスクの発生予防に努め、リスクが実際に発生した時は被害を最小限にとどめるような活動を総称してリスク・マネジメントと呼びます。
リスクアセスメントとは?
○ ウィキペディア
リスクアセスメントとは、リスクの大きさを評価し、そのリスクが許容できるか否かを決定する全体的なプロセスのことである。
リスクアセスメントとは、もともとリスク管理プロセス内のサブプロセスである。
具体的には、リスク分析により明確化されたリスク因子に基づき、
- リスク因子により組織の財務基盤にどのような悪影響を及ぼしうるかの評価
- それにより、どのリスク因子を優先的に対処していくかの優先順位決定
- リスク対処のコストパフォーマンスを、上述の財務基盤への影響度も絡めて分析評価し、再検討
と言った手順を取る。
リスクとは?リスクマネジメントとは?何のため?(パート2)
で・・・
次に、例えばこんなのからも考えてみるのはどーでしょう?
( っ・ω・)っ
リスクは、必ずしも悪い意味ではない
■ 「希望格差社会」
リスクという言葉は、近代社会になってできた言葉である。
イタリア語の risicare に由来し、もともとは「勇気を持って試みる」という意味だったという。
ルネサンス時代のヨーロッパ社会では、中世の伝統を守る生活に別れを告げ、外には、大航海に「勇気をもって」船を出し、内ではサイコロ賭博などのギャンブルが始まった。
賭け率の計算の必要から「確率論」が誕生し、同時にリスクに対処するための仕組みである「保険」が発明される。
日本語の「危険」は、英語のデンジャー(danger)に近い。
近づくと確実に生命、健康、財産などを失うものをいう。
また、英語にはハザード(hazard)という言葉があり、「差し迫った危険」というニュアンスがあり、潜在化した危険ということができる。
これらの言葉は、常に悪い意味で使われる。
しかし、リスクは、原義が「勇気を持って試みる」という意味であるから、必ずしも悪い意味ではない。
何かを得るためについてまわる危険性であり、必ず出会うわけではないというニュアンスがある。
危険が伴うことを知りながら、その危険に出会うかもしれない状況に身をさらして、何かを達成しようとする時、その危険をリスクと呼ぶ。
リスクは「主観的なもの」であるという議論もある。
将来のことを何も考えなければ、本人にとって、リスクは存在しない。
突然、危険が目の前に現れるだけである。
リスクの個人化が進行するということは、自己決定や自己責任の原則の浸透と表裏一体である。
リスクに出会うのは、自分の決定に基づいているのだから、そのリスクは、誰の助けも期待せずに、自分で処理することが求められているのだ。
失業したり、フリーターになるのは、自分の能力の問題である。
離婚したのは、離婚するような相手と結婚したからである。
そして、保険会社が倒産して保険金がもらえないのは、危ない会社を選んだ個人の責任であるというように、保険というリスクヘッジに伴うリスクの責任までもとらされるのである。
現在日本では、リスクの普遍化が進行し、「意志によっては」避け得ないものとなっている。
そして、リスクが避け得ないものとなると同時に、個人は、そのリスクをヘッジすること、そして、生じたリスクに対処することを、個人で行わなければならない時代になっている。
そのリスクに対処しなくてはいけない個人の間に差がついているのが、近年の傾向なのだ。
現実を確認することは、危機管理を行うために欠かせない一歩
■ 「ヒトはなぜ先延ばしをしてしまうのか」
過度の楽観主義の罠に落ちないためには、いくらかの楽観主義をもつ必要がある。
「現実原則」を実践し、現実を直視しなくてはならない。
現実原則を実践する人は、子どものように衝動のまま行動するのではなく、夢を実現するためにどういう代償を払う必要があるかを現実的に考える。
その一環として、どこに落とし穴があるかを予測し、失敗を回避したり、失敗のダメージを和らげたりする方法を検討する。
現実を確認することは、危機管理を行うために欠かせない一歩だ。
リスクマネジメントの勘違い
■ リスクマネジメントとは何か
リスクマネジメント。
この言葉は日本語に翻訳しにくいことから、勘違いされていることが多いように思います。
直訳すると「危険を管理する」という意味になるのですが、実際には「リスク」は「危険」とは似て非なるものです。
また、「マネジメント」を訳した日本語である「管理」も、何をどのように管理するのか、ハッキリとした答えを与えてくれません。
- リスクが高い=不確実性が高い=将来の予想がしにくい
- リスクが低い=不確実性が低い=将来の予想がしやすい
リスクとは「予想外の出来事が起こること」だと理解していただけたでしょうか。
ただし、企業経営に影響を及ぼすのは起こって欲しくない事象ですから、リスクマネジメントの対象となる「リスク」には、どうしても悪い出来事というイメージが付きまとってしまう、だから「危険」という訳語があてられている、ということなのです。
では、もう一方のマネジメントとは、どのような意味なのでしょうか。
悪い出来事が起こってしまうことを完全に抑止することでしょうか。
それとも、悪い出来事が起こってしまった後の対処方法を予め定めておくことでしょうか。
残念ながら、一般的に思われているこれらのイメージも誤解に基づくものといわざるを得ないのが現状です。
リスクマネジメントで行われる「マネジメント」を一言で表現するなら、高いリスクを低くすることと書けるでしょうか。
別の言い方をすれば、「予想の立てにくい将来の出来事」を「予想しやすくする」こととも表現できます。
経営全般に関わる事柄の不確実性をできる限り軽減することと言うこともできるでしょう。
まず、経営者が意識を改革する必要があります。
従業員は経営者の振る舞いや発言には敏感ですので、まずは己の身を正すところから始めるべきでしょう。
社会にとって有用な存在であり続ける努力が、業績として反映される時代の到来。
考え方によっては、企業の存在意義が原点に返ったのだと言うことができるかもしれません。
日本人はなぜリスクを回避したがるのか
■ 日本人はなぜリスクを回避したがるのか
「世界価値観調査」によれば、日本人は「自分は冒険やリスクを求める」のカテゴリーに自分が当てはまらないと思っている人の割合が世界で一番高い(70%強)。
日本人全体でリスクを避けようとする傾向が世界で際立っているのだ。
日本人はどんな場合でも他人から非難される可能性があることを避けようとする傾向が高い。
グローバル化が進む中でどう変わればよいのか分からず、いらだちばかりが募る日本人の心情は、世界価値観調査によく表れている。
つまり、置かれた状況に対して不安や怒りは強いものの、自らが変えていこうとする意識は低い。
自分の意見を発信して周りの人たちを変えようとする人は少ないと言われている。
ただし、状況が明確であれば(自由になんでもやっていいのだと分かれば)、米国人と同様に自己主張をする。
日本人のリスク回避志向は心の問題として扱うのではなく、リスクを積極的に取ろうとする人たちが利益を得られるような社会の仕組みを構築することが不可欠である。
リスクテイキングに対する社員たちの不安をなくすには
■ 「こうすれば組織は変えられる!」
今日、リスクテイキングの能力はあらゆる場面で要求される。
リスクをすべて避けようとすることこそ、最も大きなリスクを生み出す行為となる。
リスクを拒否する人たちは、何を行うにしても最も安全なアプローチを求める。
リスクテイキングを企業文化の中心要素にすることを真剣に考えているならば、成功したときの報酬を十分に高く、失敗したときのペナルティをできるだけ小さくするシステムをつくるべきである。
リスクテイキングに対する社員たちの不安をなくすには、結果を心配せずに、つまり失敗を恐れずにリスクを冒すことのできる文化をつくらなければならない。
大胆な積極性は、それを歓迎する環境があるとき、成功の可能性を大きくする。
組織に属す人々がリスクを取るためには、「支援」を受け続けることが不可欠となる。
また、リスクを取るには、相応の準備をしておかなければならない。
リスクを取った個人が致命的な影響を受けることがあってはならない。
権限と責任が不釣合いな組織では、誰もリスクをとりたがらない
■ 「「一体感」が会社を潰す」
権限のある人が、その権限を使ってビジネスを行い、成果をあげれば報酬を受け取り、失敗すれば責任を問われるというのが正論です。
ところが、この正論が通用しないのが日本の組織です。
権限は与えられず、責任だけとらされる組織にいるメリットはゼロです。
権限と責任が不釣合いな組織では、誰もリスクをとりたがりません。
誰もリスクをとりたがらないのですから、当然、リターンもない、じり貧の組織になります。
「挑戦しよう」「新しいことにチャレンジしよう」といくら掛け声をかけたとしても、思ったとおり自由にやらせてもらえず、失敗したら責任をとらされることがわかっているのですから、誰もそんな挑戦などしません。
誰もリスクを取ろうとしなくなる理由
■ 右肩下がりの時代を生き抜く3つの方法
人事慣行に関していえば、日本は中国以上に共産主義的だ。
いま果たしている役割や貢献よりも、平等さや既得権の方が意味を持つ。
その結果、大きな失敗でもしない限り、いまのポジションに居続けることができる。
言い換えれば、誰もリスクを取ろうとはしなくなるのだ。
リスクの有無を行動の基盤にしてはならない
■ リスクの有無を行動の基盤にしてはならない(3分間ドラッカー)
「事業においては、リスクを最小にすべく努めなければならない」
「だがリスクを避けることにとらわれるならば、結局は、最大にしてかつ最も不合理なリスク、すなわち無為のリスクを負うことになる」
「リスクの有無を行動の基盤としてはならない」
「リスクは行動に対する制約にすぎない」
(『創造する経営者』)
リスクには4つの種類がある。
- 負うべきリスク、すなわち事業の本質に付随するリスク
- 負えるリスク
- 負えないリスク
- 負わないことによるリスク
である。
自営業者にとっては「事業に失敗すること」とは?
■ 「借金なんかで死ぬな!」
自営業という立場は過酷です。
大企業の社長の場合、責任の範囲がはっきりしていますので、会社を経営破綻に導いても基本的には社長をクビになる程度で済みますが、自営業者の場合、事業資金の借入を社長個人が連帯保証している場合がほとんどであり、中には奥さんの実家を担保提供していたり、個人名義のカードローンで資金繰りしていることも少なくないので、倒産すれば債権者から個人資産の処分まで求められるのが当たり前です。
事実上の無限責任ですね。
このため、自営業者にとっては「事業に失敗すること」は「ほぼ全ての資産を失うこと」とイコールなのです。
にもかかわらず、失敗したときに備えての「意識」があまりにも希薄です。
「知識」もあまり行き渡っていません。
悲劇の原因はここにあります。
大事なのは、「意識」と「知識」の両輪です。
リスクをとるのがリーダーの役目
■ 「採用基準」
リーダーとは「決める人」です。
検討する人でも考える人でも分析する人でもありません。
リーダーとは、たとえ十分な情報が揃っていなくても、たとえ十分な検討を行う時間が足りなくても、決めるべき時に決めることができる人です。
日本の組織の決断が遅いと言われるのは、この点におけるリーダーシップの差が現れているのだと思います。
当然ですが、情報が完全に揃っていない段階で決断をすることには、リスクが伴います。
このリスクをとるのがリーダーの役目なのですが、日本では時に、「リスクを、人ではなく場所に負わせる」というびっくりするような手法が使われます。
たとえば「それはどこで決まったのか」という問いと、「○○会議で決まった」という回答が有り得ることは、日本における「決める」という行為の特殊性をよく表しています。
決めたのは場所ではなく、人のはずです。
誰かがその会議において決めたはずです。
しかし私たちは決めた人をあえて曖昧にするために、「会議で決まった」という言い方をするのです。
決めることができないのは、責任をとるのが怖いからでしょう。
決断を下す人には、常に結果責任が問われます。
それが怖い人はいつまでも決断を引き延ばします。
そして彼らが決断をしない理由(言い訳)はいつも同じです。
それは、「十分な検討時間がなかった」と、「必要な情報が揃っていない」のふたつです。
しかし過去のことならともかく、未来のことに関して十分な情報が揃うことはありません。
日本の危機管理に対する考え方
■ 「組織行動セーフティマネジメント」
ある企業では、コンプライアンス違反を指摘されることを恐れるあまり、従業員の禁止行動をどんどん増やしている。
売り上げを立てなければいけないのに、「あれもダメ、これもダメ」と過剰規制をかけられる営業スタッフの嘆きも、もっともである。
一方で、ただコンプライアンスを宣言するだけで、それでいいと思っているような企業もある。
帝国データバンクが把握しているだけでも、コンプライアンス違反が原因で失職した従業員が3550人おり、その内容は「粉飾」がトップである。
2代目社長がワンマン指揮を振るうある企業では、データ改ざんが暗黙の了解で毎年行なわれ、社内の慣習にすらなっていた。
「このままではまずい・・・」
従業員の多くが危機感を抱いているのに、トップが動いてくれない限り変えられない。
機密漏洩、企業買収、訴訟問題・・・
こうしたことによるビジネス上の危険は、グローバル化が進むビジネス社会で、もはや避けて通れない。
また、従業員の雇用に関するトラブルも大きな問題に発展する場合がある。
セクハラ、パワハラなど従業員同士のトラブルも経営に大ダメージを与える。
企業に所属する従業員のトラブルは、個人の問題に留まらず企業全体に波及するケースもあり、社をあげて早急に取り組んでいく必要がある。
さらに、経済のグローバル化は、雇用のグローバル化を促進している。
その結果、文化や風習が異なる外国人従業員を雇用することでのトラブルや、海外で活躍する日本人従業員が現地で事故に巻き込まれるケースも増えてきている。
これまで平和な環境でビジネスを進めてこられた日本の危機管理に対する考え方に大きな隔たりがあるのが現実だ。
大きな企業事故が発生する原因は、もとはと言えば一人の従業員の小さな行動にある。
企業80%から95%が、いち従業員の「非安全的」な行動から起きるということがわかっているが、そのほとんどのケースにおいて、原因をつくった従業員には悪意などないのである。
「まさか危険な事態になどならないだろう・・・」
危険につながる小さな行動は、日常の中にあまりにもたくさん存在するために、慣れっこになっていて、なかなか危機意識が持てない。
人の命を奪うような交通事故を起こした人間も、「わざと事故を起こしてやろう」などと考えていたわけではない。
ちょっとしたことが原因で、思いもよらない結果を引き起こしてしまうのである。
経営者やマネージャーは、この事実を深く認識しなくてはいけない。
売り上げを伸ばすことだけを考えたならば、経営者やマネージャーが率先して範を示さなくても、一人ひとりの従業員の働きによってそれが可能になることがある。
(継続的には無理であるが)
しかしながら、安全管理においては、この公式は当てはまらない。
よほど、経営者やマネージャーが本気にならなくては、企業の安全は成り立たないのだ。
つまり、こと安全管理においては、経営者やマネージャーのリーダーシップが強く問われているのである。
安全管理においては、経営者やマネージャーが動かなければ、従業員は動かない。
偽物のリーダーではなく、真に求められる本物のリーダーであるかどうか、その資質が問われるのがセーフティ問題なのである。
「まさか、こんなことになるなんて思ってもみなかった」
私たちがこう言い訳するとき、たしかに思ってもみなかったのかもしれないが、そこに小さな危険性が存在していること自体は知っていたはずである。
しかし、強く認識することができなかっただけ。
あるいは、認識することを避けていたと言うほうが正しいかもしれない。
人は、頭で理解しているとおりには正しく動けない。
自分が危険な目に遭いたくないし、他人を危険な目に遭わせたくもない。
ここまでは理解している。
しかし、この理解どおりにいつも正しく動けるとは限らないのが人間だ。
そうしたことを承知したうえで、「企業文化」にしていく覚悟が、経営者やマネージャーに強く求められている。
事故は個人が起こすものではなく、組織の中で起こるもの
■ 「医療事故 ― なぜ起こるのか、どうすれば防げるのか」
事故は個人が起こすものではなく、組織の中で起こるものですから、個人に責任を押しつけて処分し、それで片付けてしまうやり方では、事故を起こしやすい組織の体質はそのまま残ってしまいます。
一方、自分の責任を認め、事故の経過や状況を正直に明らかにしたばかりに、それが証拠となって処分が重くなるということになれば、その後は「事故を否定する」「不都合な点はできるだけ隠す」ようになってしまいがちになるのは、人間の心理の面から明らかです。
同様に、組織についても、事故後に組織が自発的に事故調査をし、自らの組織の問題点を明らかにして発表することによって、かえって重い処分を受けるということになれば、以後、「できるだけ隠す方が得」となってしまいます。
それでは「事故から学ぶ」ことができなくなり、安全な組織に改善するチャンスを逃すことになるでしょう。
最良のリスクヘッジの方法
■ 「フリーエージェント社会の到来 ― 「雇われない生き方」は何を変えるか」
これまでは、同時に複数の仕事をもって、仕事を「分散」させる人はほとんどいなかった。
なによりも、そんなことをする必要がなかったのだ。
ひとつの企業に就職すること、いわば自分のもっているすべての人的資源をひとつの会社に投資することは、基本的に賢明な選択と考えられていた。
しかし、いまや大半の人は、すべての人的資源をひとつの企業に投資することは全財産を株に投資するのと同じように愚かなことだと信じている。
資産運用の世界と同じように、仕事の世界でも「分散投資」が生き残りの条件になりつつあるのだ。
雇用の保障がもろくも崩れ去った結果、労働者にとって、仕事の「分散」は不可欠になった。
幼い息子と娘が働きはじめる頃には、「雇用の保障」などという言葉はもはや死語になっているだろう。
こうした変化をもたらした大きな要因は、リスクである。
組織が労働者に安定を保障していた時代には、ビジネスのリスクは組織がほとんど引き受けていた。
海外の企業との競争にさらされることはなかったし、国内の市場は巨大企業の支配下にあり、新しいテクノロジーが次々と登場することもなく市場は安定していた。
リスクは存在しないも同然だった。
一方、個人は安定をすべてに優先させ、リスクのもたらすマイナスの影響から身を守るために、リスクのプラスの部分を手放すことをいとわなかった。
しかし競争が激化し、新しいテクノロジーが普及して、ビジネスにともなうリスクはかつてとは比べものにならないほど大きくなった。
その結果、企業はすべての負担を背負うことに消極的になりはじめ、リスクを従業員に転嫁するようになった。
労働者の教育や訓練についても、似たような現象が起きている。
かつて企業は、新入社員をまる1年かけて教育したものだ。
しかし、変化のスピードが速くなって、企業はそうした投資をしたがらなくなった。
新しい技術を身につけたり、技術に磨きをかける負担を従業員に押しつけはじめたのだ。
その結果、遠隔教育やコミュニティカレッジで学ぶ社会人が増えている。
もちろん、大きなリスクを背負うことに後込みする人もなかにはいる。
そういう人は、リスクが増えれば痛みが増えると考えているのだろう。
一方、リスクの拡大を歓迎する人もいる。
そういう人は、リスクが増えれば報酬が増えると考えているのだろう。
大半の人はこの中間だ。
ほとんどの人は新しい試練におびえつつも、それを避けて通れないことをよくわかっている。
最良のリスクヘッジの方法は、様々なプロジェクトや顧客、技能などをもつこと。
すなわち仕事を「分散」させることだ。
会社勤めのかたわら副業をもつ人も増えている。
時代は変わった。
副業をもつことは、自分の人的資本の投資先を分散させる手段だ。
つまり、勤務先の会社が潰れたり、仕事を失ったりするリスクからの自衛策なのである。
近頃は、企業は社員教育をしたがらないし、起業家精神をもった社員が好まれる。
副業をもつことはクビにいたる道ではなく、仕事を得るための道になったと言っても過言ではなさそうだ。
たくさんの顧客やプロジェクトを抱えて働けば、ひとりの上司の下で働くより楽しいだけでなく、安全でもあるのかもしれない。
取引先や仕事、人脈を広げたほうが、仕事を失う危険を減らすことができるからだ。
最大のリスクはリスクを冒さないこと、リスクを冒せなくなること
■ 問題なのはリスクを冒さないこと冒せなくなること(3分間ドラッカー)
「企業活動に伴うリスクをなくそうとしても無駄である」
「現在の資源を未来の期待に投入することには、必然的にリスクが伴う」
「リスクの最小化という言葉には、リスクを冒したり、リスクをつくりだすことを非難する響きがある」
「つまるところ、企業という存在そのものに対する非難の響きがある」
(『マネジメント』)
経済活動において最大のリスクは、リスクを冒さないことである。
そしてそれ以上に、リスクを冒せなくなることである。
リスクをかけすぎると一貫性が保てなくなる
■ 「コア・コンピタンス経営」
目標を絞らないで、手段ばかりを絞っている会社が多い。
会社の長期的な方向に関する明確な構想がなければ、コア・ビジネスの定義は年中変わり、短期的な財務上の都合だけで行われる。
方針がはっきりしていなかったり、戦術がしきたりになっていたりすると、未来の成功はかなり危うくなる。
「どこに向かっているかはわからないが、慣れ親しんだ道から出るつもりはない」
という状況が、最も危険なのである。
必要なのは、明確な方針から生まれる新しい発想である。
新しい発想には自由が不可欠であるが、自由と放任は違う。
手段よりも目標を明確にしなくてはならない。
また、方針には一貫性が必要である。
すべての山や谷を予測するのが不可能である以上、目的地にたどり着く方法については十分な裁量の余地がなければならない。
戦略の方針は「方向」を大まかに指定するものであって、「方法」を指定するものではない。
リスクをかけすぎると一貫性が保てなくなる。
早まって未来への可能性を秘めたルートを放棄することは、早まって特定のルートに決めてしまうのと同じくらい致命的な結果を生む恐れがある。
リスクとは?リスクマネジメントとは?何のため?(パート3)
うーむ・・・
どっ・・・、どーでしょう???
「そっ・・・、そーだったのかー! ガ━━(= ̄□ ̄=)━━ン!! 」
「だからかー!!だからだったのかー!! ヾ(.;.;゜Д゜)ノ 」
という方も、いらっしゃれば・・・
「ナルホド・・・、ちょっぴりわかった気がするかも・・・ ヽ(´ー`)ノ 」
「あ、なーんだー、そーだったんだ~ (〃▽〃) 」
という方も、いらっしゃれば・・・
「わかったよーなわからんよーな・・・ ( ̄д ̄;) 」
「やっぱ、頭がウニ状態じゃー!よくわからーん! \(  ̄曲 ̄)/ 」
という方も、いらっしゃるんじゃーないでしょうか?
他にも、例えば・・・














などなども含めると、いろんな意味で考えさせられちゃいません? (^^)
ふーむ・・・、こーやって考えてみると・・・
まだ見えていないだけで・・・
意外なところにヒントがいっぱい溢れている
おお~っ ━━━━ヽ(゜Д゜)ノ━━━━ 見っけ~♪
のかも~???
なーんて、感じません?
(〃▽〃)
どっ・・・、どうでしょう???
皆さまは、どう思われますか?





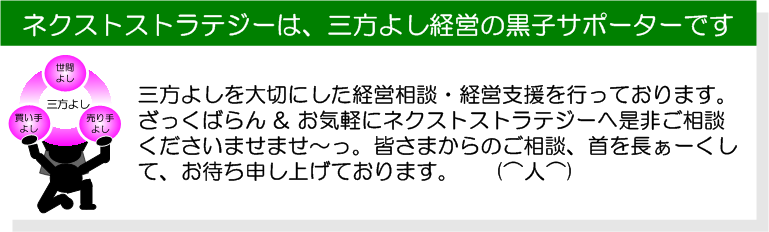
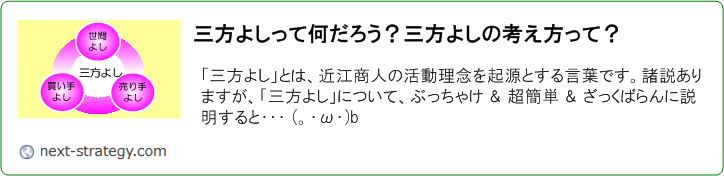


コメント