「メリットって何だろ~?デメリットって何だろ~???メリットやデメリットの判断基準って???ほげほげのメリットとかデメリットとかって、何を基準にどう判断したらいいんだろ~??? 。゚(゚^o^゚)゚。 」
「知名度が高くて有名なあの大先生が言っていたんだから、コレってメリットだけなんだよね?デメリットは全くないんだよね?ね? (;´゚д゚`) 」
「ほにゃららってやった方がいいのかな~???それとも、やらない方がいいのかな~???一般的なメリットって何だろ~?一般的なデメリットって何だろ~???( ̄▽ ̄|||) 」
「ネット検索しても、いろんな本を読んでも、いろんな人の意見を聞いても、メリットやデメリットが何なのか、わかりそーでやっぱりイマイチよくわからないよー!! o゚p(∴´⌒`∴)q゚o。 」
などなど・・・
「経営理念・ビジョン・経営計画等の作成」、「組織人事戦略(戦略的な組織づくり)」、「人材育成戦略(戦略的な人材育成)」、「自律型人材育成」などのお手伝いを行なっているからなのか・・・
「爆発・炎上・崩壊組織」で消防のお手伝いを行なうこともあるからなのか・・・
このような声をお聞きすることもあるんですが・・・
( ´・ω・`)
こーんなボログをカキカキしているからか・・・
「ほげほげのメリット」とか「ほにゃららのデメリット」とかのキーワードで検索して、訪問してくださる方もたくさんいらっしゃるんですけど・・・
(海より深ぁーく (⌒人⌒) 感謝感謝ですぅ~♪)
その度に、いろんな意味で考えさせられるコトもあるんですけど・・・
ンーン (( ̄_ ̄*)(* ̄_ ̄)) ンーン
それもあって・・・
「『ほげほげ』とやらのメリットやデメリットって、いったい何なんだろーか?」
「それは、誰にとってのメリットやデメリットなんだろーか?」
なーんて、あっちゃこっちゃの記事にカキカキしてあるんっすけど・・・
( ̄  ̄;)
それに、コレってもしかしたら・・・








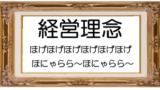







などなどにも、ある意味関係するっちゃーするのかも~???
なーんて感じるコトもあるので・・・
そもそもの話、メリットって、いったい何なんだろーか?
デメリットって、いったい何なんだろーか?
一般的なメリットって、どーゆーコトなんだろーか?
一般的なデメリットって、どーゆーコトなんだろーか?
何がどーだったら、メリットがあるって感じるんだろーか?
何がどーだったら、デメリットがあるって感じるんだろーか?
メリットやデメリットの判断基準って何なんだろーか?
メリットがあるとかメリットがないとかって、誰がどんな基準でどう判断するんだろーか?
デメリットがあるとかデメリットがないとかって、誰がどんな基準でどう判断するんだろーか?
メリットやデメリットの把握って、どんな時には必要なんだろーか?
メリットやデメリットの把握って、どんな時には必要じゃないんだろーか?
何のために、メリットやデメリットについて考えるんだろーか?
誰のために、メリットやデメリットについて考えるんだろーか?
などなども含めて、一緒に考えてみません? (^^)
あ、モチロン、「自律的に」という意味で。
ちょっと興味あるかも~?
って言ってくださる方は、お付き合いいただけると嬉しいです。
(^^)/
メリットとは?デメリットとは?判断基準って?(パート1)
んーと・・・
まずは、例えばこんなのから考えてみるのはどーでしょう?
(。・ω・)b
汎用技術のメリットとは?
■ 「機械との競争」
汎用技術が、生みの親の産業にだけ利益をもたらすわけではないことに注目してほしい。
たとえばコンピュータは、ハイテク産業のみならず、デジタル技術やデータを扱う産業すべてにメリットをもたらす。
そして今日では、あらゆる産業がこれに該当する。
コンピュータとネットワークがもたらす新しいチャンスはそれからそれへと拡がっていく。
それは創造的破壊の継続的なプロセスであり、新技術と既存技術を組み合わせることによって、仕事、職業、ひいては企業のあり方そのものにも深い変化をもたらすだろう。
さまざまな選択肢のメリットとデメリット
■ 「ワーク・シフト」
私たちの働き方の未来を形づくる要因はすべて、暗い未来を生み出す可能性がある半面、明るい未来を生み出す可能性も秘めている。
暗い未来のシナリオが実現すれば、テクノロジーの進化にともない、私たちはいつも時間に追われ続け、バーチャル化が加速する結果、多くの人が深刻な孤独を味わうようになる。
そのうえ、グローバル化の影響により、いわゆる勝ち組と負け組の格差が拡大し、グローバルな下層階級が新たに出現する。
家族の結びつきが弱まり、消費するブランドを通じて個人の評価が決まる傾向に拍車がかかり、大企業や政府に対する信頼感がむしばまれ、先進国では人々が幸せを感じにくくなる。
地球の気温がさらに高くなり、海水面が上昇し、乏しい資源の争奪戦が激化する。
しかし、ピンチは常にチャンスと表裏一体の関係にある。
もっと明るい品折が実現する可能性もある。
テクノロジーが進化すれば、世界の50億もの人々がインターネットを通じて結びつき、みんなで力を合わせて難しい課題に取り組む時代がやって来る可能性もある。
新しいテクノロジーのおかげで、地球上のすべての子どもが人類の叡智に触れられるようになる可能性もある。
グローバル化がさらに進めば、世界が一体になってイノベーションに取り組んだり、低コストでイノベーションを成し遂げる方法を途上国が先進国に教えたりする時代が到来するかもしれない。
先進国が大倹約時代に突入すれば、大量消費社会に終止符が打たれて、消費より充実した経験を重んじる社会への転換が実現するかもしれない。
高齢化が進んで70歳まで働くのが当たり前の時代が来れば、高齢になっても充実した人生を送れるようになるかもしれない。
社会の変化にともない、家族のあり方が大きく変わり、企業で重要な意思決定をおこなう地位に就く女性が増え、家族で父親がもっと育児に参加するようになる可能性もある。
エネルギー消費の枯渇と地球温暖化に関する懸念が高まれば、エネルギー消費の少ないライフスタイルに転換し、遠距離通勤をやめて職住接近型の生活を選び、飛行機をあまり利用しなくなれば、それも悪くはない。
つまり、私たちがどういう行動を取れば、どういう未来が訪れるかというシナリオを複数パターン描き出すことは可能だ。
どういう要素を人生で優先させたいかは、一人ひとり違う。
あなたの選択は、あなた自身のニーズに沿っておこなえばいい。
未来の世界で幸福な働き方を実践するためにカギを握るのは、さまざまな選択肢のメリットとデメリットを深く理解したうえで、自分の道を主体的に選択する。
職業生活でなにを望むのか?
それを実現するために、どのような代償を覚悟するのか?
メリット・デメリットを判断するのは、結局のところ「人それぞれ」
■ 最後は自分で決めましょう
物事の多くにはほとんどの場合「メリット」と「デメリット」の両方がある。
「会社員」VS「フリーランス」とか、「ベンチャーに就職」VS「大企業に就職」とか、「持ち家」VS「賃貸」とかいった論争がされることがあるけど、これらの論争がどちらかの立場の圧倒的な勝利で終わることは基本的にはない。
どちらの立場にもそれなりに分があるから、これだけ論争になっているのだ。
仮に100%メリットのみというものがあれば誰だってそれを選択するので特に論争は起きない。
自分が支持する立場が100%メリットしかない、ということはまずない。
双方のメリットとデメリットを考えた結果、自分にとっては、立場Aのほうが立場Bより優っていると判断できるので、立場Aを推している。
重要なのは、この「自分にとっては」という部分だ。
立場Aにaというメリットとa’というデメリットがあったとして、これらのメリットa、デメリットa’がどのぐらいのインパクトを持つのかは結局のところ人それぞれだ。
ある人にとってのaは+1だけど、別の人にとっては+100だったり、あるいはa’がある人にとっては-10で、別の人にとっては-1000なんてこともある。
メリット・デメリットについてはある程度客観的に抽出できたとしても、それを判断するのは結局のところ「人それぞれ」になってしまう。
自分はどちらを選ぼうか、という話は結局その人の価値判断に帰着する。
助言者の価値観で「◯◯のほうがいい」とアドバイスすることはできるけど、それはあくまで他人の判断にすぎず、自分にとって有益かどうかはわからない。
自分にとって一番の選択ができるのは、結局自分以外にはいない。
一点だけ忘れてはならないことがある。
最後の意思決定の前には、「メリット」と「デメリット」をできるだけ正しく把握するよう気をつけなければならない。
要は、「フリーランス」のデメリットを分かった上でフリーランスになるのと、分からずにフリーランスになるのとでは、全然結果が違うということだ。
「これからはノマドの時代っすよ!」という考えだけでは、事前のメリット・デメリットの把握として十分でないということは言うまでもない。
決められないのは、「判断基準が多すぎるから」
■ 「自分のアタマで考えよう」
十分すぎる情報があるのになぜなにも決まらないのでしょう?
理由は、「誰も考えていないから」です。
みんな「情報を集めて分析する」作業に熱中しています。
なにかを選ぶとき、選択肢が多いと悩みますよね。
こういうとき、私たちは「選択肢が多すぎる!」と感じるのです。
けれどじつはそれは間違いです。
決められないのは選択肢が多すぎるからではありません。
決められないのは、「判断基準が多すぎるから」なんです。
「あれもこれも」とすべての条件を満たしたくなるのが人の常です。
そしていつのまにかなにも決められなくなってしまうのです。
習慣化した行動は継続しやすく、疲れていても実行できるという利点
■ 「ヒトはなぜ先延ばしをしてしまうのか」
私たちの日常生活には、ほぼ無意識に繰り返している行動がたくさんある。
朝、寝ぼけ眼でも、朝食を食べ、歯を磨き、靴のひもを結べる。
習慣化した行動は継続しやすく、どんなに疲れていても実行できるという利点がある。
ある行動が習慣化すると、違う行動を取るほうが望ましい場合にも、私たちは同じ行動パターンを繰り返しがちだ。
同じレストランに足を運び、同じメニューを注文し、帰宅してテレビで同じ番組を見る。
もっと好ましい選択肢がほかにあるかもしれないと考えることすらしない。
どんなメリットがあるか説明され、納得すれば動く
■ 「「すみません」の国 」
日本であれば、自分の仕事が終わって手が空いているときに、「ちょっとこの仕事を手伝ってくれないか」と上司から言われれば手伝うだろう。
そうした日本での常識は、どうも多くの国では通用しないらしい。
欧米に限らず、海外勤務をした人たちがよく言うのは、日本と違って個人主義が徹底している国では、自分のノルマとして決められた仕事はするけれど、それ以上のことはしてくれないから戸惑うということだ。
組織よりも個人を拠り所とする場合は、自分のノルマ以外の仕事を手伝うには相当の理由が必要になる。
多くの場合、手伝うことで本人にとってどんなメリットがあるかが説明され、納得すれば動くようだ。
考えてみれば、日本では仕事の境界も曖昧で、どこまでが自分の仕事で、どこからが他の人の仕事かということが明確に区別しがたく、曖昧領域というようなものがあるように思われる。
それでもトラブルが生じない文化だということなのだろう。
そのいい加減さが、利他的行動をとりやすくする要因ともなっているのだ。
私たち日本人は意見を言えない、グローバルな時代に向けてもっと意見を言えるようにならないといけないといった論調が、マスメディアを通してさかんに聞こえてくる。
それはもっともな意見ではあるが、なぜ意見を言えないのかにもっと目を向ける必要がある。
意見を言えないということには、デメリットばかりでなく、何か良い面もあるのではないか。
ものごとの多義性に目を向けるほど、自分の視点からの意見を明言しにくくなる。
違う見方もあるはずだという思いがちらつくからだ。
相手の視点に立てるということは、自分の視点を絶対化せずに、ものごとを多面的に見ることができるということにつながる。
一面的にしかものごとを見られない人は、自分の見方を絶対的に正しいと信じ込む。
他者の視点を取り入れることで、利己的なホンネにブレーキをかけることができる。
日本的なコミュニケーションの欠点とされがちな傾向も、見方を変えれば、争いを防ぐ厚みのある二重構造をもっていると肯定的に評価することができるのだ。
日本型企業モデルの利点
■ 「日本の競争戦略」
日本型企業モデルは、一連の生産手法、人事政策、組織とリーダーシップに対するアプローチ、および多角化の方法等から構成される。
そして、それら構成要素はすべて、特徴的な企業目標によって導かれている。
独特の製品や、流通チャネルをはじめとする企業の諸施策は、このモデルから生まれたものである。
日本型企業モデルの利点のうち、欧米と日本の学者の間で共通に認識されているものとしては、従業員の職務能力の迅速な向上、強いコミュニティ意識の形成、従業員の企業への忠誠心の醸成、およびマネジャーの長期的視点に基づいた意思決定の奨励等があげられる。
日本型企業モデルでは、社内の強いコミュニティ意識や、従業員の忠誠心、および経営上の意思決定における長期的視点の形成等を意図した、一連の人事制度を強調する。
雇用する従業員数を限定するための厳しい選考制度、全社レベルの業績に基づいたボーナス制度、そして従業員参加型の経営スタイルは、すべてコミュニティ意識の形成に貢献していると考えられている。
日本的人事制度の中心は、終身雇用制である。
終身雇用制は男性の正社員に対して、定年を迎えるまで職を保証した。
この企業側のコミットメントは、従業員と企業のインセンティブを合致させた。
全社的なローテーション制度は、ビジネスのあらゆる側面に精通したゼネラリストとしてのマネジャーを育成した。
日本のマネジャーは、キャリア形成の過程でさまざまなポジションに配置されることを承知しているため、欧米のマネジャーと比較して変化に対してはるかに抵抗がなく、企業に対する忠誠心も高い。
破壊的なビジネスモデルの利点
■ 「経営の未来」
ファッションの好みを調整することは、宗教的信念を変えることよりおそらく簡単だろう。
同様に、ほとんどの企業幹部にとって、破壊的なビジネスモデルの利点を認めることは、固く信じている経営管理論の中核的な教義を捨てることより簡単なのだ。
戦略のライフサイクルが短くなっている世界において、イノベーションは企業がその成功の持続期間を引き延ばすことができる唯一の方法である。
それは容赦ない競争の世界で企業が生き残るための唯一の方法でもある。
参入障壁の崩壊、超効率的な競争相手、顧客の力・・・
これらの要因がこれから先、利幅を圧縮していくだろう。
この苛酷な新世界では、あらゆる会社が厳しい選択を迫られることになる。
イノベーションの炎を燃え立たせるか、それとも極端に低い人件費だけが生き残るか倒産するかを分かつ要因となる世界で、ぎりぎりでやっていく覚悟をするか、という選択である。
この点を考えると、イノベーションをすべての社員の業務にしている企業がほとんどないのは驚くべきことだ。
大方の企業で、イノベーションは依然として組織の片隅に追いやられている。
効率を追求するなかで、企業は業務から多くの無駄をそぎ落としてきた。
それ自体は、もちろん悪いことではない。
在庫レベルの低減、運転資本の縮小、一般管理費の削減という目標に異を唱えられる人間はどこにもいない。
だが、問題は、会社から無駄を全部排除したら、イノベーションも全部排除されてしまうことだ。
イノベーションには時間が必要だ。
自分の損にならないような決断をするしかないとき
■ 「人として正しいことを」
価値観を大切にする従業員と、規則を遵守する従業員の間には違いがある。
前者は「すべき」に律せられる。
彼らは価値観や信念に沿って行動し、自己統治する。
選択を迫られたときは、堅固な価値観が手引きとなる。
一方、情報に基づいて黙って従う従業員は、規則にしか関心がない。
「やってもいい」の世界に生きているのだ。
もしもお偉方が規則に従おうとしなかったら、自分の損にならないような決断をするしかない。
自分で決められなければ、それができる管理職なり上司なりに判断をあおくが、誰かが決定するまでは自分の損得勘定が前面に出ることになる。
結果として、時間や効率ばかりか、安全そのものも脅かされる。
損得勘定でしか物事を見ることができなくなってしまうとき
■ 「どん底からの成功法則」
誰にも、「おっ、これは儲かるかもしれないな」と一瞬思ってしまうおいしい話に出会うことがあるものです。
ところがそう思ってしまったら最後、損得勘定で物事を見ると、それは必ず失敗してしまいます。
判断を下さなくてはならないという場面で、人はどうしてもこれは自分にとって得となるだろうかということを考えてしまいます。
「欲」というのは、たしかに自分を突き動かしてくれる原動力になってくれます。
しかし、その「欲」を判断基準にしてしまうと、損得勘定でしか物事を見ることができなくなってしまうのです。
目先の損得を見ているかぎり、人を見たらお金と思えということになります。
いくら品性下劣な人でも、お金の面で得だと思うと、いい人に見えてしまい、お金の仮面の下にあるその人格やホンネは見えてきません。
お金の面だけではありません。
この人とつきあっておくと偉い人に紹介してもらえる、人脈ができる、などと損得で人間を見ていると、その人は単に人を紹介してもらうための道具になってしまい、その人自身がもっているいいものも見えなくなってしまうのです。
会社で社員を雇うときも、どうしても会社に直接的な「得」になるような人間を採用しようとしまうことが多いと思います。
「こいつがいると売上が伸びそうだな」
「こいつ能力ありそうだな」
「こいつは学力もあるし、いいぞ」
とさまざまに会社の得を思うのです。
なぜ人を正しく見ることができないのかというと、それはこちらの損得勘定が頭にあるからです。
「欲」を物事の判断基準にし、損得勘定で見ると視界が曇ってしまいます。
欲というフィルターが真実を覆い隠し、欲によって理性の声はかき消されるのです。
「損したくない」ことばかり考えていると・・・
■ 「この世でいちばん大事な「カネ」の話」
金銭感覚っていうのは、日々の積み重ねによってつくられていくものなんだよ。
ギャンブルや、投資、借金は、その人の金銭感覚を拡大して見せてくれるものだけど、その金銭感覚をつくる元は、子どものころからの日常の習慣なんだと思う。
習慣っていうのは、一度身についてしまうとなかなか変えられないし、変わらないものだからね。
無意識で繰り返していることが多いぶん、もしかするとギャンブルよりももっとこわいかもしれないよ。
大人がそういう態度だと、子どもだって勘違いしちゃう。
「損しない」ってことがいちばん大事みたいに思っちゃう。
「損したくない」ってことばかり考えていると、人って、ずるくなるんだよ。
少しでも人より得しようって思うから、「だったら、ズルしちゃえ」っていう気持ちが出てきてしまう。
ささいなきっかけで、それがどんどん卑しい行為に結びついてしまう。
きっかけはささいでも、「このくらい、べつにたいしたことはないよな」っていう、自分にだけ都合のいい気持ちが、あとあとの大きな分かれ道になってくる。
人間、誰だってちょっとでも「得をしたい」って思うものでしょ。
だけど、うかうかと一線を越えちゃうと、ダムに空いた小さな穴みたいに、そこから金銭感覚って崩れていってしまうものなんだよ。
モノを借りて返さなかったり、お金を払わないようにしたからって、それで「得した」なんてことは絶対にない。
あとで絶対に「マイナス」になるものなんだよ。
「ちょっとそれっておかしいかも」
「これっていいのかな?」
「どうなんだろう?」
自分なりのしっかりした金銭感覚をつくっていってほしい。
メリットとは?デメリットとは?判断基準って?(パート2)
んでもって・・・もしかしたら・・・

なんかにも、ある意味関係するかもしれないので、こんなのからも念のために一応考えてみるのはどーでしょう?
( っ・ω・)っ
メリットとは?
○ コトバンク
- 利点。価値
- 手柄。功績
○ はてなキーワード
- 功果。対価。功績
- 直接的な利点
○ ニコニコ大百科
メリットとは、「自分(または他人)にとって得(好都合)になる」という意味の英単語である。
「利点」などとも訳される。
デメリットとは?
○ goo辞書
欠点。短所。損失。
○ はてなキーワード
それがあることで、不利になる点・事項。
○ ニコニコ大百科
デメリットはメリットに打ち消しの単語を付けた言葉で、「自分に起こる悪い内容」の様な意味になり「欠点」「短所」の意味で使われている。
利点とは?
○ コトバンク
有利な点。
また、長所。
好都合な点。
好都合とは?
○ コトバンク
条件などにかなっていて、都合がよいこと。
また、そのさま。
○ Weblio辞書
都合がよいこと。
ぐあいがよいこと。
また、そのさま。
都合とは?
○ Weblio辞書
- 物事をするに当たっての事情。具合
- 物事をすることのできない事情。さしさわり。さしつかえ
- やりくりすること。工面すること。
得とは?
○ goo辞書
利益を得ること。もうけること。
有利であること。また、そのさま。
(「徳」とも書く)
損とは?
○ コトバンク
- 利益を失うこと。また、そのさま。不利益
- 努力をしても報われないこと。また、そのさま
- そこなうこと。こわすこと
○ ニコニコ大百科
損とは、何かを失うこと、何かを損なうこと、期待通りの結果が得られないこと、である。
損得勘定とは?
○ はてなキーワード
どんぶり勘定で損か得かという二者択一の判断をする場合等に用いる。
○ Weblio辞書
自分にとって損であるか得であるかを打算的に判断するさま。
利害を指標として物事を考えること。
二者択一とは?
○ goo辞書
二つの事柄の、どちらか一方を選ぶこと。
二つの選択肢のうちの一方を選ぶこと。
メリットとは?デメリットとは?判断基準って?(パート3)
うーむ・・・
どっ・・・、どーでしょう???
「そっ・・・、そーだったのかー! ガ━━(= ̄□ ̄=)━━ン!! 」
「だからかー!!だからだったのかー!! ヾ(.;.;゜Д゜)ノ 」
という方も、いらっしゃれば・・・
「ナルホド・・・、ちょっぴりわかった気がするかも・・・ ヽ(´ー`)ノ 」
「あ、なーんだー、そーだったんだ~ (〃▽〃) 」
という方も、いらっしゃれば・・・
「わかったよーなわからんよーな・・・ ( ̄д ̄;) 」
「やっぱ、頭がウニ状態じゃー!よくわからーん! \(  ̄曲 ̄)/ 」
という方も、いらっしゃるんじゃーないでしょうか?
こーやって考えてみると・・・
メリットやデメリットなど、それぞれの言葉の意味がわからなければ・・・
気づけないこと、気がつかないこともあるけど・・・
それぞれの言葉の意味だけを見ていても
それぞれの言葉の違いだけを見ていても
気づけないこと、気がつかないこともある
んじゃーないかな~???
( ・ _ ・ )
なーんて感じちゃったりなんかしません?
(〃⌒∇⌒)ゞ
他にも、例えば・・・



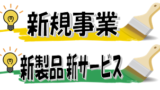










などなども含めると、いろんな意味で考えさせられちゃいません? (^^)
ふーむ・・・、こーやって考えてみると・・・
まだ見えていないだけで・・・
意外なところにヒントがいっぱい溢れている
おお~っ ━━━━ヽ(゜Д゜)ノ━━━━ 見っけ~♪
のかも~???
なーんて、感じません?
(〃▽〃)
どっ・・・、どうでしょう???
皆さまは、どう思われますか?





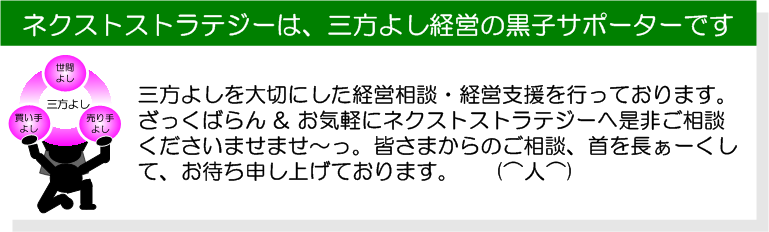
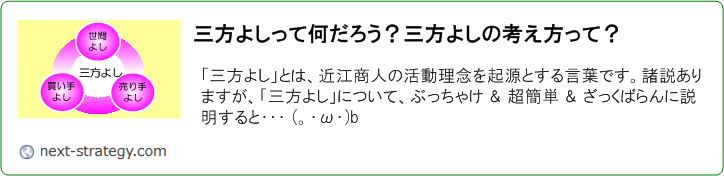


コメント