「終身雇用制度って何だろ~?年功序列制度って何だろ~?何がどう違うんだろ~?( ̄ー ̄?) 」
「終身雇用制度や年功序列制度のメリットやデメリットって何だろ~? ( ̄∧ ̄ ) 」
「終身雇用制度や年功序列制度と、成果主義や能力主義とどっちの方がどういいんだろ~?どっちの方が優れているんだろ~? (;゜∇゜) 」
「どっちの方が優秀な人材を採用できるんだろ~? (ーー;) 」
「終身雇用制度や年功序列制度だと、人件費の負担がめっちゃ重いよね・・・ (|||▽ ) 」
「そーゆー観点で比較するなら、成果主義や能力主義の方がいいような気がしなくもないんだけど??? (;・∀・)」
「だけど、なるべく長く働いてもらった方が人材採用の手間も省けるし人材育成の手間も省けるし、長い目で見たら生産性も向上しそうだしコストも下がりそうだもんな・・・ (´ε`;) 」
「強い組織をつくるには、終身雇用制度や年功序列制度の方がいいんだろーか?それとも成果主義や能力主義の方がいいんだろーか? (; ̄ェ ̄) 」
「終身雇用制度や年功序列制度と、職務型や職能型との関係って何だろ~? 。゚(゚^o^゚)゚。 」
「終身雇用制度や年功序列制度と、人事異動やリストラとの関係って何だろ~? ( ̄▽ ̄|||) 」
「終身雇用制度や年功序列制度と、人事制度との関係って何だろ~?成果主義や能力主義の人事制度とは何がどう違うんだろ~? ( ̄(工) ̄) 」
「終身雇用制度や年功序列制度と、経営計画や経営理念との関係って何だろ~?成果主義や能力主義の経営計画や経営理念とは何がどう違うんだろ~?差別化って観点から比較すると、どっちの方がいいんだろ~? ( ̄◇ ̄;) 」
などなど、このような声をお聞きすることもあるんですが・・・
( ´・ω・`)
んでもって・・・
「経営理念・ビジョン・経営計画等の作成」、「組織人事戦略(戦略的な組織づくり)」、「人材育成戦略(戦略的な人材育成)」、「経営に役立つ情報活用(IT活用・ICT活用)」などなどのお手伝いを行なっているからなのか・・・
「爆発・炎上・崩壊組織」で消防のお手伝いを行なうこともあるからなのか・・・
いろんな意味で、考えさせられるコトもあるんですけど・・・
ンーン (( ̄_ ̄*)(* ̄_ ̄)) ンーン
それに一見、全然関係ないように思えるかもしれないけど、コレってもしかしたら・・・










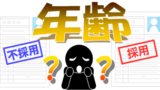




などなどにも、ある意味関係するっちゃーする面もあるのかも~???
なーんて感じるコトもあるので・・・
そもそもの話、終身雇用制度って、いったい何なんだろーか?
年功序列制度って、いったい何なんだろーか?
終身雇用制度と年功序列制度って、何がどう違うんだろーか?
どんな時には、終身雇用制度や年功序列制度が適しているんだろーか?
どんな時には、終身雇用制度や年功序列制度が適していないんだろーか?
それは誰がどんな基準でどう判断するんだろーか?
終身雇用制度や年功序列制度のメリットって、いったい何なんだろーか?
終身雇用制度や年功序列制度のデメリットって、いったい何なんだろーか?
それは、誰にとってのメリットやデメリットなんだろーか?
何のために、終身雇用制度や年功序列制度を採用するんだろーか?
誰のために、終身雇用制度や年功序列制度を採用するんだろーか?
終身雇用制度や年功序列制度、成果主義や能力主義などのいずれかを採用することって、目的なんだろーか?
それとも手段なんだろーか?
手段だとしたら、目的は何なんだろーか?
などなども含めて、一緒に考えてみません? (^^)
あ、モチロン、「自律的に」という意味で。
ちょっと興味あるかも~?
って言ってくださる方は、お付き合いいただけると嬉しいです。
(^^)/
終身雇用制度や年功序列制度のメリットやデメリットって?
(パート1)
んーと・・・
まずは、例えばこんなのから考えてみるのはどーでしょう?
d(⌒ー⌒)
終身雇用とは?(終身雇用制度とは?)
○ はてなキーワード
企業が正規に採用した社員を、特別な場合以外は解雇しないで定年まで雇用すること。
実際に定年まで雇用するという契約が存在する訳ではなく、慣行的なもの。
年功序列型賃金などとともに日本式経営の特色とされていた。
経営環境の変化により、年功序列賃金は多くの企業で見直されているが、終身雇用について企業側から見直す動きはないが、働く側には定年まで一企業で勤めあげようという意識が低下しているのが現状である。
○ m-Words
学校を卒業してから定年まで一つの企業に雇用されることを終身雇用という。
これは、年功制、企業別労働組合などとともに日本的経営の代表例として挙げられ、そのほかにも集団主義、福利厚生などが相互に絡んだ経営制度全体を終身雇用制度といい、契約に基づく雇用ではなく、終身雇用が暗黙の了解となっている制度である。
高度経済成長期においては企業への帰属意識を強く持った従業員が定着し、安心して仕事に打ち込み、なおかつ従業員の年齢構成が若く年功賃金により賃金コストが抑えられたこともあり、企業の生産性を高めた。
しかし、経済成長の鈍化に伴い、安定感はあるものの自主性に欠ける制度に安心して新たな発想を持った人材が育たないことや、過剰雇用による中高年齢層の増加で賃金コストが上昇したことなどのデメリットが強調されるようになり、制度自体が見直されるようになった。
それによって多様な雇用形態がより浸透したほか、賃金での実績主義を導入する企業が増加した。
○ exBuzzwords
終身雇用とは、正規の従業員(正社員)として採用された場合に、定年まで雇用関係を継続することである。
年功序列制度などと共に、旧日本的経営の特徴でもある。
終身雇用のもとでは、人材は社内で育成・調達をすることが前提となっている。
欧米諸国では、雇用条件については労働協約に明示されるが、日本では雇用保障については明示していない。
つまり、終身雇用制は明文化された雇用契約ではない。
長期間にわたる高度経済成長の中で、雇用の保証が実現し、それが慣行となって定着したものである。
バブル崩壊後、会社倒産やリストラ等によって、安定雇用は崩壊した。
近年の景気回復に伴い、多くの日本企業では中途採用に力を入れるようになった。
「雇用の流動化」が進むにつれ、終身雇用を守る企業は少なくなってきている。
○ Weblio辞書
正規の従業員(派遣社員や契約社員ではなく正社員)として採用された場合に、定年まで雇用関係を継続すること。
日本においては、欧米諸国のように雇用条件について労働協約に明示されている訳ではないが、経営上の大きな困難や従業員の大きな過失がない限り、労使とも雇用を継続することを前提としているという意味で、「暗黙の契約」といえる。
高度経済成長により長期間にわたる雇用保障が実現し、結果としてそれが慣行として定着したのである。
近年では、人材の流動性が高まり、日本企業の雇用の基本であった終身雇用は徐々に崩壊しつつある。
リストラにより職を失う人がいる一方で、高い能力を持つ人はヘッドハントされ、キャリアの途中で勤務先を変えることも珍しくなくなっている。
また、就職した企業に定年まで所属するのではなく、かなり早い段階から関連企業へ転籍する場合なども多くなっている。
長期間の単一企業継続という意味での終身雇用は、崩れつつあるのも事実である。
○ ウィキペディア
終身雇用とは、学校を新規に卒業した者がすぐに企業に就職し、同一企業で定年まで雇用され続けるという、日本の正社員雇用においての慣行である。
長期雇用慣行ともいう。
終身雇用制の成立を江戸時代以前の丁稚奉公制度に求める意見もあるが、現在のような長期雇用慣行の原型がつくられたのは大正末期から昭和初期にかけてだとされている。
1900年代から1910年代にかけて熟練工の転職率は極めて高く、より良い待遇を求めて職場を転々としており、当時の熟練工の5年以上の勤続者は1割程度であった。
企業側としては、熟練工の短期転職は大変なコストであり、大企業や官営工場が足止め策として定期昇給制度や退職金制度を導入し、年功序列を重視する雇用制度を築いたことに起源を持つ。
しかしこの時期の終身雇用制は、あくまで雇用者の善意にもとづく解雇権の留保であり、明文化された制度としてあったわけではないとされる。
その後第二次世界大戦終戦後、人員整理反対の大争議を経験した日本の大企業は高度経済成長時代には可能な限り指名解雇を避けるようになった。
その後50年代から60年代にかけては、神武景気、岩戸景気と呼ばれる好況のまっただなかにあり、多くの企業の関心は労働力不足のほうにあった。
そのため、この時期に特に大企業における長期雇用の慣習が一般化した。
1970年代に判例として成立した整理解雇4条件など、種々の判例や労働組合の団結により実質的に使用者の解雇権の行使も制限されるようになり、戦前まではあくまで慣行であった終身雇用が制度として人々の間に定着した。
1990年代から2000年代にかけて、多くの日本企業は円高や国際競争、平成不況の中で、人件費の圧迫と過剰雇用に直面し、雇用の調整が大きな経営課題となった。
これに対して、いったん雇った期間の定めのない従業員を解雇する際には、場合によっては解雇した従業員からの解雇権濫用による解雇無効訴訟のリスクを抱えてしまい、相当の覚悟を要する。
このような状況下での日本特有の雇用調整プロセスとして、正社員に対する残業の規制、配置転換や出向、早期退職制度やパートタイマー・期間工に対する契約更新中止、新規採用の中止などの方法が取られている
少子化、日本経済停滞などにより昨今では日本的経営の三種の神器(終身雇用、企業別労働組合、年功序列)を維持することは困難になってきている。
なお、「会社の寿命30年」(盛期という意味では今や「5年」とも)説も健在であり、それにのっとれば会社の寿命より一般的な労働人生の方が長いことになる。
企業側から見た長期雇用の利点は、長期的な展望に基づく企業内教育による人材育成への投資が行いやすいという点である。
また、教育訓練に対する従業員の意欲や、企業の忠誠心を高く維持することができる。
労働者側にとっても、雇用が長期間継続され収入が安定するという見込みは、生活の安定と心理的な安心感に貢献している。
住宅ローンのような長期的展望に基づいた生活を予測しやすいという利点もある。
しかし、この影響を受けるのは終身雇用に守られた正規労働者に限られる。
一方で、需要の低下した状態が長期に渡ると、労働保蔵は企業収支を圧迫し続ける。
終身雇用のもとでは人員整理や転職が難しく、経済の変化に伴う企業間・産業間の適正な労働力配置の妨げになるということが指摘されている。
企業にとっては、業績が悪化して労働力が余剰となった場合にも、終身雇用に守られた労働者の整理解雇は困難である。
労働者にとっても、他の企業による中途採用の機会が乏しく、また年功賃金による若い頃の「出資」を回収する必要性から、企業の業績が悪化したとしても途中で辞めることは非合理的な選択となる。
終身雇用は、正社員の長時間の残業の原因となっているという指摘がある。
なぜならば、終身雇用を前提とした雇用のシステムでは、不況期に余剰労働力の整理を行いにくいため、好況期の人手不足に対して、新規採用ではなく正社員の長時間労働で乗り切ることを迫るためである。
終身雇用を名目とした、正社員の長時間労働の要求に対して、労働者側が断わりにくい土壌があるのではないかと指摘されている。
年功序列とは?(年功序列制度とは?)
○ m-Words
勤続年数や年齢が増えるのに応じて賃金や役職や上がる制度のこと。
年長者を尊敬するという儒教的な考え方が日本に定着していることや、年齢を増し、経験を重ねることでスキルや能力が高まるという考え方があるために、日本では長く年功序列の制度が取り入れられてきた。
年功序列は、経済が成長を続け、人口が増え続けることが前提となって成立する制度であるため、1990年代に長く続いた不況が一因となり、崩壊しつつある。
年功序列は終身雇用制と並んで、日本での人事制度として長く採用されてきたが、労働者が残した成果に対して賃金を払うとする成果主義を取る企業も増えてきている。
○ コトバンク
勤続年数や年齢などの要素を重視して、組織内での役職や賃金を決める人事制度。
勤続年数や年齢が高くなれば、それだけスキルやノウハウが蓄積され、組織内における職務上の重要度が高まるとの考えから、それに応じて役職や賃金も上昇していく。
終身雇用制と合わせて、従業員の安定雇用や生活を保障し、日本経済の発展に寄与してきたが、最近は仕事の成果を重んじて役職や賃金を決める「成果主義」を導入する企業が増えつつある。
○ Weblio辞書
勤続年数や年齢によって、職場での地位や賃金が決まること。
待遇や地位を付与する折、あげた功績や出した成果を考慮せず、キャリアや年齢を判断材料とする事。
官公庁、企業などにおいて勤続年数、年齢などに応じて役職や賃金を上昇させる人事制度・慣習のことを指す。
終身雇用、企業別労働組合と並んで「三種の神器」と呼ばれ、日本型雇用の典型的なシステムである。
その他、個人の能力、実績に関わらず年数のみで評価する仕組み一般を年功序列と称することもある。
○ はてなキーワード
年上=偉い と錯覚させる日本に於ける悪習の一つ。
勤続年数や年齢が増すに従って役職や賃金が上がること。
また、そのような人事制度。
終身雇用とセットで、日本における雇用形態の特徴とされる。
ただし、この制度が維持できるのは経済が右肩上がりの成長を続け、労働力人口が増え続けることが前提となる。
また、近年同制度の崩壊により、成果主義を導入する企業が増えている。
○ ウィキペディア
年功序列制度は、加齢とともに労働者の技術や能力が蓄積され、最終的には企業の成績に反映されるとする考え方に基づいている。
結果として、経験豊富な者が管理職などのポストに就く割合が高くなる。
かつては、家族主義的な考え方や、家族の成長による生活費増加の保障など、社会学的な理由が強調されていた。
OJTなどによる企業の従業員への投資が転職によって失われないようにするなどと説明されることもあるが、若年者の働く意欲を殺ぎ生産性が失なわれているとの意見もある。
日本においてこのような制度が成立した理由としては、組織単位の作業が中心で成果主義を採用しにくかったこと、年少者は年長者に従うべきという儒教的な考え方が古代から強かったことが挙げられる。
集団で助け合って仕事をする場合は、個々人の成果を明確にすることが難しい場合も多く、組織を円滑に動かすには構成員が納得しやすい上下関係が求められる。
職能概念に基づく年功序列制度は、こういったニーズを満たす合理的な方法だったのである。
また、リスクの低い確実な選択肢を選ぼうとする国民性がこれに拍車を掛けることとなった。
年功序列の賃金体系のもとでは、実働部隊たる若年者層は、管理者である年長者層に比べ賃金が抑えられる傾向にある。
若年層のモチベーションの維持には、若年者もいずれ年功によって管理職に昇進し賃金が上昇する(若い頃には上げた成果に見合う賃金を受けられなくても、年功を積めば損を取り戻せる)という確証をもてる環境が必要であり、終身雇用制度は年功序列制度を補強する制度となっている
1990年代以降は成果主義を人事考課に取り入れる企業が増えており、人事上も年少者が上司となるケースも見受けられるようになりつつある。
しかし、成果主義における様々な問題等のため、2000年代以降に就職する若者は、年功序列型賃金と終身雇用という安定志向に回帰する傾向にある。
終身雇用制度や年功序列制度のメリットやデメリットって?
(パート2)
で・・・
次に、例えばこんなのからも考えてみるのはどーでしょう?
(⌒▽⌒)ノ
日本的な人事制度の中心は終身雇用制
■ 「日本の競争戦略」
日本的な人事制度の中心は、終身雇用制である。
終身雇用制は男性の正社員に対して、定年を迎えるまで職を保証した。
この企業側のコミットメントは、従業員と企業のインセンティブを合致させた。
終身雇用制の下では、短期的に従業員数の調節を行うことは困難となるが、米国にみられるような高い離職率、人材採用や解雇に伴うコスト、従業員の士気の低下等の不安定要素は減少した。
終身雇用制を維持することによって、業務に対する労働力が時として過剰に割り当てられていたとしても、そのコストは、従業員の企業への信頼と協力の増大による効率の向上によって、十分に相殺されると考えられた。
終身雇用制は、日本のマネジャーが社内における出世に努力することを促した。
日本企業の人事部門は、社内でも非常に高い位置を占めている。
また、全社的なローテーション制度は、ビジネスのあらゆる側面に精通したゼネラリストとしてのマネジャーを育成した。
日本のマネジャーは、キャリア形成の過程でさまざまなポジションに配置されることを承知しているため、欧米のマネジャーと比較して変化に対してはるかに抵抗がなく、企業に対する忠誠心も高い。
また、年功序列制度も、個人間の競争を緩和し、グループの連帯感を高め、長期的な業績でマネジャーを評価する等、企業の長期的業績の向上を目指すことを目的としている。
年功序列制度に基づく給与制度においては、若い従業員はその貢献度と比較して低い報酬しかな得ない傾向があるという事実は、特筆に値する。
終身雇用制は終わっていない
■ 「新・日本の経営」
日本の企業は社会組織、社員の共同体であり、共同体の全員が将来にわたって幸福に生活できるようにすることを目標にするとともに、十分な業績を達成しようと努力している。
合意に基づく意思決定、終身雇用制、年功制に基づく昇給と昇進、そして社員全員がひとつの労働組合に所属する企業内組合が日本的経営の柱である。
日本の企業は株主と経営者に報いることだけを目的とする経済組織ではない。
英米には企業はすべて株主のものだという奇妙な見方があるが、日本ではこの見方は通用しない。
日本企業では第一の利害関係者は会社に所属する人たち、社員なのだ。
日本企業は何よりも社会組織である。
企業を構成する人間が経営のシステムの中心に位置している。
会社ではたらく社員が利害関係者の中心である。
会社という共同体を構成しているのは、社員なのだ。
したがって、日本企業が社員との社会契約を守る姿勢を変えていないのは、驚くに値しない。
日本ではほとんどの国と違って、企業の生命がきわめて長い。
ここまで長寿の会社が多い事実は、日本の会社が家業でない場合にも、自己の存続を目的とする共同体であることを示している。
日本企業は売買の対象になる物理的な資産の集合体ではない。
社会組織なのであり、構成員の生活のために長く生き残ることを目標にしているのである。
「終身雇用制は終わった」とする主張は過去にもつねにあったし、いまもある。
だが、終身雇用制は終わっていない。
終身雇用制は当時もいまも、社会組織としての会社が構成員に対する義務をどこまで果たしているかを示すものである。
文化が企業の動きを左右していることに変わりはない。
日本経済が成功を収めたのは何よりも、日本の文化に基づいて経営システムを築き上げたことによるものだ。
この基盤から離れる動きをとる際には、リスクがきわめて高いことを覚悟しなければならない。
年功序列制について考えるとき、2つの点に留意しておくべきだろう。
第一に、どの社会でも昇進と昇給にあたって年功を考慮するのが一般的である。
年齢が高い人ほど地位が高くなる傾向がある。
若くして経営幹部になるのは、ほとんどどの国でも珍しいことなのだ。
そして平均賃金はすべての国で、20代前半から50代半ばまで上昇し、その後、引退の年齢まで低下している。
第二に、日本でも完全に年功序列の制度がとられてきたわけではない。
年齢とともに自動的に昇進して最後にはトップの地位につけるわけではなく、ほとんどの場合に、もっと早い時期に昇進が止まる仕組みになっていた。
そして、若くて地位が低い人が、組織を動かす力をもっている場合もあった。
賃金は年齢とともにあがっていくが、ほとんどの企業の賃金にはボーナスをはじめ、ある程度まで業績に左右される部分がある。
とはいえ、日本企業では年功と賃金の間のきわめて強い結びつきに変化があらわれている。
さまざまな調査にこの変化が示されており、管理職と一般社員の間で賃金の基準の違いが大きくなっている。
全体として、日本企業で年功序列制の重要性は急速に薄れている。
これは日本社会全体で長幼の序列が崩れてきたことによる動きであり、同時にこの傾向を強める動きでもあるように思える。
年功序列や終身雇用を否定するあまり生じた不安
■ 「職場いじめ ― あなたの上司はなぜキレる」
日本的な職場の特質を考える場合に、これまでの日本企業の良好なパフォーマンスを支えてきた年功序列型の賃金体系や終身雇用と、それを支える集団主義的な人間関係の変化を抜きにしては考えられない。
近年、こうした日本的労務管理の弊害が声高に言われるようになった。
その理由は色々とあるが、ひとことで言えば経営環境の変化にともない、これまでのやり方が通用しなくなったり、むしろ弊害をもたらすようなことが起こるようになってきたからである。
これまでは長所としてもてはやされてきたことが、逆に短所となりはじめてきているということである。
リストラが一段落した職場では、これまでの終身雇用や年功序列型のシステムの手直しと、成果主義のシステムの導入におおわらわといった状態である。
そうした急激な労務政策の転換が求められる一方で、このあまりにも急激な変化に対して、その性急さへの危惧や、先行きへの不安が職場にはくすぶり続けている。
その不安には、年功序列や終身雇用というシステムを否定するあまりに、それに代わるシステムの合意形成ができないまま突き進んでしまったという事情も加わっている。
成果主義は、あらかじめ終身雇用などに取って代わるシステムとして、ゆっくりと時間をかけて合意されてきたものではない。
現実には、終身雇用を否定してしまった後に、それに代わるシステムがなく、もはや選択の余地なく成果主義に走るしかなかったという事情がそこにはあるように見える。
いずれにせよ、こうした制度のやみくもな変更がもたらす不安が、職場での苛立ちの大きな要素となっていることは間違いない。
ブラック企業が悪用する「長時間労働をさせる権利」
■ 「ブラック企業 日本を食いつぶす妖怪」
日本の法律の不備を悪用して、違法ではない形で過労死するような長時間労働をさせる会社もある。
労働基準法では、1日8時間・週40時間を労働時間の上限とするように定められている。
ところが、労働基準法36条に基づく「36(サブロク)協定」という協定を労使で交わすと、この制限を取り払うことができる。
この「36協定」を通じて、過労死しそうな水準の長時間労働をも違法でなくしてしまう。
一応、「36協定」で延長してよい労働時間にも、上限時間が定められている。
しかし、この上限時間は法律上明記された義務ではないため、労使協定さえ結んでいれば比較的容易に受理される。
また、通常延長する労働時間のほかに「特別条項」を付け加えることによって、更に長い時間働かせることが可能となる。
厚生労働省の定める「過労死ライン」によると、月に80時間以上の残業をしていると生理的に必要な睡眠時間を確保することができないとされている。
しかし、このラインをオーバーする特別条項を結んだとしても、違法にはならないのが日本の法律なのである。
日本の大企業の大半でこうした長時間残業が導入され、さらに国家も事実上規制をかけていないという状況は、世界的にみれば異様な事態である。
だが、日本社会でこうしたことが認められてきた背景には、長時間残業と引き換えに、「終身雇用」と「年功賃金」という手厚い待遇が用意されていたからだ。
ところが、ブラック企業にそんな手厚い待遇が用意されているはずはない。
入社後も選別は続き、いつパワハラで自己都合退職に追い込まれるかもわからない。
ブラック企業はこうした日本型雇用に付随した「長時間労働をさせる権利」だけを悪用しているのだ。
「選別」や「使い捨て」を行うために、ブラック企業は「異常な命令」を行う。
「自分から辞めさせる」ためにパワーハラスメントが平然と行われ、健康を破壊するほどのノルマ、サービス残業が戦略的に課せられる。
だが、これらの多くは、実はブラック企業独自というよりも、日本型雇用から引き継がれ、「悪用」されているものだとみることができる。
そもそも、従来から日本の企業の「命令の権利」は諸外国から見て際立って強いものであった。
その理由は、日本型雇用においては、終身雇用と年功賃金と引き換えに、柔軟に命令を引き受けるという体質が身についていたからである。
例えば単身赴任という言葉は日本では一般的なものである。
当然、単身で何年もの長期間暮らすことは心身ともに大きな負担である。
だが、日本ではこうした一方的な命令を拒否することはできない。
また、残業にしても同じである。
日本の労働時間は、従来から諸外国に比して長いもので、「過労死」は世界語になってしまったほどであるが、残業命令に対して拒否することも極めて困難である。
だが、こうした厳しい指揮命令は、一方的に課せられてきたのではない。
実は、労働者側が長期雇用と引き換えに、積極的に受け入れてきた側面もある。
日本の雇用契約の場合には、長期雇用と引き換えに仕事の内容や命令のあり方にほとんど制約がかけられず、たいていのことが「人事権」として認められているところに特徴がある。
契約内容をあいまいにすればするほど業務命令の内容は柔軟に、雇用の継続は確実にされていく関係にあるとされる。
命令に制限が少なく、その分雇用が保障されるシステムは、非常に合理的に思えるかもしれない。
だが命令の契約内容に制限がない状態は、世界的にみてもかなり特殊であり、働く者には相当な負担がかかるシステムだといってよい。
これまでも日本企業の命令権は極めて強いものであり、それは時に耐えがたいものであったはずだ。
だが、多くの労働者がそれでもこれを「ブラック」などと感じずに甘受してきたのは、それだけの見返りがあったからに他ならない。
今日私たちが「ブラック」だと感じる理由は、ブラック企業は将来設計がたたない賃金で、私生活が崩壊するような長時間労働で、なおかつ「使い捨てる」からである。
逆に、仕事の内容がはっきりしている欧米型の場合には、解雇されやすい(と一般的に考えられている)代わりに、転職の際に自分のもつ専門性がはっきりしているので、他の企業からも評価されやすい。
その方が、日本のような「どんな命令がくるかわからない」状態よりも、よほど社会的な地位がはっきりしている。
終身雇用制は「贈与・互酬の関係」にもとづくもの
■ 「なぜ日本人はとりあえず謝るのか」
会社は一生の間で、日本人がもっとも長い時間を過ごすという意味で、とりわけ重要な場所であるといえる。
ある意味で日本のサラリーマンにとっては、家族よりも、「存在論的安心」を得ることができる場所である。
日本の会社は従業員に、終身雇用制や年功序列制、持ち家制度やさまざまな厚生施設などの保障だけでなく、非公式な人生相談をしたりすることができ、大きな家族に所属しているような安心感を与えている。
つまり会社は「存在論的安心」の基盤を与えているのである。
そして日本の会社では、この「存在論的安心」とひきかえに、強い非公式のルールに服することを要求される。
たとえば、新入社員研修では、会社への忠誠心をたたき込まれる。
また、家族抜きの単身赴任にも従わなければならない。
そうして若い労働者は「再 – 社会化」され、高度な自己抑制ができる労働者に育つ。
会社では、「共通の時間意識」が作動するため個人の範囲がはっきりしない。
個人の職務の範囲である「職務分掌」が不明確で、どこからどこまでが自分の仕事なのかがあいまいである。
そのために「世間」で期待される几帳面な性格の人間ほど、他人の仕事を余分に引き受けてしまい、これが過労死や過労自殺の原因となる。
また会社では個人が存在しないために、「権利」を主張するのが難しい。
たとえば日本の会社では、年次有給休暇を全部消化することは事実上できない。
それが労働者の「権利」であるにもかかわらず、である。
日本の伝統的な雇用関係である終身雇用制や年功序列制は、前者が会社の障害の生活保障をするから従業員は会社に忠誠をつくせよなという、「贈与・互酬の関係」にもとづくものだし、後者は、年齢の上昇によって給料を上げるという「身分制」にもとづくものである。
しかし現在、この日本的雇用関係が「強い個人」を前提とする成果主義の導入によって崩壊しつつあり、そのことが職場のうつ病の増加など病理現象をもたらしている。
「強い個人」はもともと社会の存在を前提としたものであって、日本の「世間」では存在しえないものであり、成果主義自体が「世間」にとっては無理難題というべきものなのだ。
終身雇用・年功序列は、外国人の社員を雇用すると矛盾が露呈する
■ 「(日本人)」
ほとんどの日本人は誤解しているが、アメリカ企業の能力主義は、利益を最大化するための仕組みではない。
それは、「能力以外で労働者を差別してはならない」というグローバル空間のルールのことだ。
アメリカでは、人種や宗教、性別や年齢で社員を差別することが許されない。
だから定年がないし、履歴書には生年月日を書く欄も、写真を貼る場所もない。
(写真を見れば性別や人種が一目瞭然だからだ)
もちろんだからといってすべての差別がなくなったわけではないが、ひとたび司法の場で差別と認定されると企業は巨額の賠償金を支払わなければならない。
だがこれは、社会に大きな難問を突きつけた。
あらゆる差別を禁じたとしても、採用や昇進の際に、企業はなにらかの仕方で労働者を選別しなければならないのだ。
そのため唯一残ったのが「能力」による評価だ。
これは能力が、人種や性別のような生得的なもの(どうしようもないもの)ではなく、本人の努力で”開発”が可能だとされたからだ。
日本企業の終身雇用・年功序列の人事制度は、年齢と性別によって社員を選別する仕組みだ。
この雇用慣行は日本というローカルな空間のなかでなら維持できるかもしれないが、企業が海外に進出したり、外国人の社員を雇用するようになるとたちまち矛盾が露呈する。
「なぜ日本人の社員と待遇が違うのか」
という外国人社員からの問いに、こたえることができないからだ。
日本型雇用はメンバーシップ型だから終身雇用
■ 企業は「ジョブ型正社員」を求めているのか?
日本型雇用はメンバーシップ型だ。
メンバーシップ型というのは、いわば家族の延長線だ。
だから、終身雇用だ。
途中でクビになることも、辞めることもない。
家族なのだから。
そうなると、当然、職に就くことよりも、その一員になることに重きが置かれる。
技能を持っていなくても家族にはなれる。
家族の生活の中で、自分の位置を見つけていく。
「就業時間外ですから行きません」と呑み会を断った新人は、そのファミリーであることがウザかったのだろうと思う。
家族でいることは、ある種の安心や安定ではあるけれど、うっとおしく、ウザいものでもある。
メンバーシップ型であることが、終身雇用を生み、新規学卒就職モデルを作り出した。
そして、そのモデルに軋みが生じている。
だが「ジョブ型にすれば解消する」という意見は安直すぎるのではないか。
日本型雇用のシステムが、現在の社会システムとそぐわなくなった点は多くある。
だからといってジョブ型にすれば解消するというのは、あまりにも思考停止だろう。
仕事をそこまで単純化して考えるからこそ、いまのアメリカの格差も生まれた。
失敗したら放り出す。
成功していない者は受け入れない。
能力のない者は排除する。
日本型雇用であれば、失敗しても、家族として守ってくれる。
それが悪い方向に進めば隠蔽や偽装のようなことになる。
良い方向に進めば、ファミリーとして仲良くやっていく協働の場として威力を発揮する。
どうして日本型雇用が日本に根付いたのか。
それがどう変節しているのか。
それを考えて、新しい道を見つけ出すべきだと思うのだ。
グローバル化という名目で欧米化に媚びるような道は、地域的な多様さを消し去る。
それが日本を幸せにするとは、とうてい思えないのだ。
「集団主義」から考える終身雇用制度・年功序列制度
■ もし「半沢直樹」がアメリカで放映されたら
アメリカはもともと「個人主義」の国である。
新大陸を開拓していくには個人が自分でリスクを取り、自分の人生を切り開いていく以外に道はなかった。
会社と従業員の関係は対等な契約であると見る。
その企業が気に入らなければ、とっとと辞めていく。
自分を生かしてくれる企業に転職し、そこで新たな人生を切り開こうとする。
米国では個人の幸福の追求が、集団での成功より上位の価値観に置かれる。
日本には「集団主義」の長い伝統があった。
組織に忠誠を誓い、波風を立てずに秩序だって行動することを求められた。
それが行き過ぎると戦前・戦中のように「組織のために命を捨てる」ところまで行く。
また、家族の犠牲も大きい。
戦後、民主主義国家になって大きく変わったが、我々の意識の中には古い価値観の片鱗が残っている。
日本の今の「閉塞感」はこうした諸要因が重なって起きているように思う。
会社というクローズドなシステムでは社員に逃げ場がない。
柔軟性を取り入れ、個人に選択の幅を認めるシステムに転換する必要があるように思う。
日本の会社組織がコミュニティとして発展してきた理由
■ 社員をつなぎ止める「新・日本型コミュニティ」を目指せ
日本をはじめとした東アジアの「コミュニティ」はそれとは様相が異なる。
人々は個々の意志で集まるというより、あまり選択肢のない中で、極端に言えば「仕方なく」集まった人々が、「ま、ここでやっていくしかないよな」という諦めのもと、集団規範に組み込まれて成り立っているのが東洋型コミュニティだ。
そこでは、個人のユニークな考えではなく、集団の持つ空気を読むことがより重要で、どのように集団に順応していくかがカギとなる。
個人が自発的に集まるコミュニティと、集団がその規範の中に個人を巻き込んでしまうコミュニティでは、そのメンバーのメンタリティや行動規範は自ずと違ってくる。
前者では、個人は自分が集団にいかに貢献できるかを考えるのに対し、後者では、個人は自分がいかに集団から利益を得られるかが重要になる。
だから、ますます強い集団規範が必要となる。
それが立ち行かなくなったのが、バブル崩壊後の日本組織だ。
そしてその直接的な理由は、年功序列、終身雇用といった「長期的関係」の組織をつくり上げる制度がなくなったことである。
先の集団規範も、メンバーが「他にいくところがないし、我慢していれば将来的には報われるので、今は集団に順応するしかない」という状態に置かれて、初めて機能するものだ。
しかし、これらの制度の崩壊によりその状態はなくなった。
後に残ったのは、日本型コミュニティの崩壊と「不機嫌な職場」だった。
かつての日本の会社組織がコミュニティとして発展してきた理由は、そのような制度に支えられた集団規範(しがらみ)であったことだ。
終身雇用制は、自社のことしか知らない人材を多数つくりだす
■ 右肩下がりの時代を生き抜く3つの方法
終身雇用制は、自社のことしか知らない人材を多数つくりだす。
こうした人たちが、自社でしか通用しない仕事のやり方を次々と生み出してきた。
日本企業があらゆることにおいて自社独自の仕様にこだわるのは、ここに原因がある。
また、日本の常識しか見えない人をつくることで、新興国のビジネスに乗り遅れてしまった。
独自仕様の追求はコスト高につながり、いまでは、頼りの国内ですら利益をあげることが難しくなってきている。
人事慣行に関していえば、日本は中国以上に共産主義的だ。
いま果たしている役割や貢献よりも、平等さや既得権の方が意味を持つ。
その結果、大きな失敗でもしない限り、いまのポジションに居続けることができる。
言い換えれば、誰もリスクを取ろうとはしなくなるのだ。
新しい環境に適応するために、リスクテイクがますます必要になっていく一方で、終身雇用制はそれを妨げる。
ガラパゴス的な終身雇用 ― 年功序列体制
■ 日本人の労働時間が長い原因は残業を「評価」する誤った精神論にある
わが国の労働慣行のほとんどが、実は、1940年体制とも呼ばれる戦後の高度成長期に確立されたものである。
そして、このガラパゴス的な終身雇用―年功序列体制の下では、ともすれば軍隊的な上意下達のシステムが出来上がり、ひたすら部下の忠誠心が試されることになりやすい。
いわば上司より先に帰ることが憚られるような空気が、自然に醸成されてしまうのである。
加えて、現行の法体系の下では、法定労働時間を超えた残業には割り増し賃金が支払われるので、「つきあい残業」には、インセンティブもまた働くことになってしまう。
これでは残業時間が長くなることは当然ではないか。
終身雇用なんてそもそも存在したのか?
■ 終身雇用なんてそもそも存在したのか?
現代の社会では終身雇用が崩壊した、と言われている。
まるで昔は終身雇用があったかのようだが、本当に終身雇用なんて存在したのか?
終身雇用ってのは、入社から定年まで何の心配もなく一つの会社で働けることだとする。
つまり、40年間安心して働けるってことだ。
入社時期を区切って考えてみる。
○ 1900年~1940年入社
社会人期間中に第二次大戦。
終身雇用どころじゃない。
○ 1950年入社
まだまだ戦後の混乱期で、いつ会社が無くなってもおかしくない。
終身雇用を信じて入社できる状況ではない。
○ 1960年~1980年入社
高度経済成長期もあり、終身雇用を信じて入社できた時代だと思う。
ただ、定年前にバブル崩壊でリストラの嵐が起きるから、結局終身雇用ではない。
○ 1990年以降入社
バブル崩壊、その後の不況で終身雇用どころじゃない。
こうして冷静に考えると、終身雇用なんてそもそも存在しなかったんじゃないか。
唯一60~80年入社の人は終身雇用を「信じる」ことはできたけど、結局崩壊した。
本当の終身雇用なんて存在しなかった。
「終身雇用制」は企業側の都合だった
■ 「やっぱり変だよ日本の営業」
早いか、遅いかの違いはありますが、死ぬまで一つの会社にいる人はあまりいません。
しかし、多くの企業は、基本的に社員が会社を辞めないことを前提に行われています。
業種や規模、社風などによっても違いますが、一般的に言えば今の若い日本人は、会社を辞めることに対して何の抵抗もありませんし、辞めることをむしろ前向きにとらえる人が増えました。
これからはこの傾向が加速するでしょう。
戦後、日本企業は長期間にわたって高度成長を謳歌してきました。
人手不足が社会問題になり、「人手不足倒産」まで起きました。
このために社員の確保が企業の経営課題の一つとなり、社員にずっと自社で働くことを期待し、奨励しました。
つまり、「終身雇用制」は企業側の都合だったのです。
日本人の集団心理をうまく利用し、一つの企業に尽くすことを美徳とし、会社を辞めることを裏切り行為と見なすようになりました。
これは、単に長く続くことで習慣化したものにすぎません。
それでも一昔前までは、終身雇用制は日本企業の文化だと言う人がたくさんいました。
しかし、バブル崩壊後やリーマンショックを経て、日本を代表するような企業でさえも大量のリストラを余儀なくされている現状を見た日本人は、自分たちの会社もすでに例外ではないことに気づいてしまいました。
企業のためではなく自分や家族のために働く感覚が、今の若い人たちはもちろん、中年の人たちにも広まっています。
一つの会社にずっといることを前提とせず、もっと自分の生き方に合う企業、もっとやりがいのある企業、もっと条件のよい企業に転職していくことが、自然なことになってきています。
しかし、実際に日本企業は社員が辞める前提で運用されているのか、そのような運用ノウハウと心構えがあるかというと疑わしいのが現状ではないでしょうか。
年功序列に従って昇進させていると、そこそこで満足してしまう
■ 「ゼロのちから」
年功序列に従って昇進させていると、中間層がそこそこで満足してしまう。
ほとんどの大企業では、上級職になるとあまり働かない。
彼らは「企業の踏み車」に乗って、ただ歩き続けているだけだ。
どこか目的地があるわけではないが、片方の足をもう一方の足の前に出していれば、そこから踏み外すことはない。
クビになるかと心配することもない。
経験と専門技術があれば大丈夫だと思い込んでいるのだ。
能力よりも勤続年数を重んじる企業では、若い管理職の多くはタイムカードを押すだけで卓越を目指そうとしない。
実際、リスクを取ってその成果で判断してもらえよりも、政治的に動いて昇進を助けてもらう方が得になる。
よい非営利組織は能力主義だ。
そのほとんどでは、リーダーが組織の中でいちばん活発で働き者だ。
頭脳明晰でも冷血で官僚的なリーダーは非営利組織にはほとんどいない。
私たちの血はすごく熱いのだ。
終身雇用と年功序列は本当に“悪習”なのか?
■ 終身雇用と年功序列は本当に“悪習”なのか?
人間は努力しているのに報われない状態が続くと、心身ともに疲弊していく。
自分の努力に対する対価の期待と、相手から受ける報酬のバランスが崩れた状態が続くと、それが慢性的なストレッサーとなり、働く人たちに冷たい雨を降らせ続けるのだ。
また、「他者からの尊敬」などの心理的報酬には、社内の上司からのねぎらいの言葉なども含まれる。
もともと村社会で生活していた日本人には、この他者からの心理的報酬によって承認を得たい欲求が強いとの指摘もある。
日本人は他人の目を気にする傾向が個人主義の欧米人に比べて強く、仲間たちに尊敬されることで、自分の価値を決める傾向が強いというのだ。
いずれにしても、年功序列という制度は、これらの3つの報酬を働いている人にもたらす制度だったと言えるのではないか。
現場で問題が起こったときや不測の事態が生じたときの対処には、経験が物を言うが、その「経験」も年功序列では評価できた。
決してパフォーマンスは高くはないし、数字につながるような結果や、目に見えるような成果を出せないけれども、その人がいることで、組織が回ることってある。
会社に評価されることはないし、昇進することも、給料が上がることもないけれども、その会社が好きで、そこの商品が好きで、お客さんのために、地道に働いている人たち。
陽の当たらない仕事を、頑なまでに真面目にやっている人たち。
そんな会社の土台を支えている人たちがいる。
パフォーマンスは決して高くないし、目立つこともない。
でも、会社が滞りなく回るための土台を支えている人たち。
そんな働き続ける力と経験という“目に見えない”力を評価できる唯一のものが、年功序列という制度にはあったと思うのだ。
家族的温情主義の土台になった終身雇用
■ 「フリーエージェント社会の到来 ― 「雇われない生き方」は何を変えるか」
第二次大戦後数十年間は、個人が会社に忠誠を誓い、会社が個人に安定を保障するという単純な取引が、個人と組織とをしっかり結びつけていた。
人々は会社に言われた通りに働き、会社の方針に疑問を差し挟むことはほとんどなく、転職することもめったになかった。
会社は事実上、終身雇用と安定した給料、それにある程度決まった額の企業年金を従業員に保障した。
こうした関係は、企業における家族的温情主義(パターナリズム)の土台になった。
決して従業員を解雇しないことを約束していたのだ。
どんなに業績が悪化しても、どんなに景気が落ち込んでも従業員の雇用は安全だった。
しかし90年代に入ると、カーテンを開けて窓の外に目を向け始めた。
家の外は、思った以上に厳しい世界になっていた。
グローバル化の進展により新しい市場が生まれると同時に、新たな競争相手が生まれた。
しかし、戦略的なミスや決断の遅い官僚的な体質など、様々な社内の問題のおかげで、変化への対応はますます後手に回った。
「会社はファミリーだ」という考え方は、よく言って時代遅れ、悪く言えば幻想に過ぎないということに気づいたのだ。
90年代の企業のリストラやレイオフ、そして終身雇用制の崩壊により、職場における忠誠心は弱まったと言われている。
しかしこれは、必ずしも事実とは言えない。
忠誠心はなくなっていない。
忠誠心のあり方が変わっただけだ。
個人が組織に示すタテの忠誠心に変わって、新しいヨコの忠誠心が生まれつつある。
取引先や同僚、元の同僚、チーム、職業、プロジェクト、業界に対する強い忠誠心が生まれている。
ある意味で、忠誠心は強化されたのだ。
年功制が基本の「実力主義」「成果主義」
■ 「社員が「よく辞める」会社は成長する!」
組織と個人の信頼を形成するうえで最大の障害になっているのは、両者の関係が虚構のうえに成り立っていることである。
つまり、終身雇用にしても将来の役職ポストにしても、会社がもはや保証できないにもかかわらず、期待を持たせるようなマネジメントを続けているところに問題がある。
少なくとも、その現実から目をそらそうとしてきたことの罪は重い。
どこの会社でも「実力主義」「成果主義」を謳うようになったが、よく見ると給与体系や昇進制度は依然として年功制が基本になっている。
せいぜい年功制という大きな枠の中で「実力主義」「成果主義」を取り入れようとしているにすぎない。
日本企業の「遅い昇進」が評価されたのは、定年までの雇用が保障され、まじめに努力していたらやがて地位も給料も上がっていくという暗黙の了解があったからだ。
その前提が崩れたら、会社が社員を裏切ることになる。
言葉は悪いが、会社が社員からの借金を踏み倒すようなものである。
給料だけではない。
現状では退職金や年金も、定年まで勤めなければ大きな損失を被るようになっている。
終身雇用をベースにして、あちこちつぎはぎを当てている現状
■ 「パラダイス鎖国」
企業の新陳代謝が進まない大きな要因のひとつが、昔ながらの雇用慣行である。
いま現在会社にいる人の職を守るために、本来なら撤退したほうがよい事業からなかなか撤退できない、企業統合が進まない、仕事を作るためだけの無駄な仕事が多い、といった弊害もある。
終身雇用に代わる効果的なシステムが確立されているとは、まだいいがたく、終身雇用への郷愁もいまだ強く、終身雇用をベースにして、昔ながらのシステムにあちこちつぎはぎを当てて使っているのが現状だ。
巷でいわれる「企業の寿命が30年」という定説に従えば、個人が一生同じ会社に勤められるほうが幸運である。
企業の寿命が限られているにも関わらず、その仕組みを維持しようとすれば、どこかに無理が出る。
終身雇用制度や年功序列制度のメリットやデメリットって?
(パート3)
うーむ・・・
どっ・・・、どーでしょう???
「そっ・・・、そーだったのかー! ガ━━(= ̄□ ̄=)━━ン!! 」
「だからかー!!だからだったのかー!! ヾ(.;.;゜Д゜)ノ 」
という方も、いらっしゃれば・・・
「ナルホド・・・、ちょっぴりわかった気がするかも・・・ ヽ(´ー`)ノ 」
「あ、なーんだー、そーだったんだ~ (〃▽〃) 」
という方も、いらっしゃれば・・・
「わかったよーなわからんよーな・・・ ( ̄д ̄;) 」
「やっぱ、頭がウニ状態じゃー!よくわからーん! \(  ̄曲 ̄)/ 」
という方も、いらっしゃるんじゃーないでしょうか?
他にも、例えば・・・


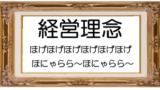




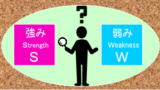







などなども含めると、いろんな意味で考えさせられちゃいません? (^^)
ふーむ・・・、こーやって考えてみると・・・
まだ見えていないだけで・・・
意外なところにヒントがいっぱい溢れている
おお~っ ━━━━ヽ(゜Д゜)ノ━━━━ 見っけ~♪
のかも~???
なーんて、感じません?
(〃▽〃)
どっ・・・、どうでしょう???
皆さまは、どう思われますか?





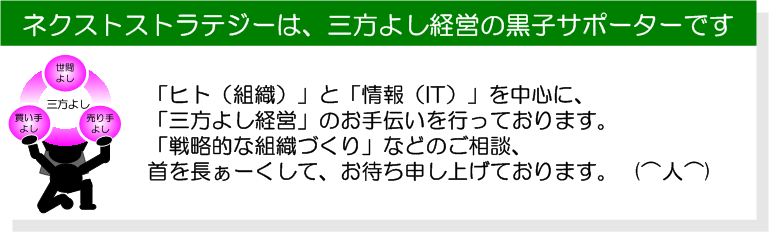
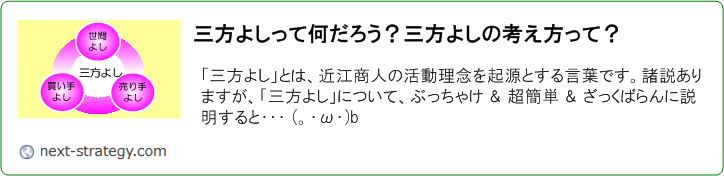

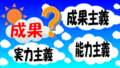
コメント