「帰納法って何だろ~?演繹法って何だろ~??? (;・∀・) 」
「帰納法と演繹法って何がどう違う?どっちの方がいいのかな~??? (・_・;) 」
「帰納法のメリットやデメリットって、何があるんだろ~??? (;゜∇゜) 」
「演繹法のメリットやデメリットって、何かあるのかな~??? (´ε`;) 」
「帰納法の方が問題を解決しやすいのかな~??? (; ̄ェ ̄) 」
「演繹法の方が問題解決力が向上するのかな??? ( ̄‥ ̄;) 」
「人材育成を行う時って、帰納法の方がいいのかな~??? (|||▽ ) 」
「それとも演繹法の方がいいのかな~??? ( ̄∧ ̄ ) 」
などなど、このような声をお聞きすることもあるんですが・・・
(`・ω・´)
んでもって・・・
「三方よしの経営相談」、「自律型人材育成」、「組織力の強化や向上」、「経営に役立つ情報活用(IT活用・ICT活用)」などのお手伝いを行なっているからなのか・・・
「爆発・炎上・崩壊組織」で消防のお手伝いを行なうこともあるからなのか・・・
いろんな意味で、考えさせられるコトもあるんですけど・・・
ンーン (( ̄_ ̄)( ̄_ ̄)) ンーン
コレってもしかしたら・・・










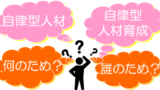
などなどにも、ある意味関係するっちゃーする面もあるのかも~???
なーんて、感じるコトもあるので・・・
帰納法って何だろーか?
演繹法って何だろーか?
帰納法と演繹法って、何がどう違うんだろーか?
どんな時には帰納法が適していて、どんな時には適していないんだろーか?
どんな時には演繹法が適していて、どんな時には適していないんだろーか?
帰納法のメリットやデメリットって何だろーか?
演繹法のメリットやデメリットって何だろーか?
それは誰にとってのメリットやデメリットなんだろーか?
などなども含めて、一緒に考えてみません? (^^)
あ、モチロン、「自律的に」という意味で。
ちょっと興味あるかも~?
って言ってくださる方は、お付き合いいただけると嬉しいです。
(^^)/
帰納法と演繹法の違いとは?問題解決との関係って?(パート1)
んーと、もしかしたら・・・







なんかにもある意味関係するかもしれないので・・・
例えばこんなのから、まずは考えてみるのはどーでしょう?
(。・ω・。)ノ
帰納法とは?
○ コトバンク
類似の事例をもとにして、一般的法則や原理を導き出す推論法のこと。
帰納的推論ともよばれる。
多くの特殊的な事実から蓋然的に真の一般的な原理、法則を発見する研究方法。
結論の蓋然的命題は、「自然の斉一性」を仮定することで普遍的法則とみなされ因果関係が確定される。
例えば、次のような推論が帰納法に当てはまる。
(a)このカラスは黒い(事例1)
(b)そのカラスも黒い(事例2)
(c)あのカラスも黒い(事例3)
(d)ゆえに、カラスは黒い(法則)
ここでは3つの事例(a)(b)(c)について言えることを一般化して(d)の法則を導き出している。
ただし、この法則はありうる事例をすべて調べて導き出したものではないため、例えば「白いカラス」といった、法則の例外が出てくる可能性は十分にある。
それゆえ、帰納法で得られる法則は必ず正しいというものではなく、ある程度確かであるというに留まる。
蓋然性とは?
○ goo辞書
蓋然性(がいぜんせい)とは、ある事柄が起こる確実性や、ある事柄が真実として認められる確実性の度合い。
確からしさ。
これを数量化したものが確率。
○ コトバンク
元来は「確からしさ」を意味する。
「必然」に対応し、事物の生起やその知識の確からしさの度合いをいう。
それらの生起や知識そのものについては必然的で、偶然の入る余地はないが、必然的な因果関係やそれに付随する条件が未知の場合、その確からしさの度合いは、偶然的ともいえる。
そこから蓋然性を可能性と偶然性のからみ合ったものということもできる。
蓋然性を経験的に法則化することもでき、数量的に表わされるときは確率という。
自然の斉一性とは?
○ ウィキペディア
自然の斉一性原理または単に斉一性原理とは、科学哲学の世界で用いられる言葉で「自然界で起きる出来事は全くデタラメに生起するわけではなく、何らかの秩序があり、同じような条件のもとでは、同じ現象がくりかえされるはずだ」という仮定。
例えば次のような推論を考えて欲しい。
前提1. 二日前、あの東の山の間から、太陽が昇ってきた
前提2. 昨日、あの東の山の間から、太陽が昇ってきた
前提3. 今日、あの東の山の間から、太陽が昇ってきた
結論. よって明日は、西から、スイカが昇る
この推論はおかしいと思うだろう。
今までずっと東だったのが、なぜ突然に西になるのか、そして今までずっと太陽が昇ってきたのに、なぜ突然スイカが昇ってくるのか、と思うだろう。
ここであなたが「この推論はおかしい」と考える上で前提としている考えこそが自然の斉一性である。
つまり、今までこうだったのならば、これからも今までと同じような形で、自然は振舞っていくはずだ、という仮定のことである。
演繹法とは?
○ コトバンク
前提となる事柄をもとに、そこから確実に言える結論を導き出す推論法のこと。
演繹による推理の手続き。
代表的なものに三段論法がある。
演繹法では、前提となる事柄がすべて正しいと認められれば、そこから必ず正しい結論を導き出すことができる。
三段論法とは?
○ コトバンク
文章を大前提、小前提、結論の順に組み立てて推論する方法。
例えば、
「人間は死ぬ」(大前提)
「ソクラテスは人間である」(小前提)
故に「ソクラテスは死ぬ」(結論)
の類。
帰納法と演繹法の違いとは?問題解決との関係って?(パート2)
んでー、次に、例えばこんなのからも・・・
帰納法の考え方が適していたり、役に立ったりするのはどんな時なんだろーか?
演繹法の考え方が適していたり、役に立ったりするのはどんな時なんだろーか?
帰納法の考え方も演繹法の考え方も、どちらも適していたり、役に立ったりするのはどんな時なんだろーか?
帰納法の考え方も演繹法の考え方も適さなかったり、役に立たなかったりするのはどんな時なんだろーか?
帰納法と演繹法のそれぞれのメリットやデメリットって何だろーか?
それは誰にとってのメリットやデメリットなんだろーか?
などなどについて考えてみるのはどーでしょう?
o(*⌒O⌒)b
- 論文を書く時
- 企画書を書く時
- 提案書を書く時
- 反省文を書く時
- 履歴書を書く時
- 職務経歴書を書く時
- 自己PRを考える時
- 志望動機を考える時
- 試験の問題を作成する時
- 試験の問題を解く時
- 試験の採点を行う時
- 試験の問題でなぜ間違えたのか、なぜ正解できたのか原因を考える時
- 日報を作成する時
- 報告書を作成する時
- 決算書を作成する時
- 会社のホームページを作成する時
- 会社案内のパンフレットを作成する時
- チラシを作成する時
- 社内報を作成する時
- 就業規則を作成する時
- 仕様書を作成する時
- マニュアルを作成する時
- 契約書を作成する時
- 助成金や補助金の申請書を作成する時
- 新製品や新サービスを考える時
- マーケティングを行う時
- 顧客ニーズやウォンツを把握する時
- パソコントラブルの原因を探る時
- 不良品が発生した原因を探る時
- 売上や利益が上がらない原因を探る時
- ノルマが達成できていない原因を探る時
- 生産性が向上しない原因を探る時
- 残業が減らない原因を探る時
- 改革が上手く行かない原因を探る時
- 人材育成の効果が出ない原因を探る時
- 人手不足の原因を探る時
- 属人化の原因を探る時
- モチベーションが向上しない原因を探る時
- マニュアル人間や指示待ち人間になってしまっている原因を探る時
- 優秀な人材が辞めてしまう原因を探る時
- 優秀な人材が見つからない原因を探る時
- 部分最適と全体最適の違いについて考える時
- 自社にどのような人材が必要なのか考える時
- 自社にどのような組織が必要なのか考える時
- 自社にどのようなIT(ICT)が必要なのか考える時
- 人材育成について考える時
- 社長や上司の指示通りに動く人材を育成したい時
- 協調性のある人材を育成したい時
- 主体性のある人材を育成したい時
- チャレンジ精神のある人材を育成したい時
- 問題解決力のある人材を育成したい時
- 自律型人材育成を行いたい時
帰納法と演繹法の違いとは?問題解決との関係って?(パート3)
んでもって・・・
例えばこんなのからも考えてみるのはどーでしょう?
(。・ω・)b
論理思考を行う際に忘れてはならないこと
■ 「論理思考の「壁」を破る」
「きちんと説明したのに、どうしてあんな返事が戻ってくるんだ」
「あれほど考えたことなのに、どうして話がうまく進まないんだ」
「どう考えても正しいんだから、早く納得してくれよ」
解決しなければならない問題について、相手にとっても自分にとっても正しくなるよう論理的に考え抜いて結論を出した。
しかしそれが相手に受け入れられず、結果としてWin-WinならぬLose-Loseになってしまった。
上司に何かを訴えかける場面でも、部下に何かを指示する場面でも、顧客に何かを提案する場面でも、配偶者や恋人に何かを頼む場面でもいい。
その際に、図らずもこうした結果になったことはないだろうか。
論理思考を行う際に忘れてはならないことがある。
それは、仮説思考によって出た結論はあくまでも「行動する」ための結論であり、問題解決のためには常に行動と結果、それに基づくフィードバックが伴わなくてはならないということだ。
すなわち、問題解決策を見出した後、行動に移る際に周囲の人間と問題意識や考え方を共有し、自分が先頭に立ったり、目上の人に提案したりバックアップしたり、あるいは第三者としてアドバイスしたりするなど、さまざまな形で問題解決へ向けて周囲を巻き込んでいくノウハウが必要なのだ。
言い換えれば、論理思考はけっして万能薬ではなく、それさえマスターすれば問題が解決できるわけではない。
頭の中にロジックツリーが描けた段階では、まだ問題解決のスタートラインに立っただけだ。
その結論を頭に留めて、問題解決に向けて主体となるべき人物たちの顔を思い浮かべ、議論の進捗状況から当事者間の共有度合いや理解度、相手の思考パターン、志向性、感情なども含めて状況を分析し、それに合わせた論理構成を組んでコミュニケーションをとることで、ようやくスタートラインから前に動き出すことができるのである。
しかし、ここで「壁」に当たることが多い。
相手が自分とは異なるロジックを持っている場合や、いままで是とされていたロジックとは異なるロジックが結論となった場合である。
さらには、相手の立場や過去の経緯から考えて、相手にとっては
「頭ではわかっても心がついてこない。そもそも、わかりたくない」
ような結論が出てくる場合である。
こうした場面では、話しにくい相手に話しにくいことを伝えて理解してもらい、納得してもらわなければならない。
初めて取り組む課題にぶつかったとき、だれしもすぐに解決方法を考えつくわけではない。
考え込むところから始まるのはすべての人に共通したことだ。
「いいかげん」な答えは客観性に乏しく、Why?とSo What?の繰り返しに弱い。
一方で、確かな答えはWhy?とSo What?に強い。
問題から結論に至るまでのストーリーが正しいロジックで成り立っているからだ。
「論理的に考える」ということは、目の前にある情報・ファクトの材料から、客観的に確からしい仮説を立て、それを確認していくという、一連のプロセスを何回も重ねることである。
そして、正しい論理でつながっているストーリーができあがるのだ。
仮説思考とは、いったん立てた仮説に対してWhy?(なぜ?)とSo What?(だから何だ?)を繰り返して、入手可能な情報・ファクトから確からしい結論を考え出すことである。
そのプロセスのうち仮説を確認し、より確からしく内容をブラッシュアップする糸口を引き出すのが「検証分析」である。
仮説思考に失敗する原因としてよく見られるのが、検証分析が杜撰(ずさん)であるために結論をより確からしくするきっかけを失い、思考が深まっていないことだ。
問題解決の前に考えておかなければならないこと
■ 「90分で学べるIT提案力」
問題解決のための技法は、よく話題になることがあります。
さまざまな技法が存在し、実務でよく利用されているものもあります。
しかし、問題解決の前に私たちは大切なことを考えておかなければなりません。
それは、解決したい問題は、そもそもどのようにして見つけたらよいかということです。
これが意外に難しいのです。
最も重要なことは「現状などいくら見ていても、現状だけを見ていたのでは問題点は見えてこない」ということです。
現状はただの事実であって、それだけでは良いも悪いもないのです。
問題を解決するには、まず「問題」がわかっていなければならない
■ 「なぜ危機に気づけなかったのか」
問題を解決するには、まず「問題」がわかっていなければならない。
企業をはじめ、多くの組織において問題は隠れてしまい、いくら問題解決法を知っていても「解決すべき問題」が何か、わかっていないことが問題になっている。
問題が起こり、大事故・大惨事に発展してから解決策を見出すより、問題になりそうなことを早くに発見し、まだ軽微なうちに手を打つことのほうが価値がある。
しかし、手遅れになってからやっと危機に気づいたり、見当違いの問題を解決しようとしている場合さえある。
真の問題を見極めることが最も難しい課題である。
問題があることが問題なのではない
■ 「なぜ社員はやる気をなくしているのか」
本当は問題があるのだが、誰も気づいていないために解決されない、ということはよくあることだ。
「問題の芽」は多くの場合、隠れたままで、外からは気づかれないような状況になっていることが多い。
ということは、問題を解決し、改善しようと思えば、
「問題は何か」
「問題はどこにあるのか」
がわかっていなくてはならない。
問題がまだ起きていない段階で、その芽を見つけるのも大事なことだが、いつもそれができるとはかぎらない。
つまり、問題が起きることで、ようやくその問題に気づく、というのはよくあることなのだ。
注目すべきは、こうした大きな問題が出てくる前に、ほとんどの場合その前兆である小さな問題が顔を見せている、ということだ。
小さな問題を無視し続けていると、それらの小さな問題は内部で発酵しながら増殖し、身体が弱ったときに発病する。
大きな問題が「起きて」しまうのだ。
問題があること自体を問題と考えてはいけない。
どんな組織にも問題はあるのだから。
問題があることが問題なのではない。
問題が見えてくること自体はきわめて望ましいことなのだ。
問題解決の手法を学ぶことが効果的?
■ 「経営者の手帳」
「問題解決の手法を学ぶことが効果的」
といったことを、まことしやかに論ずる人は多いものの、現状を理解し、あるべき姿(理想)を示したなかでの問題論を語る人は意外に少ない。
あるべき姿と現状をとらえていない問題論は、それこそが最大の問題なのだ。
まず与えられた問題を疑うことから始めるべき
■ 「論点思考」
学校の勉強であれば、試験の出題者の出した問題を解けばいいので、どちらかといえば正しい解き方、あるいは効率的な問題の解き方が教育の中心になっている。
ましてや国語の問題に数学の問題が紛れ込むことや、「この中には解くべき問題と解いてもしょうがない問題が混ざっているので自分で判断しなさい」なんてことは絶対にない。
ところが、ビジネスの世界では誰も「あなたが解くべき問題はこれである」と教えてくれない。
一般のビジネスパーソンの場合は、どうしても上から与えられた問題を鵜呑みにしがちである。
なにか命令を受けたときには、まず与えられた問題を疑うことから始めるべきだ。
問いの設定が正しく行なわれていれば、成功は半ば保証されたようなものである。
逆に問いの設定が間違っていれば、その後の戦略の策定・実行をいくら精緻華麗に行なったとしても、もともと方向性が間違っているのだからよい結果につながるはずがない。
例えば売上不振に陥っている会社の社長が、
「我が社の課題は売上不振だから、この問題をなんとかしよう」
といったとしよう。
あなたはどんな手を打つだろうか。
対症療法は、一時的なカンフル剤としては効果をあげるかもしれないが、結局長続きしない。
なぜなら、売上不振は現象にすぎない。
売上不振をもたらしている真の原因、すなわち論点は別にある。
「自分の頭で考える」ということ
■ 「本質を見抜く「考え方」」
世の中のさまざまな言い分、見解、判断などといったものに接して、
「誰の言っていることももっともに聞こえる」
「みんなそれぞれに立派な理屈がありそうだ」
などと感じて、いったいどの結論が正しいのか、わからなくなってしまう・・・。
そんな経験はないでしょうか。
これは恥ずかしいことでも珍しいことでもありません。
むしろ、何ものにもとらわれない素直な考え方をしていたら、多くの場合、こうした疑問にとらわれて当たり前なのです。
正しいものの見方や考え方というのは、できるだけいろいろな立場や視点からものごとに光を当て、曇った眼鏡や色眼鏡、歪んだレンズでものごとを見ないようにすることから始まるということです。
そのために何が大切か、誰の目にも明らかなのは、すでにできあがっている他人の考え方に染まらないで、「自分の頭で考える」ということです。
一見もっともらしく見える他人の判断や見解を、そのまま自分の頭に採り入れるということは、もしかしたらとんだ色眼鏡や歪んだレンズに、自分の頭を支配されかねないということです。
「権威」に対して強くなれば、「疑う力」は向上する
■ 「疑う力」
人は情報が少なく、自分で検証が難しい問題について、「権威」の言うことを信じたがります。
人が無条件に信じてしまう「権威」には、「警察官」「医者」「大学教授」「人気タレント」などがあります。
これら「権威」の言うことを、多くの人は無条件に信じます。
ステレオタイプな権威への妄信が、「疑う力」を停止させ、思考停止に陥らせる一つの原因です。
逆に言えば「権威」に対して強くなれば、「疑う力」は向上します。
たとえば国が発表したからといって、正しいとは限らないと考えるなど、つねにそういう思考の癖を身につけておくのです。
ナチの教育は、金太郎飴的な人間を再生産すること
■ 「ヒトラーに抵抗した人々 – 反ナチ市民の勇気とは何か」
彼ら反ナチ主義を掲げて戦った、「普通の人々」の勇気とはなんだったのか、そして、彼らはどんなふうにあの時代を生きたのか。
それは決して、あの時代特有のことではない。
彼らの活動にいまも学ぶことがあるはず。
ナチの教育を一言で言えば、金太郎飴的な人間、つまり没個性の人間を再生産すること。
国民の大多数は、ヒトラーの経済政策に大きな期待を寄せ、彼を支持した。
つまりあれは、「国民の同意による独裁」だったということを忘れてはいけません。
単なるイデオロギーで、国民大衆が12年間もの間、非道な独裁者に対して万歳するなんてありえないのです。
統治の手法として、そこには「ニンジン」が必要で、それは人間の本性を突いているとも言えます。
ヒトラーは、そういうものを巧みに操作し、徹底的な利をもって国民を操ったのです。
一方、処刑された教育学者は知識の詰め込みに熱心な教育者ではありませんでした。
彼が目指したものとは、狭い村社会を超えた、開かれた世界を子どもたちと共有し、自分で考えることができる人間、すなわち、主体的自己を育むことです。
あの混沌とした時代の技術社会で人間が生きていくためには、何よりも自律的で、自分をよく知る人間であることが重要なのだ、と言ったのです。
彼のこのメソッドは、いまのドイツの教育にも受け継がれています。
日本の教育は、あまりにも暗記中心
■ 日本とドイツ、学習方法に見る隔たり
日本の公立中学校に少しずつ慣れ始めた我が娘。
帰国子女ならではのいろいろな試練が降り掛かってきます。
例えば日本の学習方法。
あまりにも暗記中心なのです。
日本の教育現場では、たとえその事柄を理解していなくとも、“とにかく覚えること”が求められているようでした。
考えること、興味のあることを追究すること、自分の意見を述べること・・・・・・
そういう訓練はドイツでたくさんしてきたのですが、記憶力を鍛えるトレーニングは初めてです。
ドイツの先生は言います。
「疑問がないと答えは出てこないんだよ」と。
なるほど、疑問を持つことは学問の始まりかもしれません。
1つの現象や物事をどう見るか、質問の立て方によっていろいろな答えが導き出せる。
世の中の考え方やものの見方は当然1つではない。
こんなドイツの授業風景が、日本に戻ってからは何度も懐かしく思い出されるのでした。
なぜ日本人は世界で通用しないのか
■ なぜ日本人は世界で通用しないのか
日本の入試は中学から大学まで、答えは1つであるという前提でつくられています。
それに合わせて学校でも、答えがある問題を出して、その解き方を教えています。
そういった教育を通して「答えは1つ」と植えつけられているから、答えが出ない現実の問題に対応できない面があるのではないかと。
フランスの高校卒業試験であるバカロレアでは去年、「あなたは自由と平等、どちらが大切だと思いますか」という問題が出ました。
これはどちらを選んでもよくて、なぜ自分はそう考えたのかを論理的に説明することが求められるわけです。
日本人とフランス人のハーフの友人がフランスに転校になり、日本で解いたことのある問題がテストで出たそうです。
彼女は日本で習った通りの答えを書いたのですが、結果は0点。
彼女の母親が「うちの娘は正しいことを書いている」と抗議にいくと、先生は
「この解答には彼女の考え方がまったく入っていない」
「これでは世界に対する彼女の付加価値がゼロだ」
と説明しました。
残念ながら日本の場合は、先生が1番偉くて、生徒は知識を一方的に与えられる人になっています。
先進国に追いつく過程においてはそうした教育も効果的でしたが、日本は1990年代前半にアメリカに追いついてしまった。
知識を与えられるだけの教育では、その瞬間に、誰も絵を描けなくなってしまう。
それが「失われた20年間」につながったのかなと。
背景には1人だけ違う意見を持つことを許さない日本の企業文化があると思います。
上の意見に逆らうことができない状態じゃいい発想も出てこないし、仕事へのモチベーションも上がらないでしょう。
アメリカでは、自分の考え方と合わないと思えば転職します。
日本のように我慢しない。
ということは、日本では多くの人が自分の考えを諦めているわけです。
採用にも問題があると思います。
企業は、上の意見に服従してくれる人のほうが都合がいい。
だから「答えはいくつもある」なんて難しいことを言う人より、自分たちのカルチャーに染められるように、「とにかく頑張ります」と言う人を積極的に採ってきました。
小中学校のときから「答えはいくつもある」という教育をしていって、彼らが社会に出たときに化学反応が起きれば、新しい日本というものが見えてくるはずです。
問題解決への道
■ 問題の名称をわかりやすく変更しよう!
世の中で「問題だ! 問題だ!」と言われてても、何が問題なのかぜんぜん分からないコトが多いんだよね。
たとえば、
東京一極集中が問題だ!
って、何が問題なの?
限界集落が問題だ!
ってのも、何が問題なのかな。
地方の自治体の多くが消滅するのが問題だ!
コレも何が問題なのかよくわかんない。
少子化が問題だ!
WHY ?
問題って、もうちょっと本質がよくわかるような名称で呼んだほうがいいと思うんだよね。
大事なことは、
- 問題を問題と認識し
- 問題を解決するためにはなにをすればいいのか
という方向で思考することです。
問題を「仕方のないこと」「我慢しよう」と考えてしまい、「できない理由」ばかり声高に叫ぶ人が増えてしまうと、世の中は進歩しない。
面倒なこと、理不尽なこと、大変すぎることに関しては、「これってちょっと変じゃね?」って声に出していいましょう。
そして可能なら、個人としてどんどんそれらを避けましょう。
ひとりひとりがそうすることで、問題解決への道が拓けるのです。
「論理力」とは、ごく単純なもの
■ 「図解 フィンランド・メソッド入門」
「どうして?」
フィンランドの小学校で、いちばんよく聞く言葉がこれです。
生徒が発言すると、先生が即座に「どうして?」と聞くのです。
生徒が何か意見を言えば、「どうして、そう思ったの?」
生徒が何か感想を言えば、「どうして、そう感じたの?」
私が3年生の文法の補習授業に参加したときのことです。
先生は単語をひとつずつ挙げ、その品詞が何であるかを生徒に質問していきます。
「机の品詞は何?」
「名詞です」
「どうして?」
「ええっと、『ぼくが机します』とは言わないし、それに・・・・」
授業のあと、私は先生に質問しました。
「どうして正解の生徒にも『どうして?』とたずねるのですか?」
すると先生は次のように答えたのです。
「品詞の性質を完全に説明できるかどうかは、それほど重要ではありません」
「『どうして?』と聞くことによって、なぜ自分がそのように答えたのか、改めて考える機会を与えることが重要なのです」
「放っておくと、生徒は短絡的な思いつきを、ただ反射的に答えるだけになってしまいますからね」
容赦なく「どうして?」とたずねられては、生徒たちは自分の発言を常に客観的に見直さざるをえません。
こうして、論理力、さらには批判的思考力が育っていくのです。
論理力というと、われわれは難しいものを想像しがちです。
「論理」という言葉が、いかにも堅苦しく響くのかもしれません。
しかし、ここでいう「論理力」とは、ごく単純なものです。
何か意見を言ったら、必ず「どうして、そう思ったのか」を言う。
何か感想を言ったら、必ず「どうして、そう感じたのか」を言う。
ただそれだけのことなのです。
フィンランドの小学生ができることなのだから、日本の小学生にできないわけがありません。
ましてや、大人であれば、簡単にできるはずのことなのです。
しかし、現状をみるかぎり、この簡単なことを日本人はなかなかできていません。
言葉で説明しなくても分かり合えるところが多いというのは、日本の文化の美徳なのでしょう。
何も説明しないでも分かり合えるのならば、それがいちばんいいのです。
問題なのは、いちいち説明しなければ分かり合えない場合です。
そういう状況では、何か意見を言ったら、「どうして、そう思ったのか」を説明しなければ通用しない。
何か感想を言ったら、「どうして、そう感じたのか」を説明しなければ分かってもらえないのです。
フィンランドの先生が「どうして?」攻撃をしかけるのも、生徒の頭の中に、この論理の回路をつくるためといえるでしょう。
われわれの頭の中に論理の回路があろうとなかろうと、日本国内では充分に活躍できるに違いありません。
しかし、論理の回路がないまま、日本から一歩でも外に出てしまえば、ほとんど通用しないでしょう。
その能力が欠けているかぎり、どんなに英語が上手でも国際的には通用しません。
それは、相手がどこのだれであろうと、自分の言いたいことを理解させる能力、そして、相手がどこのだれであろうと、その言うことを理解する能力です。
多くの国では、この能力を小学校から国語の授業で段階的に教育しています。
しかし、残念ながら日本では、この能力を身につけるような教育はされていません。
誤解のないように言っておきますが、日本人のコミュニケーション力が劣っているといっているのではありません。
むしろ、世界的にみても、日本人ほどコミュニケーションに細かい心配りをしている人々はいないと思います。
ただし、そのコミュニケーション力は、相手が日本人の場合にしか通用しません。
日本人同士ならば、いちいち説明しなくても分かり合える部分が多いからです。
しかし、世界には、さまざまな人々がいます。
そのほとんどは、日本人にとって当たり前のことであっても、いちいち説明しなければ分かってくれません。
人間がしかるべき比較優位を維持できるものは何だろうか
■ 「機械との競争」
コンピュータは、パターン認識や複雑なコミュニケーションなど、これまで人間が独占してきた領域を侵食しつつある。
たとえばカスタマーサービス係に代わってバーチャルアシスタントが導入され、売店やスーパーマーケットではセルフレジが普及してレジ係の需要が減りつつある。
いまやiPodから水着、金貨、サングラス、カミソリまで自動販売機で買える時代だ。
また商品情報は、店員に聞かなくても店に備えられたタッチスクリーンで入手できる。
自販機のコストは、実店舗と比べたら微々たるものだ。
こうした動きは、消費者の購買習慣を反映したものとも言える。
インターネット通販の浸透に伴い、セールスマンや店員がいないところでモノを買うことにすっかり違和感がなくなっている。
パターン認識も複雑なコミュニケーションもいまや自動化が可能だとなれば、人間の能力でコンピュータに脅かされないものは、何があるのだろうか。
人間がしかるべき比較優位を維持できるものは何だろうか。
企業経営における人材育成の意味とは何だろうか?
■ 「研修開発入門」
「教えること」というのは、昨今、「教え込み」という言葉でイメージされるように、どちらかというと忌避されるような傾向があるように思います。
そもそも、「教えること」とはいったいなんでしょうか。
「教える」とは決して「一方的に何かを伝える」ということではありません。
企業経営における人材育成の意味とは、何でしょうか。
これは最も基本的な問いですが、多くの関係者にとって必ずしも「自明」ではありません。
企業は何のために人材育成をするのかについて、改めて考えたことのない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ともすれば私たちは「そもそも人材育成とは何か」を問わずして、「人材育成をどのように行うか」を考えがちです。
経営学的には、人材育成とは「組織が戦略を達成するため、あるいは、組織・事業を存続させるために持っていてほしい従業員のスキル、能力を獲得させることであり、そのための学習を促進すること」であるとされています。
あくまで「手段」であって、「目的」ではないということです。
それでは、その「目的」とは何でしょうか。
いったいどのような場合、どのような機会を通して、「人材育成」が「企業の経営活動に資する行為」すなわち、「経営の役に立つ」ことになるのでしょうか。
また、中長期のレンジで人材育成の流れを見ていくと、歴史的に普遍的かつ不変的な人材育成手法も存在しないことにも留意しなくてはなりません。
人材育成のあり方は、自社の戦略、外的環境の変化に応じて、常にベストなあり方が変化していくのです。
帰納法と演繹法の違いとは?問題解決との関係って?(パート4)
うーむ・・・
どっ・・・、どーでしょう???
「そっ・・・、そーだったのかー! ガ━━(= ̄□ ̄=)━━ン!! 」
「だからかー!!だからだったのかー!! ヾ(.;.;゜Д゜)ノ 」
という方も、いらっしゃれば・・・
「ナルホド・・・、ちょっぴりわかった気がするかも・・・ ヽ(´ー`)ノ 」
「あ、なーんだー、そーだったんだ~ (〃▽〃) 」
という方も、いらっしゃれば・・・
「わかったよーなわからんよーな・・・ ( ̄д ̄;) 」
「やっぱ、頭がウニ状態じゃー!よくわからーん! \(  ̄曲 ̄)/ 」
という方も、いらっしゃるんじゃーないでしょうか?
他にも、例えば・・・








などなども含めると、いろんな意味で考えさせられちゃいません? (^^)
ふーむ・・・、こーやって考えてみると・・・
まだ見えていないだけで・・・
意外なところにヒントがいっぱい溢れている
おお~っ ━━━━ヽ(゜Д゜)ノ━━━━ 見っけ~♪
のかも~???
なーんて、感じません?
(〃▽〃)
どっ・・・、どうでしょう???
皆さまは、どう思われますか?




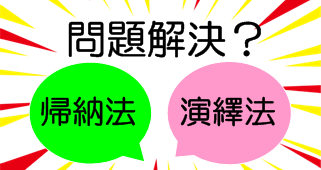
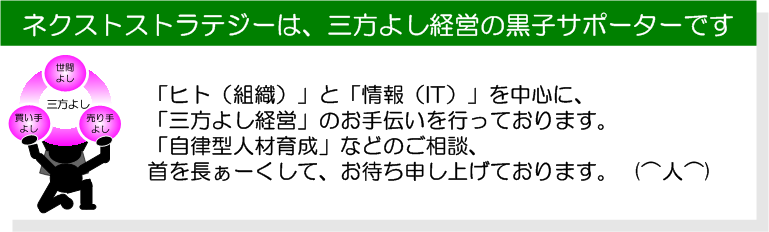
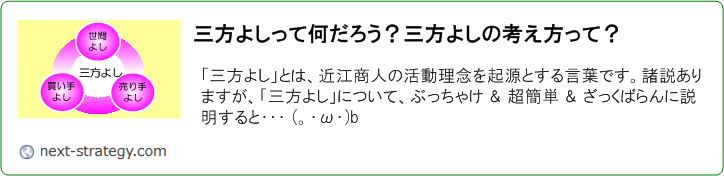


コメント