「コンセンサスって何だろ~? ( ̄ー ̄?)」
「日本語では合意形成って言うみたいだけど、合意形成って何をすればいいんだろ~?合意に至るには何をどーすればいいんだろ~? (・_・;) 」
「コンセンサスと経営方針って、何がどう関係するんだろ~? (;゜∇゜) 」
「コンセンサスと組織力って、何がどう関係するんだろ~? ( ̄○ ̄;) 」
「社内コンセンサスって、どんな時に必要なんだろ~? o( ̄_ ̄|||)o 」
「ちゃんと説明もしたし社内コンセンサスを図ったつもりだったんだけど、合意したつもりはないって後で言われちゃったことがあるんだよね・・・、コンセンサスが図れているかいないかって、どんな基準でどう判断すればいいんだろ~? (ーー;) 」
「会議を何度やっても長時間やっても、社内コンセンサスが得られない原因って何だろ~?説明の仕方が悪いのかな~?どーしたらコンセンサスが得られるんだろ~? (・・、) 」
「これが会社の方針だって言っているのに、不平・不満をたらたら言われちゃうんだよね、コンセンサスはちゃんと得られているはずなのに、何をどう説明しても文句ばっか言われちゃうのって何でなんだろ~??? (o´д`o)=3 」
などなど、このような疑問の声をお聞きすることもあるんですが・・・
( ´・ω・`)
「経営理念・ビジョン・経営計画等の作成」、「組織人事戦略(戦略的な組織づくり)」、「組織力の強化や向上」、「経営に役立つ情報活用(IT活用・ICT活用)」などのお手伝いを行なっているからなのか・・・
「爆発・炎上・崩壊組織」で消防のお手伝いを行なうこともあるからなのか・・・
こーゆー疑問って意外と大事
なんじゃーないかな~???
o(*⌒O⌒)b
もしかしたら・・・
失敗から学んだり、ピンチをチャンスに変えるきっかけにもなり得る
場合もあるのかも~???
なーんて感じることもあるのと、それにコレってもしかしたら・・・











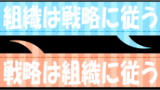




などなどにも、ある意味関係するっちゃーする面もあるのかも~???
なーんて感じるコトもあるので、一緒に考えてみません? (^^)
あ、モチロン、「自律的に」という意味で。
ちょっと興味あるかも~?
って言ってくださる方は、お付き合いいただけると嬉しいです。
(^^)/
コンセンサスとは?合意形成と組織力の関係って?(パート1)
んーと・・・、もしかしたら・・・

なんかにも、ある意味関係するかもしれないので、例えばこんなのからまずは考えてみるのはどーでしょう?
(。・ω・)b
コンセンサスとは?
○ Weblio辞書
意見の一致。全員の同意。
反対意見がないこと。
合意。共感。
○ コンセンサスとは?
コンセンサスは、「関係者全員の合意と納得で結論を出す」という意味です。
英語の consensus のことで、元の意味は一致、同意、合意、大多数の意見、相違、世論などの意味です。
日本では、同意・合意を得るまでの説明、作業、手続きなども含めて「合意形成」の意味で使います。
対象のコンセンサスが得られないと思い通りにならない、というような使い方をします。
○ はてなキーワード
意見の一致。総意。
複数人間が合意すること。
英語と同じ意味に加えて、「根回し」を意味することが多い。
上司から部下への業務指示に際して使われる「コンセンサスをとっておくように」は、「あとあとこちらに火の粉が降りかからないように、万事確認しながらうまくやっておくように」の意がこめられた業務の丸投げの最終通告であることも少なくないので注意が必要。
合意形成とは?
○ ウィキペディア
合意形成とは、ステークホルダーの意見の一致を図ること。
コンセンサスともいう。
特に議論などを通じて関係者の根底にある多様な価値を顕在化させ、相互の意見の一致を図る過程のことをいう。
「議論の場の設定、議論の公開、十分な情報提供」が公正に守られるシステム作りが必要だという指摘がある。
特定の協定が結ばれた共同体の介入を防ぐ前提が必要であるため、明確化を図り知識を共有化することで特定の協定を明示知にする。
これにより直接関与しないステークホルダーに対しても判断材料を提供する。
根回しとは?
○ コトバンク
正式の交渉や会議に先立って、これを円滑かつ有利に運ぶため、非公式な場で、通常個別的に、説得や妥協を通じて事前に合意形成を図る政治技術をいい、下工作ともいう。
元来は園芸上の用語。
根回しは、
- 争点が公になる以前に行われるもの
- 対立が明確になってから行われるもの
- 交渉・会議がいったん決裂に陥ってから行われるもの
の3種類に分けられる。
まず争点が浮上する以前の根回しは、予想される反対派が反対を公にするまえにその反応を探って妥協を図ったり、相手方の機先を制して中間派を味方に引き入れたり、反対派が対応を準備するまえに正式の決定に持ち込んだりするために行われる。
○ exBuzzwords
根回しとは、決済権者に対して正式な決済を依頼する前に、前もって決済の内容について協議や説明をしておくことにより、正式な決済依頼について迅速に事が運ぶように配慮すること。
基本的には、稟議や会議体において、複数人の多数決等により決裁がなされる場合に行われることが多く、決済権者がひとりの場合に行われることは少ない。
合意とは?
○ goo辞書
互いの意思が一致すること。
法律上は、当事者の意思表示が合致すること。
○ はてなキーワード
当事者の意思表示が合致すること。
議論を通じて約束を見出すこと。
同意とは?
○ Weblio辞書
相手と同じ意見・考え。
また、同じ考えであることを意思表示すること。
他の者の行為について賛成ないし是認の意思表示をすること。
○ はてなキーワード
既存の意見に賛成すること。
決められた約束を受け入れること。
総意とは?
○ Weblio辞書
全員の意見や意思。
○ ウィキペディア
総意とは、全員の一致した意見・考え。
組織全体を構成する構成員全体の直接または間接による意思表示によって帰結される意思、即ち全体に共通する意志の事である。
また、組織または団体の比較多数または一定機関の意思により総意と表現する場合もある。
コンセンサスとは?合意形成と組織力の関係って?(パート2)
で・・・
次に、例えばこんなのからも考えてみるのはどーでしょう?
( っ・ω・)っ
何一つ合意できないばかりか、話し合いすら成立しないとき
■ 「(日本人)」
日本人、中国人、インド人、アラブ人がひとつのテーブルを囲んだとしよう。
このとき日本人が武士道を、中国人が儒教を、インド人がヒンドゥー教を、アラブ人がコーランの教えを持ち出したら、何一つ合意できないばかりか、話し合いすら成立しないだろう。
日本企業における意思決定の方法はコンセンサスが基本
■ 「日本の競争戦略」
日本企業における意思決定の方法は、コンセンサスを基本としている。
日本企業では「稟議書」や「根回し」といった方法によって、誰一人として意思決定のプロセスからはみ出るものが出ないようにしている。
稟議書は、ある提案の発案者が、組織のあらゆるレベルの人間の同意を得たことを確認して初めて、経営トップの判断を仰ぐプロセスである。
また、根回しは、ある提案が公式のものになる前の段階で、様々な組織メンバー間の意見の基礎固めをする非公式プロセスである。
日本型企業モデルにおけるリーダーシップ・プロセスは、コンセンサスを追求することを特徴とする。
稟議書による意思決定プロセスは、懸案事項に対する意思表明の機会をすべてマネジャーに提供することによって、コンセンサスを形成し、その実施を円滑に進めた。
公式な組織内における非公式なグループによる議論を通じて、意思決定の叩き台が形成された。
QCやTQCは、コンセンサスの形成や会社志向を助長した。
このように多くの公式、および非公式な形での従業員の経営プロセスへの参加は、高い品質水準の達成と製造現場における漸進的なイノベーションの導入に貢献した。
稟議書による意思決定プロセスや終身雇用制、年功序列制度よりもむしろ、日本的経営の成功に貢献している。
このような状況を考慮すれば、大多数の現役の経営陣が職場の調和を過敏なまでに重視することはそれほど驚くべきことではない。
しかしながら、いずれのプロセスも、話し合いやコンセンサスの形成に膨大な時間を要する。
このようなプロセスは、戦略的ポジショニングの確立に際して深刻な弊害を伴う。
まず、あまりにも多くの承認を必要とするために、これは大胆または独自性のある戦略が遂行されないことをほとんど保証するようなものである。
なぜなら、ある事業部に有利で、他の事業部には不利となるような提案が通り、トレードオフが行われる可能性がほぼないからである。
さらに、ひとたび多くの関係者の承認を得てしまうと、たとえその製品や事業が成功しなかった場合でも、撤退するのが非常に難しくなる。
みんなが一つの意見に染まっていることは、とても危険な状態
■ 「本質を見抜く「考え方」」
「全員一致したら、その決定は無効」
これはユダヤ人がサバイバルのために見につけてきた、歴史の大教訓です。
何かを決める際に、全員一致の決定は無効になり、また一から議論をやり直さなければいけません。
全員一致などありえないことで、もしも全員一致するようなことがあれば、それはもう誰一人として、真剣に考えていない証拠であるとみなすわけです。
みんなが一つの意見に染まっているということは、とても危険な状態だといえます。
それが間違っていたり崩れたりしたときに、全員が共倒れになってしまうからです。
みんなが言っていることが正しいとは限らない。
それはかえって危険信号なのだと認識することが大切です。
なかでも強敵なのが、相手が最初から自分の都合のいい結論を持っていて、「先に結論ありき」の論理を組み立てているときです。
本来、ものごとを考えるとか、議論するとかというときは、まだ結論が出ていない問題だからこそ、そうした議論や考察が必要なわけです。
ところが、ときとして最初から特定の結論があり、それをあたかも自由な討論の末に出てきた結論のように見せかける議論が行なわれることがあります。
「ディベート」の本では、誰も反対できない大義名分をスローガンとして声高に叫んだり、数字や論理を戦術として上手に利用したりせよと教えています。
たしかにそういった論戦では有効でしょうが、個人対個人の心からの納得を得られるものではありません。
人間は「絆を求める動物」です。
相手を心から理解するためには、お互いに考えていることを聞いて、人間的な接触を通して本音を打ち明け合う、それが肌身感覚というものだと思います。
ふと浮かんだ疑問は、自分の正直な感覚です。
ものごとを考えるときは、冷静な情報分析も必要ですが、この「感覚」がものをいうことも多いのです。
情報を見るときは、自分の実感が大切なのです。
実感として「こうじゃないのか?」と肌身で感じた疑問は、無理に押さえつけないことが必要です。
肌身感覚や皮膚感覚といったファジーな感覚は、すべての人間が生まれながらに持っている、危機回避のために備わった能力、つまり安全装置なのかもしれません。
頭で正しいと判断しても、何かのシグナルを察知したときは、立ち止まってもう一度振り返るという、そんな心の強さを身につけておきたいものです。
大切なことは、調整責任と決定権限はセットということ
■ 「ヒーローを待っていても世界は変わらない」
私には私の意見があり、別の人には別の意見がある。
それが当たり前です。
逆にそうでなければ気持ち悪い。
みんなが同じ意見を持っているような社会は、自由な社会とは言えないでしょう。
だから、異なる意見を闘わせ、意見交換や議論をする中で、お互いの意見を調整することが必要となります。
夫婦や親子のような親しい間柄でも、自分の意見や意向だけを一方的に主張し、「おれの言うことを聞かないおまえが悪い」と言い続けていたら合意形成に至らないことは、誰もが経験していることだと思います。
国レベルでも同様で、自国の言いたいことだけ言い合っていたら、すぐに戦争です。
そうならないための技術として「外交」があります。
しかしそれは面倒なことでもあります。
世の中には、物事をすぐに「決めつける」人も、何度言ってもこちらを理解しようとしない「わからず屋」も、たくさんいます。
そしてお互いに、自分は柔軟で、異なる意見を受け容れる力を持っているが、相手こそが「決めつける人」で「わからず屋」だと思っています。
しかしそれでも、誰かに任せるのではなく、自分たちで引き受けて、それを調整して合意形成していこうというのが、民主主義というシステムです。
したがって民主主義というのは、まず何よりも、おそろしく面倒くさくて、うんざりするシステムだということを、みんなが認識する必要があると思います。
面倒くさくて、うんざりして、そのうえ疲れるシステムである以上、投げ出したくなるのは人情です。
自分で他人と調整するのは大変です。
誰かがその面倒くさい作業を担ってくれたほうが楽です。
その場合、私たちには「民主主義を放棄する」という選択肢があります。
王制なら王様が決めてくれます。
その代わり、その面倒で疲れることを引き受けて調整して決めてくれた人たちの決定には黙って従います、という選択です。
このとき大切なことは、調整責任と決定権限はセットということだ、と私は考えています。
なるべく自分たちで決めたければ(決定の権限を持ちたければ)、自分たちで調整責任を背負わないといけない。
調整責任を委ねるならば、決定権限も委ね、それには従わなければならない。
調整は面倒くさいから嫌だ、しかし決定はさせろというのは、実際問題として成り立たない。
自分たちは要求はする、しかし調整はしないという態度は、結局、
「誰かが調整してくれ」
「ただし、自分の要求を通すように」
と言っていることと変わりません。
合意形成する前には、必ず「合意のない状態」がある
■ 社会的合意形成
「合意形成」とは、文字通り「合意を形成する」ということです。
逆に言うと、合意形成する前には、必ず「合意のない状態」があるわけです。
意見をまとめようというときに、ひとびとの意見がぶつかっている、対立している、反対を向いている。
こんな状態ですね。
では、社会におけるこうした対立が、悪化するとどうなるでしょう。
個人間ですと喧嘩になりますね。
もっと深刻な争いになると訴訟になったり、さらに意見が対立している集団の規模が大きいと、紛争になったり、最後には、戦争になったりします。
そこで、このような「意見の対立」が悪化しないよう、話し合いを行い、その結果、みんなの意見をまとめて、問題解決を図る。
これが「合意の形成」です。
家庭や企業における当事者は、常に特定できます。
誰と誰とが争っているかが明確にわかります。
けれども、社会の場合は特定が難しいんですね。
対立する当事者の範囲が明確でないことがしばしばある。
そんな状況で合意を形成すること。
これを、社会的合意形成と呼んでいるわけです。
社会というのは、そもそもが曖昧なんですね。
ここからここまでがひとつの社会、と線引きしにくい。
利害の一致しない当事者同士だと、意見が対立したまま、状況が硬直してしまい、開発も保全もできない、というようなことになりがちです。
合意すれども、船は動かず
■ 「ダイアローグ 対話する組織」
どうも従来のコミュニケーションでは、「伝わっていない」ことがある・・・
コミュニケーションが希薄なせいか、人と人とのつながりも失われた気がする。
こうした危機感は、実は無意識に多くの組織で共有されているように思います。
しかし、社内で価値観を共有し、社員の結束力を高めるため、会社の命令で半ば強制的に親睦を深めるのは、果たして今のビジネスの環境にマッチしたやり方なのでしょうか。
そもそも高度経済成長期に社員が価値観や行動規範を共有できたのは、社内運動会や飲み会のおかげだったのでしょうか。
年功序列と終身雇用、右肩上がりで給料が上がっていき、ずっとここで暮らしていけるという家族主義的な企業観が社会全体に広がっていた。
悪く言えば、組織全体が企業に隷属する個人の集団だったからこそ、運動会も飲み会もコミュニケーションの手段のひとつになり得ただけではないでしょうか。
非日常の社内運動会や社員旅行では会社に隷属することを求められ、日常的には自律した個人として成果をあげることが求められる・・・
このようなやり方で、価値観や行動規範が「何も言わなくても伝わる」昔のような組織の「絆」が生まれるのでしょうか。
日本全体が、大量生産を行えば、今日より明日、明日より明後日、自分たちはさらに裕福になれるという「大きな物語」を共有しているとき、企業にとって取り組むべき問題は明確であり、何をすれば会社の利益になるのかを社員全員が共有することも、特に難しいことではありませんでした。
だから、相互に理解を深めていくための「対話」に多くの時間を費やすよりも、疑う余地のない共通の目標に向かって、休むことなく全力で突き進むことが大切だったのです。
しかし、今日の企業にとっては「取り組むべき問題は何か」ということ自体があいまいで、流動的なものになっています。
このような社会にあっては、社員の価値観や信念も多様化し、「上からの命令には疑問をもたず、一糸乱れずまっすぐ進め」といった古い時代のロジックは通用しません。
むしろ一人ひとりが
「そもそも、このプロジェクトは何をめざすのか」
「そもそも、この製品の存在意義は何か」
を主体的に考え、あいまいで、流動的な「めざすべき方向」を共に探索していく、協同的な思考プロセスをつくり上げていくことが必要になりました。
「早く走ること」よりも「深く考えること」が求められる時代だと言っていいかもしれません。
そして、それぞれが「深く考えたこと」を、どのように行動につなげていくか。
そのためには、お互いの理解を共有し合うプロセスが必要となるでしょう。
「人間同士の間にコミュニケーションが成立すること」は、ふだん考えているよりも、ずっとずっと難しい行為であることを私たちは認識したほうがよいでしょう。
「議論」とは最終的に何かについて意思決定する場だということです。
つまり、「いくつか選択肢があったうちのどれが正しいのか、輪を戦わせ、どちらかを捨てて、どちらかをとる」ということが「議論」の典型的なかたちであり、それを効率化したものが「いい議論」ということです。
残念ながら、「いくつかの選択肢について、輪を戦わせ、どれが正しいか決める」という「議論型」の話し合いでは、「設定された問題が本当に適切なのか」や「他に選択肢の可能性はないのか」といったことが検討されることはありません。
さらに、「唯一の正解」を選択しようとしているため、選択肢の優劣をつけることや、誰かの管理責任を問うことばかりを意識した話し合いとなります。
「対話」というのは、それとはまったく異なるプロセスです。
勝ち負けを決めるディベートでもなければ、互いに最大の利益を追求するための取引でもない。
むしろ、前提となっている選択肢の可能性をもう一度探るとか、評価の基準そのものを再吟味するといった方向に話し合いを進めていきます。
コミュニケーションを「情報の移動」と理解している限りにおいては、共有できているのは「情報」だけ。
相手の考えている価値前提や行動の背景にある世界観を共有していなければ、たとえ妥協点が見つかったとしても、全員が思いをひとつにして行動するなどはできません。
合意すれども、船は動かず。
結局、いいチームワーク、いい組織行動につながらないのです。
組織文化や組織の価値観とは、命令や規則のように押しつけられるものではありません。
組織文化は、それぞれの組織を構成する人々の日常的な経験に根ざしていて、「共通の体験」を語り合い、意味づけしていくことによって生まれるのです。
理念が日常的な行動と結び付くには、その内容について、自分なりに「腹に落ちて」いなければならないのです。
そのためには、理念を言語化された単なる情報として受け渡すのではなく、メンバー一人ひとりが「自分はこう考えている」とか、「自分の意見は少し違う」といった、主体的な姿勢で理念を意味づけていく機会をつくり出す必要があります。
一人で決めることには、暴走する可能性がつきまとう
■ 「なぜ会社は変われないのか」
日本的な物事の決め方というのは、みんなで合議して、お互いに納得できる話し合いができる時はいいが、それができない時は時間切れになって、しかたなく
「とりあえず」
「いちおう」
決めたかたちをとっておく。
曖昧な中身をもちながら形式的な要件だけを整えておくのである。
しかし「とりあえず決めたこと」というのは気持ちのうえでは暫定的なものだから、具体的な実効力をもって展開していかない。
決めたといっても妥協の産物のような決め方だから、話し合ったその当の本人が決まった内容をそれほど重視しているわけではないし、周りも同じようにその内容を信用していない。
さらに問題なのは、誰も「責任をもってフォローする状態になっていない」という点である。
形式上の責任者はいるがフォローがない。
これは責任の範囲が不明確というような問題ではなく、そもそも実質的な意味での責任というものが存在するのかどうか、という問題なのである。
また、過去に不祥事などが起きた経験をもつ企業の場合などは特にそうなのだが、過剰に意思決定のミスを恐れ、何でもかんでも上におうかがいを立てるのが当たり前という習慣になってしまっているケースがある。
本来、下のレベルで判断すべき案件を、上におうかがいを立てるということがいつも行われていると、待ちの姿勢が蔓延し、意思決定の能力をもつ人間がいなくなってしまう。
つまり、上におうかがいを立てることで下は責任を上に預け、上は意思決定に関わっていながらも、直接担当していることではないから、責任は本気で感じていないということが起こり得る。
合議で何かを決めるという決め方の問題も含めて、こういう場面で問題なのは、形式上の責任者の有無ではなくて「誰も心の底から責任を感じていない」という事実なのだ。
一人で決めるというのは、勝手に決めることと同義語ではない。
勝手に決めては誰もついてこない。
どうぞ好きにやってくださいと単に無視されるだけである。
一人で決めることには、常に暴走する可能性というものがつきまとう。
「みんなが納得する」ために一番手っ取り早いのは合議をみんなが納得するところまでやることである。
しかし現実はそんなに簡単ではない。
合議してもみんなが納得する状況にならないケースがあるからである。
「みんなが納得する」必要のある事柄と、そうでなくてもお互いの基本的な信頼関係さえあれば一人で決めてもよい事柄との区別が必要だ。
みんなが納得する必要のある事柄とは、たとえば目標であるとかルールなどがそれである。
決められた事の中身がみんなに関係することは、やはりみんなの納得がなければ機能しない。
コンセンサスとは?合意形成と組織力の関係って?(パート3)
うーむ・・・
どっ・・・、どーでしょう???
「そっ・・・、そーだったのかー! ガ━━(= ̄□ ̄=)━━ン!! 」
「だからかー!!だからだったのかー!! ヾ(.;.;゜Д゜)ノ 」
という方も、いらっしゃれば・・・
「ナルホド・・・、ちょっぴりわかった気がするかも・・・ ヽ(´ー`)ノ 」
「あ、なーんだー、そーだったんだ~ (〃▽〃) 」
という方も、いらっしゃれば・・・
「わかったよーなわからんよーな・・・ ( ̄д ̄;) 」
「やっぱ、頭がウニ状態じゃー!よくわからーん! \(  ̄曲 ̄)/ 」
という方も、いらっしゃるんじゃーないでしょうか?
他にも、例えば・・・






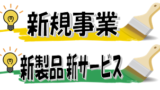






などなども含めると、いろんな意味で考えさせられちゃいません? (^^)
ふーむ・・・、こーやって考えてみると・・・
まだ見えていないだけで・・・
意外なところにヒントがいっぱい溢れている
おお~っ ━━━━ヽ(゜Д゜)ノ━━━━ 見っけ~♪
のかも~???
なーんて、感じません?
(〃▽〃)
どっ・・・、どうでしょう???
皆さまは、どう思われますか?





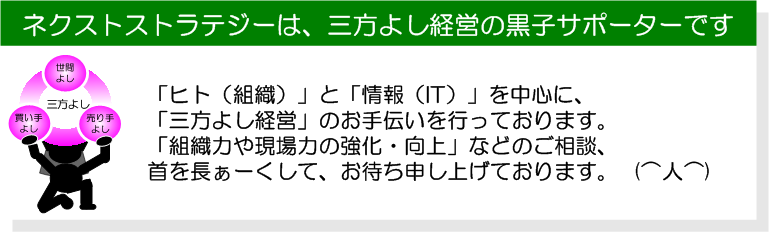
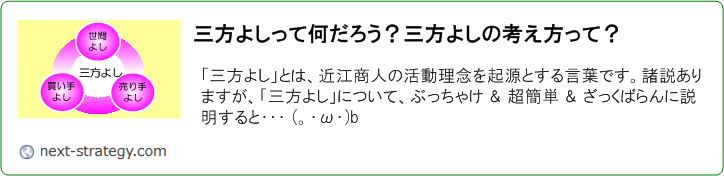


コメント